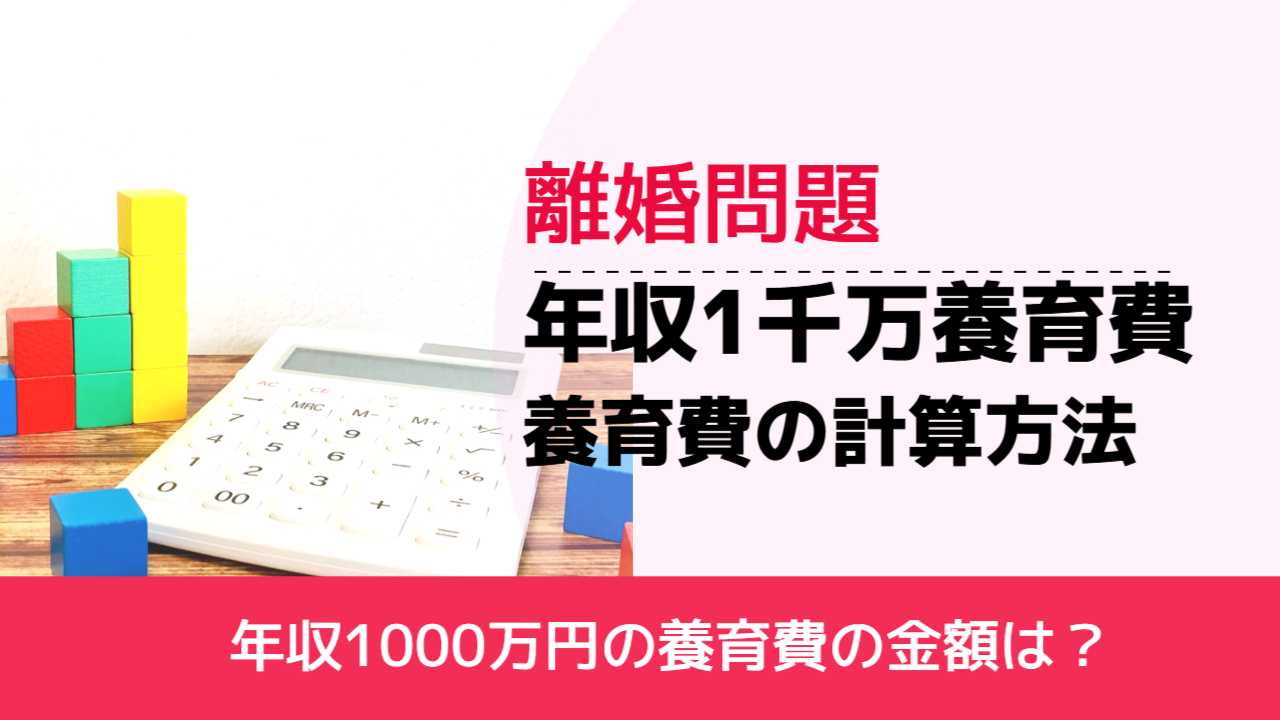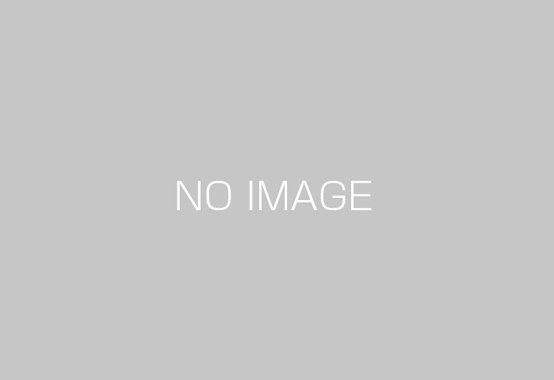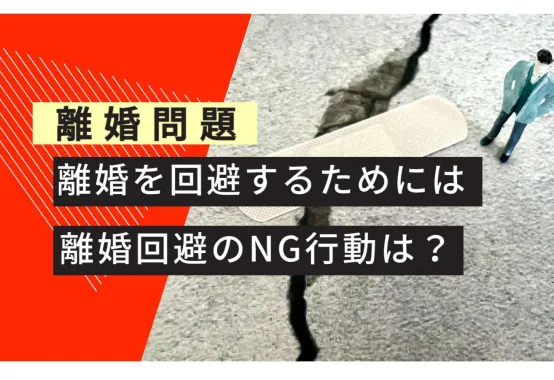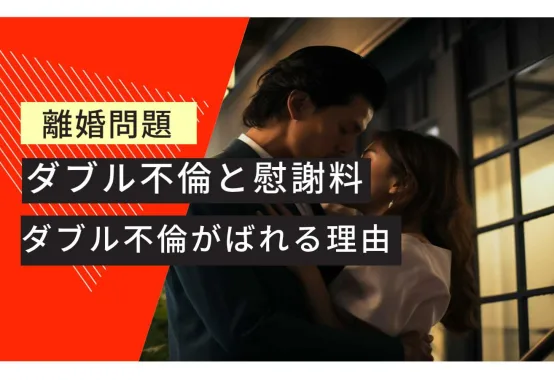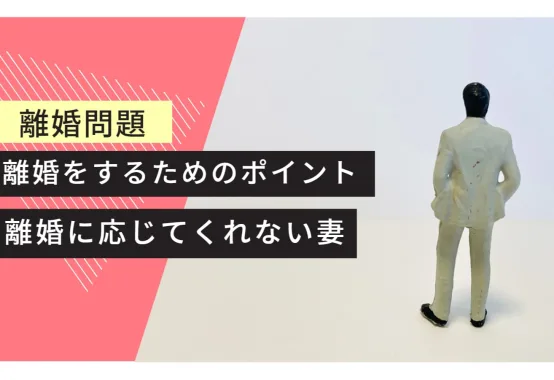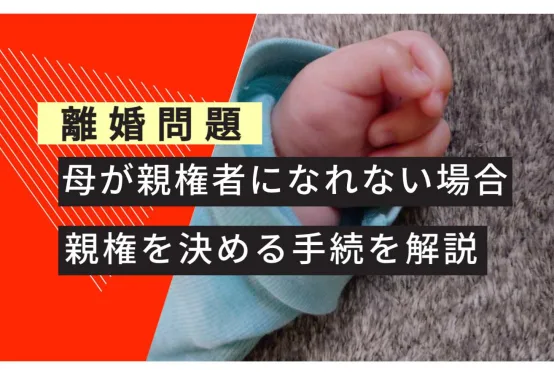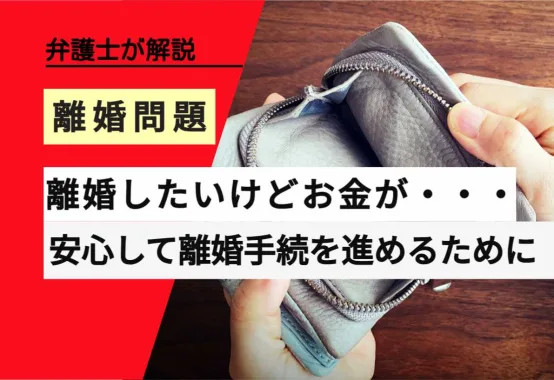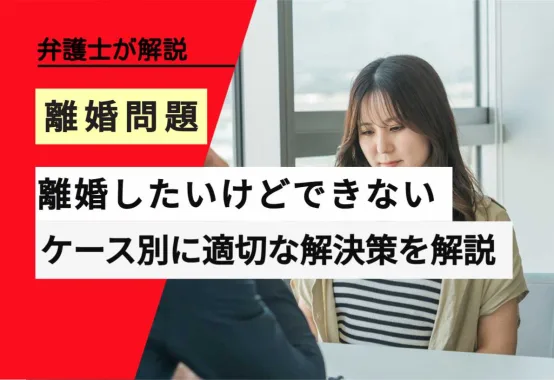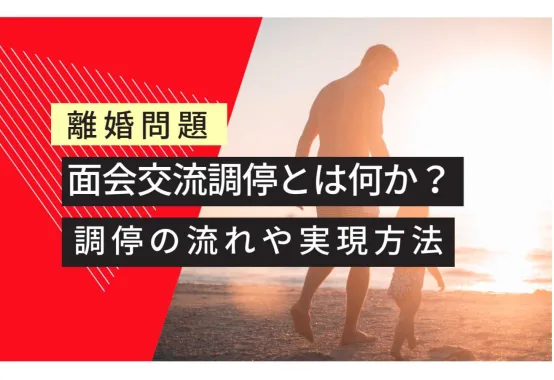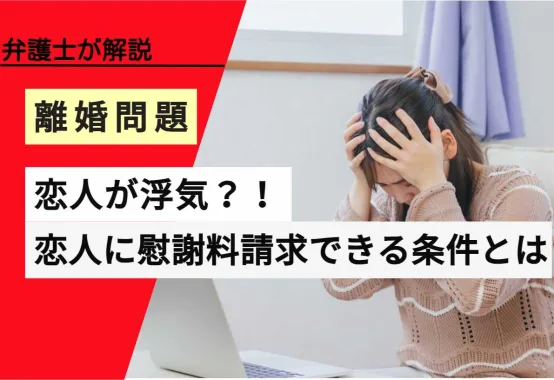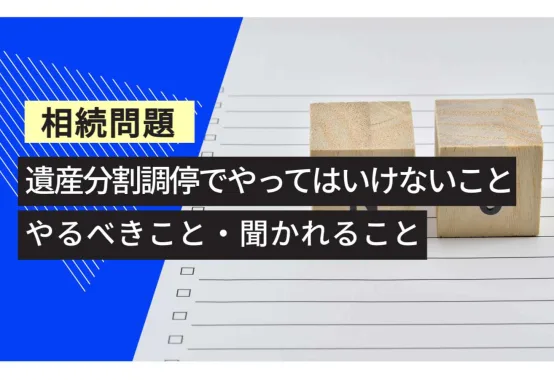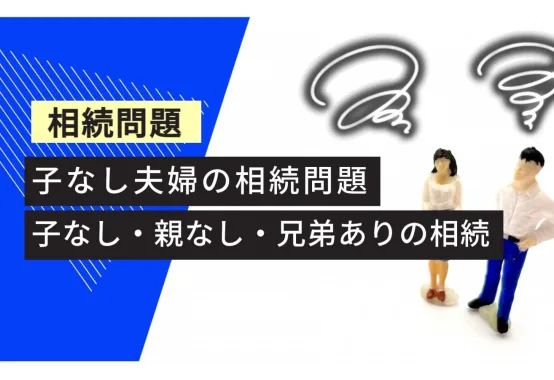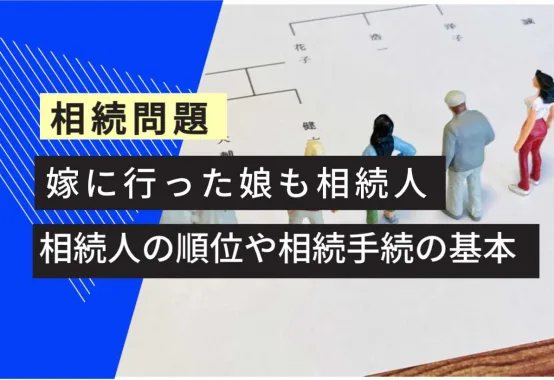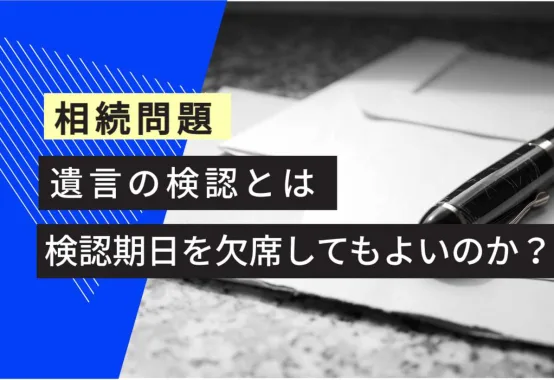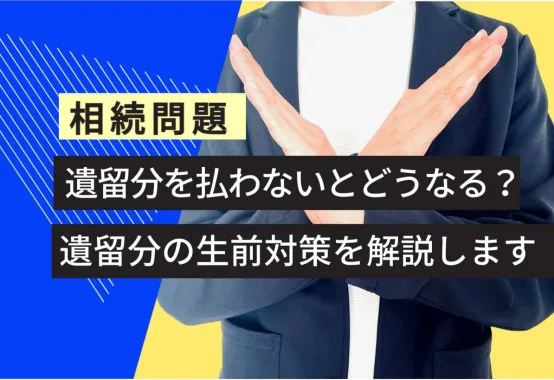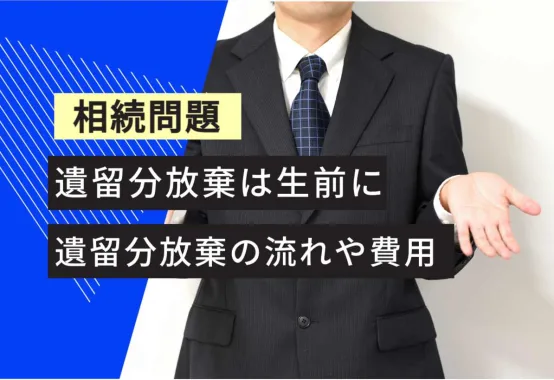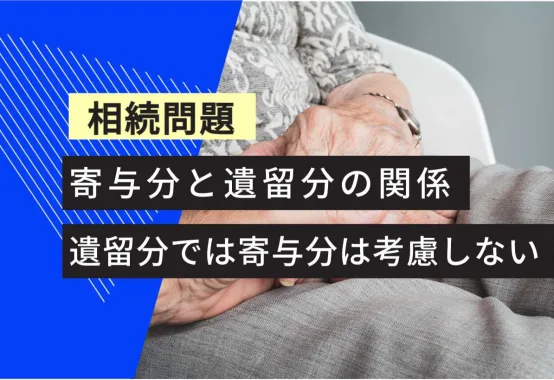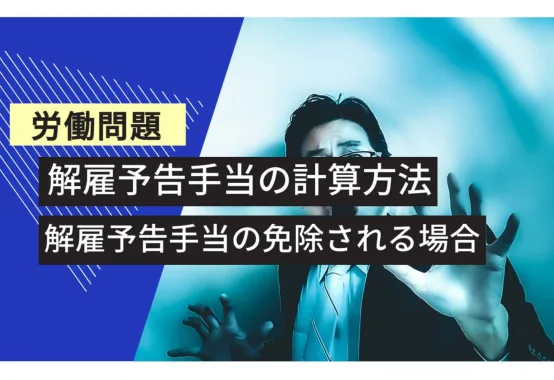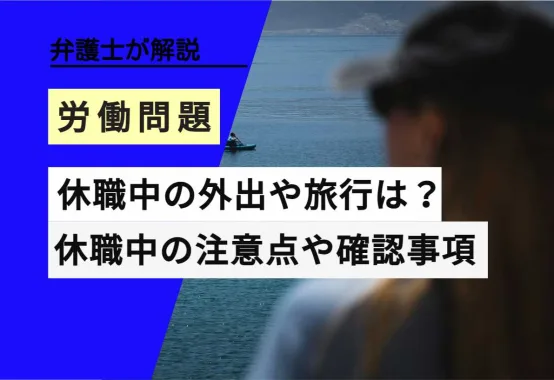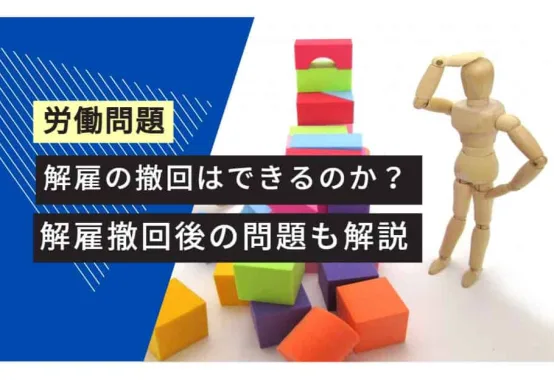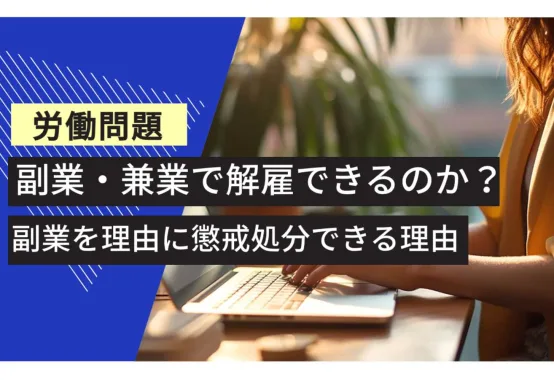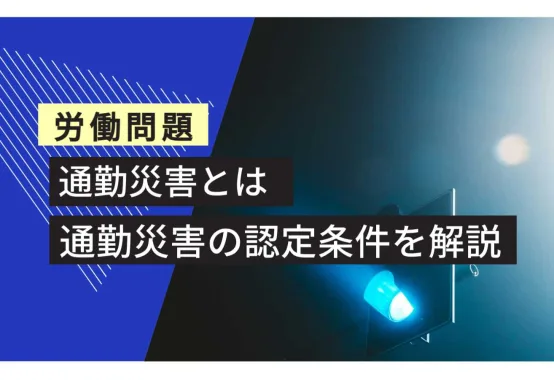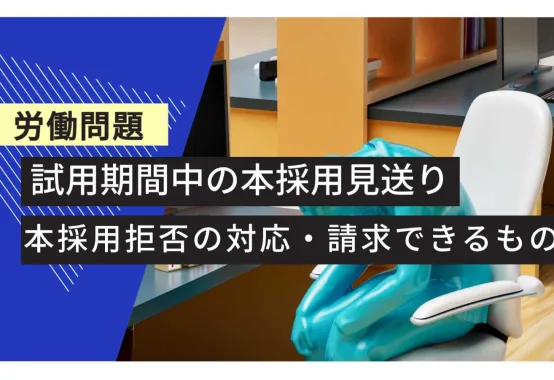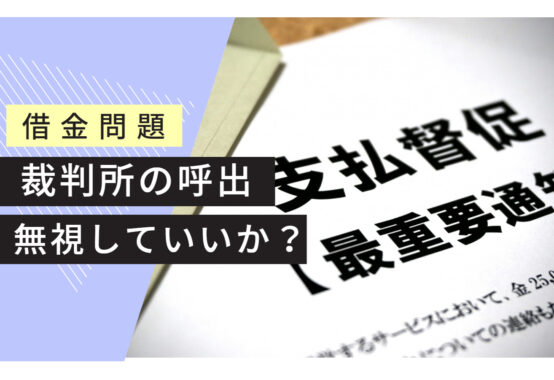元配偶者の年収が1000万円の場合、高額の養育費を受け取れる可能性があります。
ただし、養育費は父母の収入額に応じて形式的に決まる部分があります。そのため、同居している時に受け取っていた生活費よりも、低くなる可能性もあります。
この記事では、年収1000万円の親が支払う養育費の相場をケースごとに紹介します。併せて、養育費の不払いや減額請求に対する対処法なども解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
養育費とは?
養育費とは、子どもが成熟して自活できるようになるまで育てていくために必要な費用のことです。
衣食住などの生活に必要な費用はもちろんのこと、教育費や医療費、相応の交際費や娯楽費など、子育てに必要な費用はすべて養育費に含まれます。
離婚して親権を失った側の親も、子どもに対しては自分と同水準の生活を保障しなければならない扶養義務を負っています。
年収1000万円の養育費の算出方法

養育費の適正な金額は、主に両親の年収や子どもの人数・年齢によって決まります。そのため、裁判所はこれらの要素を重視して養育費の金額を計算する方法を打ち出しています。
以下で、裁判所が発表している養育費の計算方法を解説します。元配偶者の年収1000万円の場合も、以下の計算式で養育費の金額を算出することになります。
養育費算定表による養育費の計算方法
裁判所は、養育費を簡単に計算できるように、「養育費算定表」という早見表を公表しています。
この算定表で養育費を計算するには、まず、裁判所のホームページに掲載されている表の中から、子どもの人数と年齢に該当するPDFを開きます。
例えば、3歳の子どもが1人いる場合は「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)」というタイトルの表を開きましょう。
算定表には、両親の年収に応じた養育費の目安(相場)が記載されています。権利者の年収に該当する行を横に、義務者の年収に該当する列を縦に見ていき、両者が交差するところに記載されている金額が、養育費の相場です。

標準算定式による計算方法
裁判所の養育費算定表には、あらゆるケースが網羅されているわけではありません。子どもが4人以上いる場合や、複数いる子どもの親権者が別々になったような場合、算定表では養育費の金額が分かりません。このような場合には、標準算定式によって養育費を計算する必要があります。
計算式
養育費の標準算定式は、以下のとおりです。
子供の生活費×支払義務者の基礎収入÷(支払義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)÷12ヶ月
子供の生活費
「子どもの生活費」は実際に支出している金額ではなく、次の計算式によって一般的に必要と考えられる金額を割り出します。
支払義務者の基礎収入×子供の生活費指数÷(親の生活費指数+子供の生活費指数)
生活指数
「生活費指数」は厚生労働省の統計に基づく数値であり、親が100、0~14歳の子どもが62、15歳以上の子どもが85とされています。
基礎収入
「基礎収入」とは、両親の年収から税金や諸経費を差し引いた金額のことです。実際の年収に対して、所定の基礎収入割合を掛けて算出します。年収1000万円の場合の基礎収入割合は、給与所得者で40%、事業所得者で51%とされています。
基礎収入の計算
給与所得者であれば、支払総額に基礎収入割合を掛けます。事業所得者であれば、「課税される所得金額」から「実際に支出していない費用」を差し引いた残額に基礎収入割合をかけます。
計算例
一例として、義務者の年収1000万円(給与所得)、権利者の年収200万円(給与所得)、3歳の子供が1人いるケースで計算してみると、次のようになります。
子供の生活費(約153万円)×支払義務者の基礎収入(400万円)÷(支払義務者の基礎収入(400万円)+権利者の基礎収入(80万円))÷12ヶ月=10万6,250円
毎月の養育費は10万6,250円で、算定表による相場(10~12万円)の範囲内となっています。
給与所得者と自営業者の養育費算定基準の違い
養育費算定表の収入欄には、『給与』と『事業』の区分があります。
父母の収入の種類が給与所得であれば、給与に当たります。サラリーマンや公務員の収入が給与に当たります。
給与所得者の収入額は、源泉徴収票の支払額を指します。つまり、天引きされた手取額ではなく、控除される前の額面を指します。
個人事業主の収入や役員報酬は、事業収入に区分されます。
事業収入の場合、確定申告書における「課税される所得金額」から「実際に支出していない費用」を差し引いた残額を年収とします。
実際に支出していない費用とは、基礎控除、青色申告特別控除額、生命保険料控除などが該当します。
年収1000万円の養育費の計算例(母に収入がある場合)
それでは、支払義務者の年収が1000万円の場合における養育費の相場を、ケース別に養育費算定表を使って計算してみましょう。
支払義務者の年収が1000万円の場合、権利者の年収が200万円だとすると、子供の年齢別、人数別の養育費の相場は以下のようになります。
当然ながら、子供の人数が多くなるほど、また年齢が高くなるほど、養育費の相場は高くなります。
1人の場合
子供が1人の場合における養育費の相場は、以下のとおりです。
養育費算定表
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 0~14歳 | 10~12万円 |
| 15歳以上 | 12~14万円 |
標準算定方式
| 子供の年齢 | 養育費の相場 | 計算式 |
| 0~14歳 | 10万4997円 | 1000万円×40%=400万円 200万円×43%=86万円 400万円×62/162=153万864円 153万864円×400/486=125万9970円 125万9970円/12月=10万4997円 |
| 15歳以上 | 12万6051円 | 400万円×85/185=183万7837円 183万7837円×400/486=151万2623円 151万2623円/12月=12万6051円 |
2人の場合
子供が2人の場合における養育費の相場は、以下のとおりです。
養育費算定表
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 2人とも0~14歳 | 14~16万円 |
| 第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 16~18万円 |
| 2人とも15歳以上 | 16~18万円 |
標準算定方式
| 子供の年齢 | 養育費の相場 | 計算式 |
| 2人とも0~14歳 | 15万1871円 | 400万円×124/224=221万4285円 221万4285円×400/486=182万2457円 182万2457円/12月=15万1871円 |
| 第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 16万3276円 | 400万円×147/247=238万566円 238万566円×400/486=195万9314円 195万9314円/12月=16万3276円 |
| 2人とも15歳以上 | 17万2737円 | 400万円×170/270=251万8518円 251万8518円×400/486=207万2854円 207万2854円/12月=17万2737円 |
3人の場合
子供が3人の場合における養育費の相場は、以下のとおりです。
養育費算定表
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 3人とも0~14歳 | 16~18万円 |
| 第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 18~20万円 |
| 第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 18~20万円 |
| 3人とも15歳以上 | 18~20万円 |
標準算定方式
| 子供の年齢 | 養育費の相場 | 計算式 |
| 3人とも0~14歳 | 17万8422円 | 400万円×186/286=260万1398円 260万1398円×400/486=214万1068円 214万1068円/12月=17万8422円 |
| 第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 18万5562円 | 400万円×209/309=270万5501円 270万5501円×400/486=222万6750円 222万6750円/12月=18万5562円 |
| 第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 19万1713円 | 400万円×232/332=279万5180円 279万5180円×400/486=230万560円 230万560円/12月=19万1713円 |
| 3人とも15歳以上 | 19万7067円 | 400万円×255/355=287万3239円 287万3239円×400/486=236万4806円 236万4806円/12月=19万7067円 |
母が無職である場合(潜在的稼働能力の有無)
支払義務者の年収が1000万円でも、受取権利者の年収によって養育費の金額は変わります。母(受取権利者)が無職で年収0円の場合は、上記の相場よりも養育費が高くなります。
しかし、働けるにもかかわらず養育費をあてにして働かない母にまで、相場どおりの養育費を支払うのは不公平です。
そのため、受取権利者が働こうと思えば働けるにもかかわらず働かない場合は、潜在的稼働能力があるものとして年収を想定し、養育費を計算することもあります。
潜在的稼働能力がある場合
母が無職であるものの潜在的稼働能力があり、100万円~120万円程度の年収は得られるはずだと想定できる場合、子供の年齢別、人数別の養育費の相場は以下のようになります。
【子供1人、支払義務者の年収1000万円、権利者の年収100万円のケース】
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 0~14歳 | 10~12万円 |
| 15歳以上 | 12~14万円 |
【子供2人、支払義務者の年収1000万円、権利者の年収100万円のケース】
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 2人とも0~14歳 | 16~18万円 |
| 第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 16~18万円 |
| 2人とも15歳以上 | 18~20万円 |
【子供3人、支払義務者の年収1000万円、受取権利者の年収100万円のケース】
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 3人とも0~14歳 | 18~20万円 |
| 第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 20~22万円 |
| 第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 20~22万円 |
| 3人とも15歳以上 | 20~22万円 |
潜在的稼働能力がない場合
母が持病などで働けず、潜在的稼働能力がない場合、子供の年齢別、人数別の養育費の相場は以下のようになります。
【子供1人、支払義務者の年収1000万円、受取権利者の年収0円のケース】
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 0~14歳 | 12~14万円 |
| 15歳以上 | 14~16万円 |
【子供2人、支払義務者の年収1000万円、受取権利者の年収0万円のケース】
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 2人とも0~14歳 | 18~20万円 |
| 第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 18~20万円 |
| 2人とも15歳以上 | 20~22万円 |
【子供3人、支払義務者の年収1000万円、受取権利者の年収0円のケース】
| 子供の年齢 | 養育費の相場 |
| 3人とも0~14歳 | 20~22万円 |
| 第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 20~22万円 |
| 第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 22~24万円 |
| 3人とも15歳以上 | 24~26万円 |
母が無職であっても、潜在的稼働能力の有無によって養育費の金額に違いが出ることがお分かりいただけるでしょう。
養育費の終期
養育費の支払時期の終わりである「終期」も気になるところでしょう。
結論としては「子供が自活できるほどに成熟するまで」ということになりますが、具体的に何歳までもらえるのかはケースによって異なります。
原則20歳まで
原則的には、子供が20歳になるまで養育費をもらえます。
成人年齢は2022年4月1日から18歳に引き下げられましたが、現在でも一般的には子供が20歳になるころまで親のサポートが必要と考えられています。そのため、家庭裁判所の実務では、現在でも養育費の終期は原則として20歳までとされています。
親の学歴や子の年齢(大学一貫校や大学進学率の高い高校)
子供が小さいうちに離婚する場合、養育費の支払いは20歳までと取り決めるのが一般的です。大学などに進学するための学費については、改めて協議する旨を取り決めておきます。
一方、離婚時に子供が中学生や高校生になっていて、大学までの一貫校や大学進学率の高い学校に在籍している場合は、大学に進学することを前提として養育費を取り決めることもあります。両親ともに大卒で、離婚時の子供の学業成績などから大学に進学する可能性が高いと考えられる場合も同様です。
逆に、離婚時に子供が20歳未満でも、既に就職して自活しているような場合は養育費の請求が認められないこともあります。
離婚後に再婚した場合
離婚時に相場どおりの養育費を取り決めたとしても、その後の事情の変化によって養育費を減額されたり、支払いを停止されたりすることがあります。
その典型的なケースとして、両親のどちらかが再婚した場合が挙げられます。
義務者が再婚した場合
支払義務者が再婚し、再婚相手との間に子供が生まれた場合は、養育費を減額される可能性が非常に高いです。支払義務者には、新たに生まれた子供に対する扶養義務が生じるからです。支払義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合も同様です。
再婚後の家庭に子供がいないとしても、再婚相手に対する扶養義務が生じ、養育費が減額される可能性はあります。この場合には、再婚相手の職業や収入、無職(専業主婦)なら潜在的稼働能力の有無などが考慮されます。
権利者が再婚した場合
受取権利者が再婚した場合も、養育費を減額されることが多いです。
特に、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚相手が第一次的に扶養義務を負います。そのため、元配偶者が支払うべき養育費は大幅に減額されたり、場合によっては支払いを停止されることもあります。
再婚相手と子供が養子縁組をしない場合は、再婚相手に扶養義務は生じません。しかし、受取権利者の生活状況を考慮して養育費が減額される可能性はあります。
養育費の問題に対する対処法
離婚後の養育費は、スムーズに支払ってもらえるとは限りません。むしろ、様々な問題が生じるケースが非常に多いのが実情です。
ここでは、養育費でよく生じる問題と対処法について解説します。
養育費でよく生じる問題
養育費で最も多いトラブルは、「不払い」です。厚生労働省の調査によると、母子家庭で元夫から養育費の支払いを受けている世帯は25%にも満たないということです。離婚時に養育費を取り決めたにもかかわらず、途中で不払いとなるケースは多いです。当初から養育費の支払いに応じない親もいます。
また、養育費の支払いを請求したり、相手の給料を差し押さえたりしようと考えても、離婚してから年数が経っていると所在や就業先が分からなくなっていることが少なくありません。
また、事情の変化による養育費の減額請求も、よくあるトラブルのひとつです。
公正証書を作成する
養育費の不払いを防止するためには、取り決めた内容を離婚協議書や合意書に記載し、公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくことが有効です。
強制執行認諾文言付きの公正証書には法的な強制力があります。そのため、養育費の支払いが滞った場合には、裁判をしなくても相手の給料などを差し押さえて、強制的に回収できるようになります。
第三者からの情報取得で就業先を調査する
給料を差し押さえるためには、相手の就業先を特定しなければなりません。就業先が不明の場合は、民事執行法上の「第三者からの情報取得手続」を利用して調査が可能です。
第三者からの情報取得手続とは、確定した金銭債権を有する人が強制執行(差し押さえ手続きのことです。)を申し立てるために、裁判所を通じて相手の財産を調査できる手続きのことです。
この制度を利用すれば、裁判所から役所(第三者)への情報照会によって、支払義務者の就業先が登録されていればその情報が開示されます。就業先が分かれば、裁判所に強制執行を申し立てて相手の給料を差し押さえることができます。
養育費の問題は弁護士に相談を
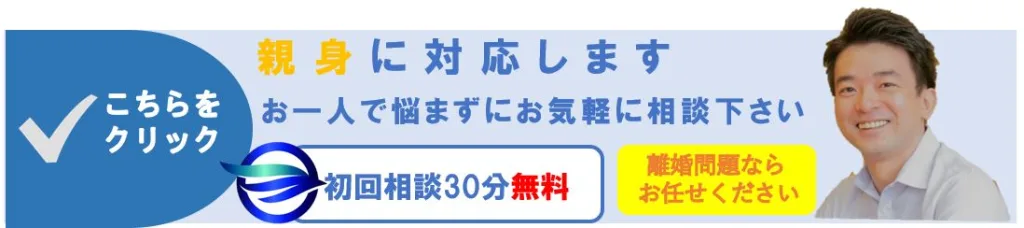
養育費は、子供のための大切なお金です。相手が支払いに応じない、取り決めたのに途中で不払いとなった、納得のいかない減額を請求された、などのトラブルが発生したときは、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士は、相手との話し合いだけでなく、調停や裁判などの法的手段も活用して、適切な養育費の回収を図ります。
養育費の問題でお困りの方は、一度、弁護士に相談してみるよとよいでしょう。