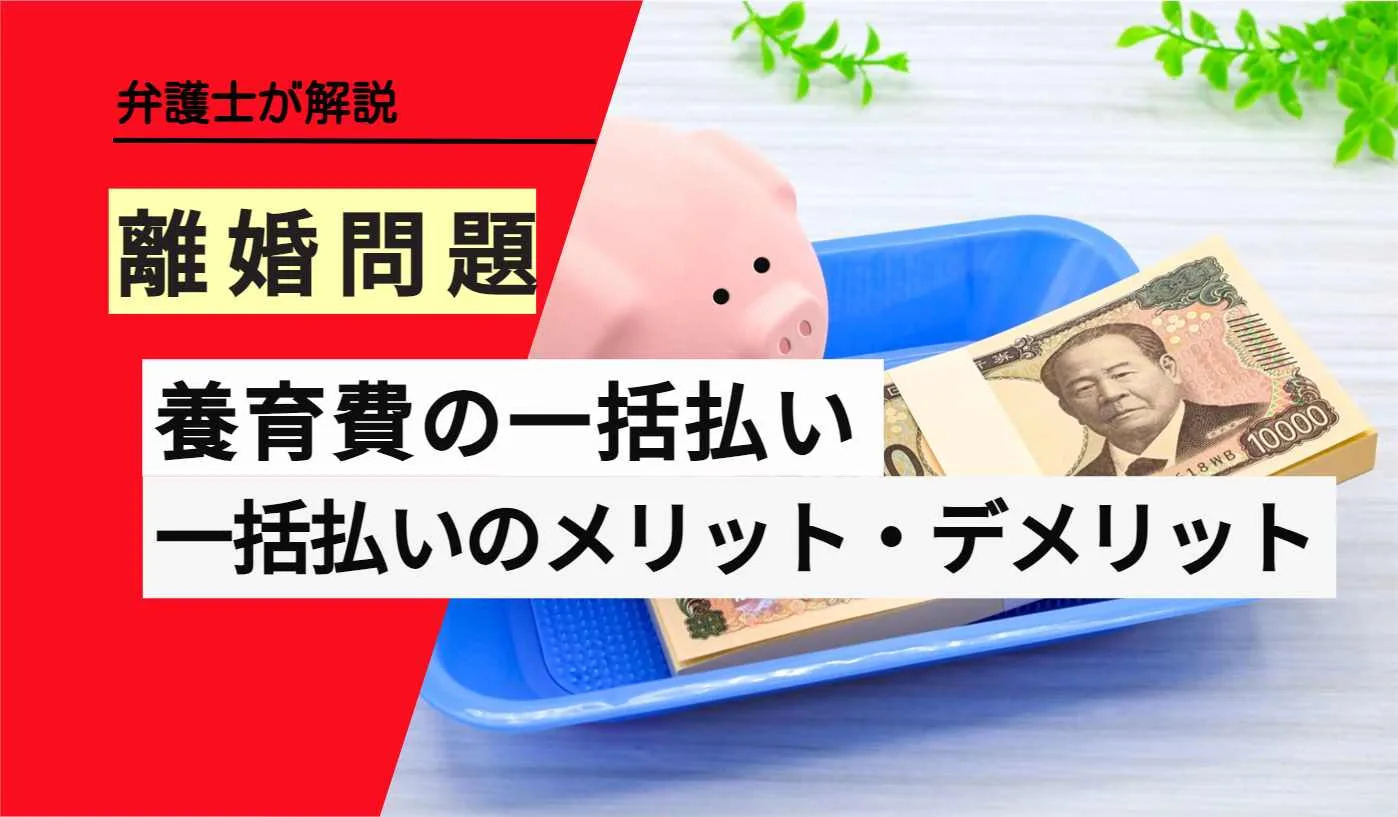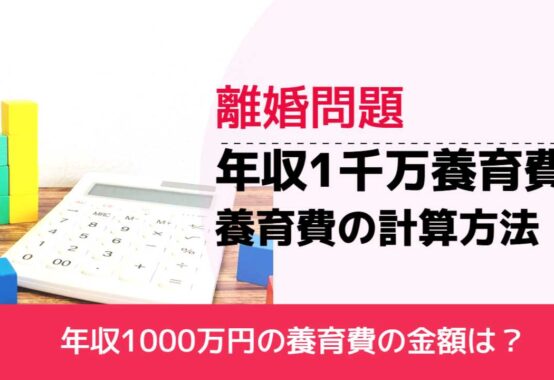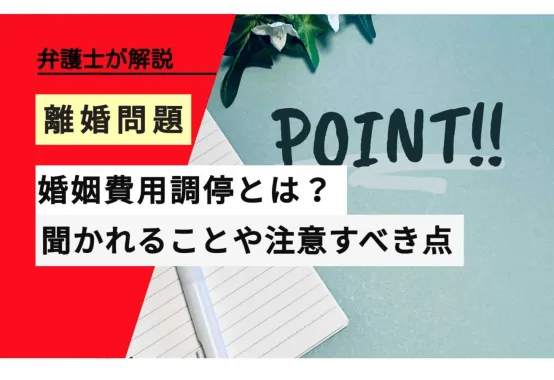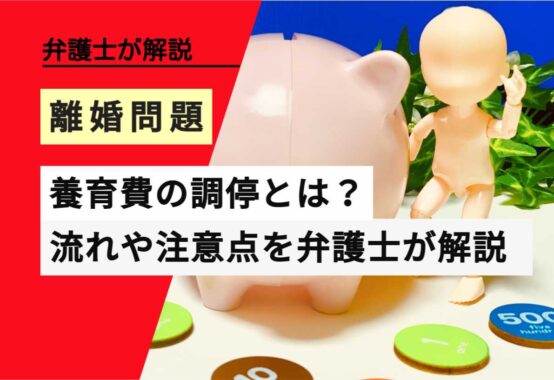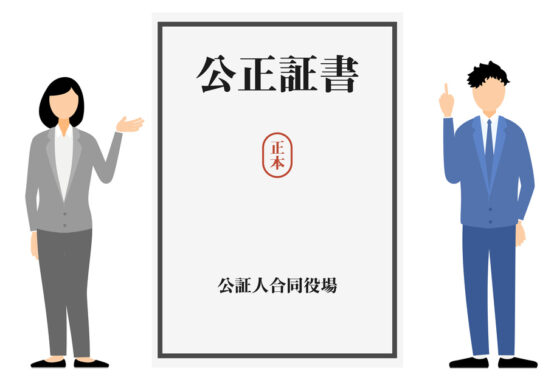離婚した夫や妻との接触を極力控えたい、不払いを防ぎたいとの思いから、養育費を一括で受け取りたいと思う人も多いかと思います。
養育費は離婚後の子供の生活を支えるために重要なものです。養育費の支払方法を一括払いとする場合にはメリットがありますが、デメリットや注意点もあります。場合によっては、贈与税が生じたり、将来の追加請求ができなくなるなどの問題も生じるため、養育費の一括払いには注意をしなければなりません。
本記事では、養育費を一括払いするメリット・デメリット、そして一括払いの注意点について分かりやすく解説します。
養育費の一括支払いを求めることはできるか
養育費の支払方法には、1ヶ月毎に支払う定期金払いと養育費の終期までの養育費をまとめて支払う一括払いがあります。
以下では、養育費の支払方法について解説します。
養育費は毎月払い(定期金払い)
養育費の支払いは基本的には毎月払いで行われます。
養育費は、子供の成長に応じて子の生活のために支払われるものです。そのため、養育費は、1ヶ月毎に支払われるのが原則です。
一括(一時)払いも可能
養育費は基本的に毎月支払う形式が一般的ですが、一括(一時)払いで支払われることもあります。
ただし、養育費の一括払いを強制することはできません。養育費の権利者と義務者との間で養育費の一括払いを認める合意が必要です。養育費の義務者側が一括払いを拒否するようであれば、養育費の一括払いを求めることはできません。

養育費の一括請求のメリット・デメリット
養育費の一括請求を考える際には、メリットとデメリットを十分に理解することが重要です。以下では、それぞれの側面について具体的に解説していきます。
一括払いのメリット
養育費の一括請求にはさまざまなメリットがあります。以下に、養育費の一括請求の具体的なメリットを詳しく解説していきます。
相手方との接触を回避できる
養育費の一括払いにより、離婚後に相手方との接触を減らすことができます。
定期払いであれば、毎月相手方からの入金を確認し、万が一、不払いであれば相手方に対して支払いを催促しなければなりません。
そこで、養育費を一括払いとすることで、毎月の養育費支払いのやり取りがなくなり、相手方と定期的にコミュニケーションを取る必要がなくなります。このように一括払いを選択することで、離婚後の生活におけるストレスや不便を減らし、精神的な負担を軽減させることができます。
不払いによるリスクを回避できる
一括払いにより不払いがあった時のリスクを避けることができます。
養育費の不払いがあれば、相手方に支払いを催促します。それでも、支払いに応じない場合には、相手方の預貯金や給与を差し押さえて、強制的に未払分を回収しなければなりません。差押えが成功しない場合には、相手方の財産や勤務先を調査しなければなりません。それでも、未払い養育費の回収が成功しなければ、未払いの状態が続き、経済的に不安定な状態となります。
しかし、養育費の一括払いを受けていると、このような不払いのリスクを回避することができます。
急な出費に対応できる
養育費の一括払いにより、予期せぬ出費にも迅速に対応することができます。
離婚後に子供の病気や怪我等により特別な出費を要する場合、ご自身の資産から支出するか、相手方にその一部の負担を求めることになります。
十分な資産を有していれば問題はないかもしれませんが、仮に十分な資産がない場合には、緊急時の対応が困難となるおそれもあります。
他方で、養育費の一括払いを受けていれば、突発的な出費にも即座に対応することが可能となります。
養育費の一括払いは、離婚後の生活を安定させ、経済的な余裕を生む手段となります。


デメリット
養育費の一括払いには複数のメリットが存在しますが、デメリットも無視できません。
離婚の交渉を困難にさせる
養育費の一括請求に固執すると、離婚交渉を複雑化させる可能性があります。
養育費は定期払いが原則であり、相手方の同意がなければ一括払いを求めることはできません。
それにもかかわらず、養育費の一括払いを離婚条件として固持し続けると、離婚協議を難航させてしまうおそれがあります。
追加の請求が困難となる
養育費を一括で受け取ると、離婚後の事情の変化があっても、養育費の追加請求をすることが難しくなります。
定期払いであれば、離婚後に収入の増減等の重要な事情の変動があれば、養育費の増額を求めることができます。
しかし、一括払いを受ける場合、将来の事情の変動があった場合のリスクも踏まえて一括払いを選択している以上、事情の変更も織り込み済みといえます。
そのため、事情の変更があったとしても、養育費の追加請求をすることが通常よりも難しくなる可能性があります。ただ、一括払いを受けた時点でも予想できないほどの大きな収入の増減があったような場合には、養育費の追加請求が認められる可能性はあります。
贈与税の課税を受ける可能性がある
養育費の一括払いは贈与税の課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。
本来、養育費を月額で受け取っている場合、その養育費は贈与税の課税を受けないのが原則です。
しかし、贈与税を一括で受け取ると、生活費又は教育費に充てるために通常必要な範囲を超えるとして、贈与税が課税される可能性があります。
そこで、贈与税対策のために、一括払いされる養育費を信託財産とする信託契約を結び、毎月定額の金銭を受け取るようにし、一方的に解約できないようにする方法が考えられます。
再婚による返金が必要になる可能性
受け取る側が再婚する場合、養育費の一括払いの一部を返金しなければならない可能性があります。
養育費の権利者側が離婚後に再婚し子供と養子縁組した場合、養育費の義務者は子供の養育費の義務から解放されます。
そうすると、養育費の一括払いを受けている場合には、養子縁組後の期間の養育費は、本来支払う必要がない養育費ということになります。そのため、養育費の権利者側が再婚したことで、一括受取している養育費の一部の返金を求められる可能性はあります。
そこで、養育費の合意に際して、再婚や養子縁組をした場合でも、返金を求めないとの条項を定めておくことが重要となります。
養育費を一括請求する際の計算方法
養育費を一括請求する場合、その計算方法にはいくつかあります。
月額の養育費の合計額とする
養育費の1ヶ月あたりの金額に養育費の終期までの期間をかけた金額の合計額を一括払いの支払額とする方法です。
計算方法として、単純で分かりやすいものといえます。
例えば、月額5万円の養育費を現在5歳の子供が20歳になるまで支払う場合を考えてみましょう。この場合、以下の計算により一括払いの養育費は900万円となります。
5万円×12ヶ月×15年=900万円
養育費の合計額から中間利息を控除する
養育費の一括請求を行う際には、合計額から中間利息を控除する計算方法があります。
養育費の一括払いを受け取る場合、その受け取る養育費には、数年後、数十年後の将来の養育費も含まれています。
本来、将来の支払時期に受け取るはずの養育費を先行して受け取った上で、定期預金等に預けるなどして、その将来の支払期限まで将来分の養育費を運用することが可能となります。
そこで、養育費の合計額から将来の利息分(中間利息)を控除して現在の価値に割り戻すことが必要となります。具体的には、民法上の法定利率が年3%とされていますので、この年利3%の利息を基に、中間利息(ライプニッツ係数)を養育費の月額に掛けることになります。
中間利息の控除は、養育費を支払う義務者側の納得も得やすい公平な計算方法といえます。
例えば、月額3万円の養育費を5年間で支払う場合、中間利息(ライプニッツ係数)である4.5797に1年分の養育費を掛けます。この場合、養育費の一括払額は、1,648,692円となります。
3万円×12月×4.5797=1,648,692円
一括払後の養育費の追加請求の可否
養育費の一括払い後でも、特別な事情がある場合には追加請求が認められることがあります。
上記のとおり、養育費の合意の当時、予期していない特別の事情が発生すれば、養育費の増額請求をすることが認められています。
養育費の一括払いをした時でも、予想していない重大な事情変更が生じ、一括で受け取った養育費の額が子の生活の実情に適さなくなった場合には養育費の追加請求は認められます。
ただ、養育費の一括受取を選択した際、支払いの終期までに、一定程度の収入の増減があることは当然に予見できたといえます。
また、養育費の義務者としても、養育費の一括払いにより、養育費の追加請求を受けないと期待するのが通常です。
そのため、養育費の追加請求は、通常の養育費の場合よりも厳格に判断されることになります。
そこで、追加請求が認められるためには、合意当時、養育費の支払終期までに生じることが予想できないような事情の変更が生じることが必要です。
例えば、予想もしないような大幅な収入の増減や営んでいた事業の倒産、病気により高額な医療費が発生する場合などが挙げられます。
他方で、遊興費に支出したために養育費がなくなった場合や無計画に私立学校に進学させて養育費が不足した場合には、追加請求は認められにくいといえるでしょう。
| 【東京高裁平成10年4月6日】調停離婚にあたり子どもが成人になるまでの養育費を一括で支払うこと、将来相互に金銭上の請求をしない旨を約束したところ、その後に、子供の私立高校と大学費用の支払いを求めた事案です。親権者は、受領した養育費を計画的に使用して子の養育に当たる義務があるものと解すべきである。しかし、高等教育を受ける前から私立学校と学習塾に通学させれば、高等教育を受けるまでに養育費を使い切ることを容易に予測できたにもかかわらず、子供を小学校から私立学校と学習塾に通わせたことで、養育費を使い切ったことが認められるため、養育費の追加請求を認めませんでした。 |
養育費の一括払いを受けるための注意点
一括払いの合意を得るための注意点・ポイントを解説します。
養育費の一括払いの合意をしてもらうためにはいくつかの戦略が必要です。
養育費の条件を譲歩する
養育費の一括払いを求める際に、その交渉を円滑に進めるためには、養育費の条件の歩み寄りに応じる姿勢を持つことが重要です。
本来、養育費は月額払いが原則です。そのため、一括払いの支払いは、義務者からすれば養育費の条件の譲歩となります。
そのため、当事者間の公平の観点から、養育費の一括払いを求める権利者側においても、養育費の条件を譲歩しなければ、義務者から合意を得ることが難しくなります。例えば、養育費の1ヶ月あたりの金額を減額したり、養育費の終期を短くしたりすることが考えられます。
面会交流を積極的に行う
子どもの面会交流に協力的な姿勢を示すことは、養育費の一括支払いに合意してもらうための重要な要素です。
養育費の義務者側は、子どもと定期的に会うことを希望することが多いため、義務者側に対して面会交流に協力的な姿勢を見せることで、養育費の支払いに前向きになってくれることが多くあります。例えば、面会交流を拒否することなく、面会交流の大切さを理解した上で、できる限り相手方の求める面会交流を受けるように努めます。
仮に、面会交流の条件を拒否する場合でも、その理由を丁寧に説明し、相手方の理解を得られるようにします。
養育費の一括払いを受けるための流れ
養育費を一括払いで受け取るための流れを説明します。まずは、話し合いから始め、話し合いが難航すれば、調停手続に移行して進めていきます。
話合いをする
相手方と養育費の金額や支払方法について協議をします。
離婚前であれば、養育費だけでなく、養育費の前提となる子の親権、慰謝料、財産分与などの離婚条件と一緒に協議することが一般的です。
合意書を作成する
相手方との協議の結果、合意に至れば必ず合意書を作成します。できれば、単なる合意書ではなく公正証書にしておくことが大切です。強制執行認諾文言付公正証書であれば、相手方が合意内容を守らなかったとしても、訴訟や調停を経ずに強制執行をすぐにできます。
調停申立をする
相手方との話し合いが奏功しない場合には、調停の申し立てをします。
離婚前であれば離婚調停の申し立て、離婚後であれば養育費の調停の申し立てをします。調停手続では、家庭裁判所の調停委員が当事者を仲裁して話し合いによる解決を目指します。
訴訟手続
離婚調停が不成立となれば、離婚訴訟を提起することになります。
訴訟手続では、当事者双方が主張と立証を繰り返し行い審理を行います。裁判官から和解の提案を受けて和解により解決となることも多くあります。ただ、和解協議の甲斐なく和解が成立しなければ判決手続となります。
審判手続
離婚後の養育費の調停手続が不調になれば、自動的に審判手続に移行します。
審判手続も訴訟手続のように当事者の主張反論を通じて審理を行います。審理が尽くされると、裁判官から審判が下され終局的な判断が示されます。
養育費の問題は弁護士に相談を

養育費は、子供の健全な成長のために必要な費用です。元配偶者との接触を避けるために養育費の請求を控えているケースも多くあります。
子供の教育費に充てる十分な収入と財産があれば別ですが、そうでないにもかかわらず、養育費を請求しないことは、子供の養育環境を劣悪にします。
弁護士に相談・依頼することで、相手方との交渉や調停手続きを任せることができ、心理的な負担を軽減できます。また、養育費の金額やその他の条件について、あなたにとって有利となる選択肢を提供してもらえることができます。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。