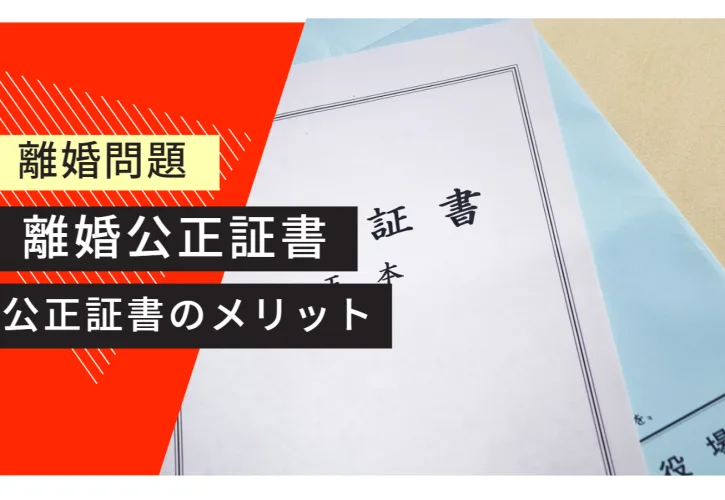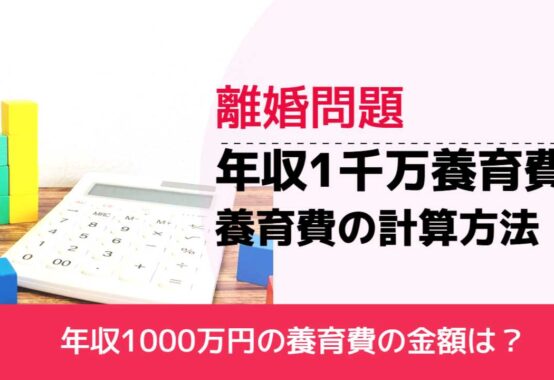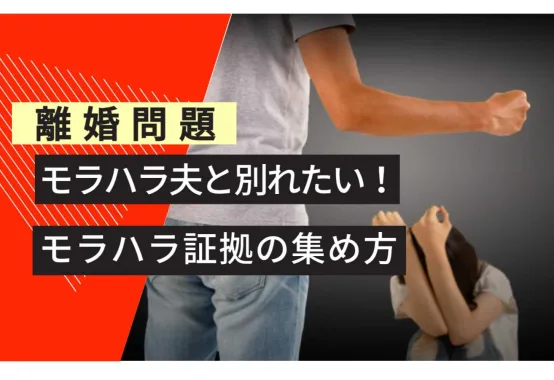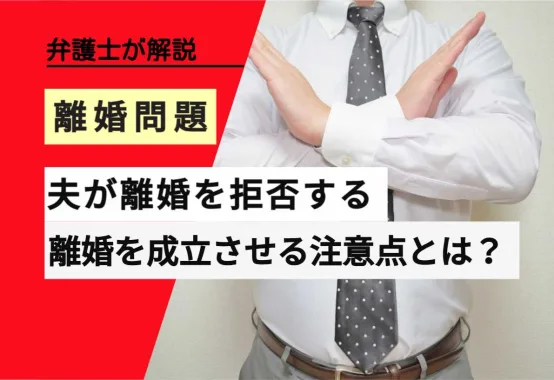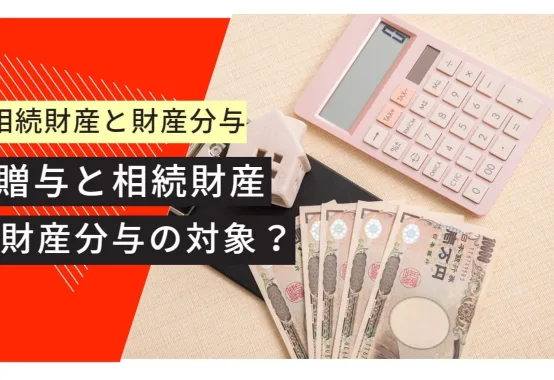協議離婚に際して、作成される離婚公正証書。
しかし、公正証書は常に作成されるわけではありません。相手方が公正証書の作成に協力してくれないこともあります。
公正証書をわざわざ作成するメリットは、裁判をせずに強制執行できること、公証人の面前で意思確認をするため争いを予防できることです。
公正証書を作成するのであれば、漏れのないように必要な事項を文書に盛り込むことで、離婚トラブルを蒸し返しのないように解決することが重要です。
公正証書を作成するとして、どのような内容の公正証書を作成するべきなのかを解説します。
離婚公正証書とは何か?
何となく聞いたことのあるワード、「公正証書」。
公正証書とは、全国各地に設置されている公証役場に在籍する公証人が作成する公文書を言います。公正証書は、様々な合意書の作成のために用いられます。
離婚合意書だけでなく、遺言、売買契約書や賃貸借契約書などの目的のために作成されます。公正証書を作成したことがある人は非常に珍しいと思います。
離婚公正証書は離婚時に作成する公文書
離婚公正証書とは、協議離婚の成立する際に、合意した離婚条件を記載する公正証書のことをいいます。
協議離婚とは、夫婦間が話し合いをした上で、双方の合意の下で離婚届を提出して離婚を成立させる場合をいいます。これに対して、裁判所の調停手続により離婚する場合を調停離婚、訴訟手続を通じて離婚する場合を裁判離婚と呼びます。
日本では、離婚全体のうち協議離婚が8割を占めており、ほとんどのケースが協議離婚により離婚していることが分かります。


離婚公正証書を作成するメリットとデメリット
離婚公正証書を作成することには、多くの利点もありますが、それだけではありません。いくつかのデメリットもあります。メリットとデメリットを比較し、それぞれの事案に応じて離婚公正証書を作成するべきかを検討するべきでしょう。
離婚公正証書のメリット
離婚時に公正証書を作成しておくメリットは多くあります。離婚後のトラブルを防ぐためにも、合意した内容を公正証書にしておくことは非常に有用です。
公正証書作成する5つのメリット
- 離婚条件の誤認を防ぐ
- 離婚の条件の証拠となる
- 強制執行できる
- 調停や裁判を回避できる
- 原本を公証役場で保管してもらえる
離婚条件の誤認を防ぐ
離婚する際、『離婚すること』だけでなく、これに関連する事項、例えば、子供の親権やその養育費の金額・終期、財産分与の金額、年金分割、慰謝料といった離婚条件を決めることが多いです。
これを当事者間の口約束だけで合意し、何らの書面も残さずにいると、事後的に言った言わないの水掛論になったり、双方で認識のズレが生じてしまうことがあります。
そこで、離婚条件に関する誤認を防ぎ、将来の紛争を予防するため、離婚条件を具体的に記載した合意書を作成しておくことが必要となります。
離婚条件の証拠となる
離婚条件を当事者間の口頭で確認するだけでも、合意としては有効です。
しかし、離婚成立後に離婚条件に関する争いが生じてしまった場合に、合意した離婚条件を証明できる手段がなければ、相手が認めない限り、主張する離婚条件が裁判所において認定されることはありません。
そこで、万一、将来、離婚条件に関する争いが生じた場合に備えて、離婚条件を明確に記載した合意書を作成しておくことが必要となります。
さらに、公正証書として作成しておくことで、第三者である公証人が作成プロセスに関与しているため、単なる合意書よりも高い信用性が認められます。
強制執行をできる
本来であれば、調停や訴訟手続きを経なければ強制執行することはできません。
しかし、公正証書としておくことで、相手方が約束を守らない時に速やかに強制執行することができます。詳細は後述します。ただし、強制執行できるのは、お金の支払を求める金銭債権の不履行に限られます。
離婚調停や離婚訴訟を回避できる
離婚調停や離婚訴訟は時間と費用を多く費やします。
離婚調停は、家庭裁判所において、離婚条件について当事者間で話し合いをします。離婚訴訟では、家庭裁判所の裁判官が離婚条件を含めた離婚問題を審理します。そのため、1年以上の時間を要することが一般的です。また、弁護士費用も多く発生しがちです。
他方で、公正証書は、調停調書や判決書といった裁判所の書類と同じ効力を有しますが、離婚調停や離婚訴訟のように多くの時間と費用を要することはあまりありません。
公正証書で原本が保管される
公正証書を作成すると、公正証書の原本が公証役場にて保管されます。公正証書の原本の保管期間は、原則として作成年度の翌年から20年とされています。
公正証書を作成すると、その謄本と正本が交付されます。たとえ、これらの謄本を紛失してしまったとしても、先ほどの保管期間以内であれば、謄本の再発行を依頼することができます。
離婚公正証書のデメリット
合意書を公正証書とする場合、公証役場に公証人手数料を支払う必要があります。合意の内容によってマチマチですが、5万円から10万円の範囲内で計算されることが多いと思います。
また、公証人のスケジュールによっては、公正証書の作成までに数週間の期間を要することがあります。
| 財産分与・養育費・慰謝料額の合計 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |


離婚公正証書に書くべき内容
離婚公正証書は、夫婦間の争いを終局的に解決し、紛争の蒸し返しを防止するために作成するものです。そのため、離婚公正証書を作成する際には、できる限り抜け漏れの無いように必要な事項を盛り込むようにします。
以下で紹介する文案はあくまでも一例ですので、個別の事案に対応するものではありませんのでご留意ください。
表題
公正証書の表題は、離婚公正証書、合意書、離婚合意書などです。公正証書を作成する場合、公証人が表題を付けることが多いでしょう。
離婚
合意後、離婚届を提出することを確認します。公正証書の作成によって当然に離婚が成立するわけではありませんので注意です。公正証書の作成日からいつまでに離婚届を提出する必要があるのかを明記することもあります。
離婚の合意
夫〇〇(以下『甲』という。)と妻〇〇(以下『乙』という。)は、合意の上、協議離婚をする。
親権
夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚時に、子供の親権者を誰にするのかを決めなければなりません。
親権者
甲乙間の子の長女○○(生年月日:〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という)の親権者を乙と定め、乙において子を養育監護する。
養育費
親権者とならない親は、親権者となる親に対して養育費を支払う義務を負います。
養育費の金額は、夫と妻の収入に応じて計算されます。簡易的な数値であれば、裁判所が公開する養育費算定表によって算出することができます。
養育費
甲は乙に対して、丙が20歳に達する日の属する月まで、令和○年○月○日から、毎月月末までに、養育費として月○○円を、乙指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
関連記事|養育費は公正証書にして不払いを防ごう!養育費の基本と公正証書のメリットを解説
財産分与
離婚時に夫婦間で財産分与がなされる場合には、その内容や支払方法を定めておきます。
住宅ローン付の自宅不動産に、住宅ローンを負わない妻や子供が居住し続ける場合には、①居住期間、②家賃の支払いの有無、③住宅ローンの債務引き受け、④自宅不動産の所有権の移転などの具体的な条件を決めておきましょう。
財産分与
甲は乙に対し、財産分与として、令和〇年○月○日までに金○○○円を乙指定の銀行口座に送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする
住宅ローン付自宅不動産を譲渡するパターン
1.甲は、離婚に伴う財産分与として、本件自宅不動産の所有権を譲渡する。
2.甲は、本件自宅不動産にかかる住宅ローン債務を完済したときに、本件不動産について、前記財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続に関する費用は、乙の負担とする。
関連記事|財産分与の対象にならないものとは?
関連記事|財産分与の時効は2年?財産分与の期限と請求の流れを弁護士が解説
関連記事|債務超過している場合の預金の財産分与は?
慰謝料
相手方の不貞行為(不倫・浮気)やDVが理由となり離婚する場合、離婚慰謝料あるいは解決金の支払いを合意することがあります。
相手方が、慰謝料を一括払いできないために分割払いとする場合には、分割払いの回数や怠った場合の処理を明記しておきましょう。
慰謝料請求(一括払いパターン)
甲は乙に対し、慰謝料として、令和〇年○月○日までに金○○○円を乙指定の銀行口座に送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする
慰謝料請求(分割パターン)
1 乙は甲に対し、本件解決金として金〇〇万円の支払義務があることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金員を下記のとおり分割して甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
記
令和〇年〇月から令和〇年〇月まで毎月末日まで 〇万円
3 乙は、前項の金員の支払を怠りその金額が〇万円に達した場合、当然に期限の利益を喪失し、乙は甲に対して、前項の金額から既払額を控除した金員及びこれに期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで年〇%の割合による遅延損害金を付して直ちに支払う。
関連記事|不貞行為とは何か?どこからが不貞行為かを弁護士が解説します
関連記事|モラハラで慰謝料を請求できるのか?モラハラの意味や慰謝料の条件
関連記事|DVの慰謝料請求の相場は?DVの慰謝料請求について弁護士が解説
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に厚生年金や共済年金の納付記録を離婚時に分割する制度をいいます。年金分割の分割割合が合意できている場合には、その内容を盛り込んだ公正証書を作成しておくことがポイントです。
仮に公正証書を作成しなければ、「年金分割すること及び按分割合について合意している旨を記入し、自らが署名した書類」を作成し、夫婦が揃って年金事務所に提出しなければなりません。公正証書(又は公証人の認証がある合意書)があれば、夫婦揃って年金事務所に赴く手間が省けます。
公正証書に年金分割の条項を盛り込む場合には、年金事務所で発行された「情報通知書」を提出する必要がありますので、予め年金事務所に情報提供請求をしておきましょう。
年金分割
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)とは、本日、厚生労働大臣に対し、当事者間の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求を行い、厚生年金保険法第78条の2第1項の請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。
TIPS!
離婚した日の翌日から2年以内に年金事務所に年金分割請求をする必要があります。そのため、公正証書が完成した後、安心してそのまま放置していると年金分割ができなくなります。年金分割は、公正証書等を作成した後、①公正証書、②マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書、③戸籍謄本年金事務所に提出しなければいけません。
関連記事|熟年離婚をした場合の年金分割の基礎知識
住所や勤務先の変更と通知義務
当事者の住所や勤務先が変更された場合、相手方からの情報提供を受けなければこれらを知ることはできません。特に、相手方の勤務先の情報は、相手方の給与の差押えをする場合には、必要となる情報となります。弁護士を通じて、住民票の職務上請求や第三者からの情報取得手続きを利用すれば、これらの情報を収集することはできますが、時間と費用を要します。
そこで、住所や勤務先等の変更があれば、遅滞なく連絡する旨の条項を設けておきましょう。
住所変更等の通知
甲及び乙は、住所、居所及び勤務先が変更になった場合は、遅滞なく他方の当事者に通知しなければならない。
清算条項
離婚成立後に夫婦間での争いを未然に防止するため、合意書で定められた約束以外に、お互い名目のいかんを問わず金銭の請求をしないことを合意します。
清算条項を設けることで、合意後に『実はこんな請求もあるので、支払え』という事態を予防できます。
清算条項
甲及び乙は、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務関係の存しないことを相互に確認し、名目の如何を問わず相互に金銭その他の請求をしないことを約束する。
強制執行認諾文言
公正証書の最大のメリットでもある、強制執行を認める文章です。
公正証書に強制執行を認める条項を設けることで、相手方が不払いに陥っても、わざわざ訴訟手続をすることなく、差押手続を行うことができます。
なお、公正証書による強制執行は、お金の支払いを求める金銭債権のみが対象となります。
不動産の明渡し等の金銭債権以外の債権については、対象外となります。
強制執行認諾文言
甲は、本合意書において定めた金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。
離婚公正証書に書けないこと
公正証書は公文書である以上、盛り込む内容には制約があります。法律上無効である内容や公序良俗に反する内容を書くことはできません。
公正証書に書けない内容は以下の事項があります。
- 養育費の支払いを拒否する
- 面会交流を拒否する 親権者変更を禁止する
- 利息制限法を超える金利の記載すること
- 慰謝料や財産分与の支払いを長期間の分割とすること
離婚公正証書の作成までのスケジュール
離婚の公正証書を作成するには、以下の作成手続きを経る必要があります。

離婚協議を行う
まずは、夫婦間で離婚条件を含めた離婚協議をします。あくまでも公証役場では、夫婦間で合意した離婚条件を公正証書として作成する場所です。公証人が夫婦の間に仲裁して離婚条件を調整することはありませんので、注意が必要です。
子供の親権や養育費
親権者(監護者)、養育費等の月額金額、終期、進学や疾病時の諸費用の負担
財産分与
財産分与の金額や支払時期、自宅不動産の権利関係や離婚後の居住関係(住宅ローン)、年金分割
慰謝料関係
慰謝料や解決金の金額、支払い方法(一括か分割か)、支払時期、支払いを行った場合の処理方法
面会交流(面接交渉)
回数、日にち、場所、方法、宿泊の有無
婚姻費用
離婚する前に別居をしている場合、別居から離婚するまでの生活費(婚姻費用)について協議します。
婚姻費用とは、別居してから離婚するまで、収入の多い配偶者が少ない方に支払う、社会生活上必要となる生活費を言います。婚姻費用の請求があった場合には、離婚するまでに夫(妻)が支払うべき婚姻費用の金額を協議しておく必要があります。
関連記事|別居中の生活費とは?別居後の婚姻費用を弁護士が解説します
原案の作成
離婚条件の調整ができれば、公正証書とする合意書の原案作成をします。
夫婦の一方で文案の叩き台を作成して、これをもう一方で確認し、内容の調整をしていきます。当事者間の文案の調整回数を減らすために、文案の作成を弁護士に依頼することもあります。
また、公証人に文案の概要を伝えて、文案の作成をしてもらうこともあります。
公正証書作成の予約
公正証書を作成する公証役場に電話をして、作成の申し込みをします。
まずは、作成を申し込む公証役場を選定した上で、公証役場に電話をします。公証役場によって予約方法は区々ですが、電話やメールを通じて作成日の予約をします。申込者だけでなく相手方またはその代理人の予定も調整しなければならないため注意しましょう。
必要書類の準備と提出
離婚公正証書の場合、戸籍謄本の提出が必要となります。
本人確認のために印鑑登録証明の提出を求められますので、印鑑登録証明書と実印を用意します。作成日の1週間程前までに、作成した文案と一緒にこれら必要書類をファックス、メール等の方法で公証役場に提出します。
また、公正証書の作成を弁護士に依頼する場合には、公正証書の文案を添付した委任状を提出する必要があります。
作成日当日
予約した時間に公証役場に出向きます。
実印、印鑑証明、運転免許証等の身分証明書を持参します。所定の時間になれば、公証人から公正証書の内容確認と必要書類の確認をされます。
双方、異論がなければ、公証人が合意書の内容を読み上げます。読み上げが終わると、夫婦双方で署名捺印をします。作成が終わると、作成費用の支払をします。
あらかじめ夫婦のうち誰が負担するのか、分担するのであれば、その負担割合を決めておきましょう。
お近くの公証役場はこちらから検索ください。
作成後の流れ
公正証書を作成する場合でも離婚届を作成して、これを役場に届出しなければなりません。本籍地のある役場であれば離婚届を提出するだけで、離婚手続を行うことができます。本籍地ではない役場であれば、離婚届の他に戸籍謄本の提出が必要となります。
関連記事|離婚後の手続きを弁護士が解説|チェックリストも紹介しています
公正証書があれば裁判をせずに強制執行できる
公正証書を作成しておくことで、面倒な裁判手続きをすることなく、養育費や財産分与の支払のための強制執行を行うことが可能となります。
本来は判決や調停調書が必要となる
相手方が合意した内容を履行しない場合、差押え等の強制執行を行い、相手方の意向に関係なく、相手方の財産から未払分の回収をすることができます。
しかし、この強制執行を行うためには、『債務名義』という書類が必要となります。
聞きなれないワードですが、債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、審判といった裁判所が作成した文書を言います。
公正証書ではない、単なる合意書は、裁判手続を経ずに作成された文書ですので、この合意書に基づいて強制執行することはできません。
そのため、強制執行をするためには、合意書の履行を求める訴訟提起あるいは調停の申立てをした上で、和解あるいは判決を得る必要があります。
しかし、訴訟提起をした上で、判決手続まで審理を進めるためには、ある程度の時間(1年前後)を要します。
関連記事|離婚調停とは?離婚調停の流れや時間、調停成立後の流れ
関連記事|離婚裁判の期間と流れ|長期化する原因や早期解決のポイント
公正証書は判決に代替する
公正証書にしておくと、訴訟手続を経ることなく、相手方の預貯金や給与を差し押さえることができ、大幅な時間と労力の節減となります。
ただ、公正証書を根拠に強制執行をするためには、公正証書に強制執行を認める文言を定めておくことが必要です。また、強制執行できるのは、金銭債権に限られています。
このように公正証書を作成しておくことは、訴訟手続を経ずに強制執行に着手でき、時間的にも費用的にも節約できるというメリットがあります。
離婚公正証書の作成は弁護士に相談しよう

離婚公正証書の作成は、早期に離婚手続を終結できる点で有益といえます。
しかし、早期の解決を重視するあまり、養育費や慰謝料等をかなり高額な金額で合意してしまうケースもあります。
一度合意をしてしまうと、これを覆すことはかなり難しいです。
公正証書の作成をする際には、あらかじめ弁護士に相談することを推奨します。当事務所では案文の作成に加えて、公証役場の予約から作成日までの作成サポート全般をお手伝いしています。
まずは、お気軽にお問合せください。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。