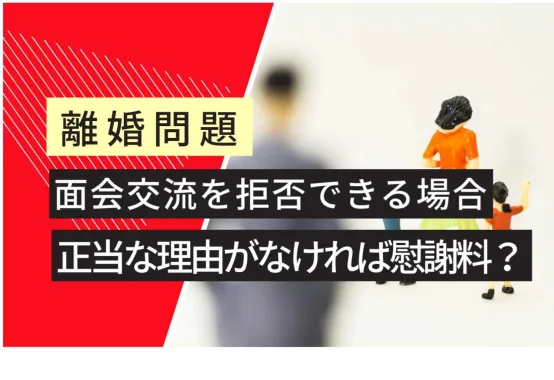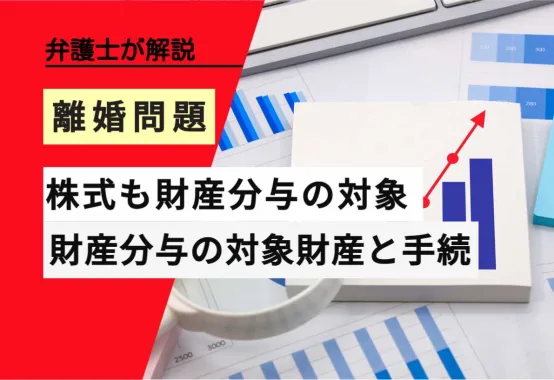モラハラを理由とした離婚や慰謝料請求の相談が年々増加しています。
モラハラ夫と離婚するために、モラハラが法定の離婚原因に該当することが必要です。その上で、モラハラ被害を受けてきたことを証拠により証明できなければなりません。多くのケースでは、モラハラ被害を証明することができず、長期間の別居を余儀なくされることもあります。
本記事では、離婚問題に注力する弁護士が、モラハラの基礎知識や離婚手続きを解説しています。
モラハラとは何か?

モラハラは、モラルハラスメントの略語です。
モラハラは、倫理や道徳といったモラル(moral)に反する精神的な嫌がらせや攻撃(harassment)のことです。
一般的に身体的な暴力行為は伴わず、侮蔑的な言動によって他者の人格や尊厳を傷つけて精神的に追い詰め、その心身に傷を負わせる精神的な暴力が該当します。
モラハラは、パワハラと異なり職場や学校の人間関係だけでなく、夫婦や親子、恋人の間でも発生しています。
パワハラとの違い
また、パワハラのように職務上の地位や権力は関係ありません。
いずれにしても、被害者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、精神疾患や退職または離婚などの原因になるため、社会問題の1つとして認識されています。
モラハラの加害者は、無意識のうちにモラハラ行為を行うため、自力でモラハラの問題を解決させることは非常に難しい傾向にあります。
モラハラ加害の内容
モラハラをする人の多くは、自分自身のモラハラに気付いていません。また、モラハラ被害を受けている配偶者も、配偶者のモラハラを知らず知らずに受け入れてしまい、モラハラ被害を受けていることの自覚を持たないことがあります。
モラハラ加害の内容は次のようなものが挙げられます。
モラハラ加害の内容
☐ すぐに大声で怒鳴り散らす
☐ 「バカ、最低の人間だ」と罵倒してくる
☐ 親族や友達をバカにする
☐ 体調に関係なく「家事をして当たり前」と言って気遣いをしない
☐ 妻や子供の買物や学費等について異常に細かい
☐ 家計簿をつけるように指示をして収支の報告をさせられる
☐ 実家の帰省に良い顔をしない、嫌味を言う
☐ 友人との付き合いを絶とうとする
☐ 仕事に出ることを妨害する
☐ 生活費を入れない
☐ 無視し続けることがある
☐ 子どもに妻の悪口を吹き込む
☐ 家事育児を軽んじる発言をする
☐ 理由もなく食事を作り直すよう言ってくる
☐ 周囲からは「良い夫」と見られる
モラハラをする人の特徴
モラハラをする人の特徴は次のようなものが挙げられます。
モラハラの特徴
☐ こだわりが強い
☐ 世間体はよい
☐ 外面が良い
☐ 嫉妬深い
☐ プライドが異常に高い
☐ 束縛が強い
☐ 間違いを責め続ける
☐ 人に厳しく自分に甘い
☐ 価値観や考えの違いを認めない
☐ 虚言癖がある
☐ 性格の二面性
モラハラは離婚したい理由の上位
厚生労働省の「平成30年(2018)人口動態統計の年間推移」によると、離婚件数は20万7000組となっていますが、平成14年の28万9836組のピークと比べて減少傾向となっています。
裁判所の統計データによると、離婚したい理由の順位は以下のとおりとなっており、精神的な虐待、つまり、モラハラが男女のいずれにおいても、上位となっていることがわかります。
| 【夫の申立ての動機】 1位 性格の不一致 2位 精神的に虐待する 3位 異性関係 |
| 【妻の申立ての動機】 1位 性格の不一致 2位 生活費を渡さない 3位 精神的に虐待する |
モラハラが離婚調停申立ての動機の上位にランキングされている理由は様々ですが、時代の流れに伴う夫婦感の大きな変化によって、かつては家庭内で解消されてきた問題が解消し切れずに、夫婦関係を破綻させる要因になっているものと思われます。
モラハラ夫と離婚するためには
モラハラ被害を受けさえすれば、常に離婚請求が認められるわけではありません。
以下で紹介する、いくつかの注意点を踏まえながら離婚手続を進めていくことが重要です。
モラハラが離婚原因にあたること
モラハラが直ちに離婚原因となるわけではありません。
モラハラが法定の離婚原因となるためには、婚姻関係を維持できない程に重大な事由に該当することが必要です。
モラハラが法定の離婚原因となる条件を解説します。
離婚原因とは何か?
モラハラを理由に離婚を申し出ても、配偶者が認めないケースは少なくありません。
そういった場合には、最終的に裁判にまで発展する可能性が高くなります。
このような状況において、離婚を求めて裁判を起こすには、離婚を求めている配偶者において、民法770条の離婚原因が存在することを主張し、これを証明しなければなりません。
民法で規定された離婚原因は次の5点です。
【離婚原因】
|
この中で、モラハラを離婚の原因とするには、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当している必要があります。
離婚原因になるモラハラとは
モラハラのうち婚姻関係を継続し難い重大な事由と言えるモラハラは離婚原因となります。
モラハラの場合、家庭内において、長い時間をかけて積み重ねられた行為が婚姻関係を破綻させるものといえるかを判断します。
つまり、家庭内であっても、配偶者の人格を否定するような暴言、侮辱、脅迫は精神的な虐待となります。そのような精神的な虐待が長期間、多数回にわたって、家庭内で繰り返されている場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。


モラハラを証拠で証明する
モラハラを離婚原因として認定してもらうためには、具体的な証拠が必要になります。
特に、モラハラは家庭内で行われることがほとんどであるため、これを事後的に裁判所内で立証することは容易ではなく、予め裁判手続を見越した証拠収集の準備が必要となるでしょう。
裁判では離婚の成立だけでなく慰謝料の請求も可能ですが、そのためにも具体的な証拠が必要です。
証拠集めの主な方法としては、以下のものが挙げられます。
| ✅モラハラ行為の録画や録音 ✅メモや日記などによる記録、モラハラに該当するメールやSMSの保存 ✅医師の診断書 |
また、これら客観的な資料のほか、証人尋問の証言や当事者尋問による供述に加えて、尋問中の応答状況も事実認定を補強するものになります。
さらに、家庭裁判所調査官による子の意向調査に関する調査報告書の内容を事実認定の証拠としてする裁判例もあります。
①録画や録音
モラハラ行為の録画や録音では、隠しカメラを設置したりICレコーダーを常に持ち歩いたりして、加害行為を客観的に記録しておくことが重要です。
録画や録音は、モラハラの声のトーン、声量、発声のスピード、行為者の表情を分かりやすく説明することができ、手紙やメールなどの証拠では伝え切れない部分も証明できる有用な証拠です。
モラハラ行為の証明においては、録画や録音が裁判官に対して、最もモラハラの内容やその程度を伝え易い客観資料と言えるでしょう。
可能な限り多くの録画や録音データを収集するように心がけましょう。
②メモや日記
メモや日記はなるべく克明に記述することで信憑性が深まります。
モラハラに該当するメールやSMSは、誤って削除してしまうケースが少なくありません。
そういったケアレスミスを想定した対策として、スクリーンショットによる撮影が推奨されています。
日記の場合、モラハラ行為を受ける都度、書き残すように心掛けてください。
日記がモラハラ行為を証明する有用な証拠となるためには、過去のモラハラ行為を振り返ってまとめて記録したものでは不十分です。
なぜなら、過去の記憶を辿って作成した日記の場合、その過去の記憶が事実に沿った正確なものとは評価されにくいからです。
そのため、モラハラ行為の都度、新鮮な記憶を基に作成されたもので、数回の記録に留まらず、継続して作成されたものであることが重要となります。
③診断書
医師の診断書も、裁判では重要な証拠の1つになります。
そのため、モラハラが原因で心身に不調が生じた場合には、必ず病院に行って医師の診察を受けておくことが大切です。
診断書の作成を依頼する際には、可能な限り、具体的な症状、これによって受ける影響(就労が可能か否か等)、症状が発生するに至った経緯を記載してもらうように申し出ましょう。
別居して婚姻費用を請求する
モラハラ夫との離婚協議が進まない場合には速やかに別居をしましょう。また、モラハラ夫によるモラハラ加害から逃れるために、離婚協議を経ずに別居することもあります。
別居後は、精神的な負担を回避するために、弁護士等の代理人を通じて離婚協議や離婚調停等のプロセスを進めていきましょう。
その際には、夫に対して婚姻費用という生活費の請求を忘れずにしておきましょう。
つまり、別居してから離婚成立までの期間は数か月に及ぶことがあります。離婚調停や離婚裁判となれば1年以上の期間を要します。別居後の生活を安定させるため、収入の多い夫に対して、生活費を請求するようにしましょう。この生活費のことを法律上「婚姻費用」といいます。
モラハラの裁判例の検討
相手方の人格を否定するような粗暴な言動、心無い言動が、長期間にわたって執拗に繰り返し行われている場合に、離婚原因が認められています。
このモラハラ行為が離婚原因となるためには、暴力などのDVに匹敵する程度のものである必要まではないとされています。
その理由としては、DVに匹敵する場合でなくても、日常生活の言動の積み重ねによって、婚姻関係の継続に必要とされる夫婦の信頼を修復できないほどに破壊することは十分にあり得るからです。
さらに、多くの事案では、モラハラ行為のみで婚姻関係の破綻を認定するのではなく、その他の事情も考慮しながら、夫婦関係が修復できない程に破綻しているかを認定しています。
例えば、以下の事情が挙げられます。
| ①別居期間やその間に関係修復のための努力 ②性生活の有無や程度 ③モラハラを受けた側の性格や属性(穏和で大人しく、面と向かって反論できない) ④行為を受ける配偶者本人以外の関係者に対する言動 |
| 東京地方裁判所平成16年4月28日判決 | |
| 発言内容 | 「離婚する。出ていけ。」「妻失格だ。」「常識がない。」「お前は狂っている。」「夫に反発するんじゃない。」「毎日遊んでいるくせに口答えするな。」「お前には母親の資格はない。」等多数 |
| 判決 | 妻の人格を無視したとも言える夫の暴言、夫が自己の言動について反省をすることがないことから、今後、婚姻関係を修復し、改善することは期待できない。別居期間も1年足らずであることなどを考えても、現時点において、婚姻生活を修復することは困難であり、婚姻関係は完全に破綻しているものと認められるから、民法770条1項5号の離婚事由があるものというべきである。 |
| 東京地方裁判所平成17年6月10日判決 | |
| 発言内容 |
妻に「バカ」「この野郎」「てめえ」「ボケッ」「コラッ」などという言葉を繰り返し連続して怒鳴るようなった。 長男に「バカ男」「バカ」などと言うようにもなった。 妻に唾を吐きかけたり、食べ物や飲み物をまき散らしたりするようになった。 |
| 判決 |
妻を侮辱する被告の面罵や罵倒、物を投げつけたり、まき散らしたり、長男や飼犬にまで暴力を振るうなどという行為に加えて、別居を開始させ離婚調停を申し立てて一定期間を経過したころには、婚姻関係は破綻したものと判断することが相当である。 |
モラハラ夫との離婚手続
モラハラを理由に離婚手続きを進める場合、まずは、話し合いをします。話合いが決裂すれば、離婚調停、離婚裁判といった手続きに移行します。
モラハラ夫との離婚協議をする
モラハラを原因として離婚したい場合には、まず配偶者に当事者間の話し合いを申し出たうえで協議離婚を目指します。
離婚調停や離婚訴訟は、後述するように裁判所を介した手続であるため、時間を要することが多く、また、諸々の費用もかかります。
そのため、まずは離婚協議を進め、負担の少ない速やかな解決を目指します。
当事者だけで話し合うことも可能ですが、当事者間の協議にストレスを感じる場合、弁護士に相談の上、弁護士を代理人とすることも検討するべきです。
多くのケースでは協議により合意が成立しますが、相手が加害行為を認めなかったり感情的になったりして、成立に至らないケースも少なくありません。
また、慰謝料、親権や養育費、財産分与といった離婚条件を理由に離婚がまとまらないこともよくあります。
離婚調停を申立てる
家事調停とは、裁判官1名と男女1名ずつの委員によって構成された調停委員会によって、家庭問題を解決するための斡旋を行う手続きのことです。
原則として裁判官は調停の場には加わらず、主に2名の調停委員が双方の意見を聞き取ったうえで解決策を提示します。
調停期日の当日は、調停室に2名の調停委員が在室し、申立人と相手方がそれぞれ入れ替わりで調停室に入室し、調停委員に対して、各当事者の言い分を話します。
調停期日では、申立人と相手方が対面しないように配慮されています。
調停委員の仲裁により、双方が納得すれば調停離婚は成立しますが、一方が調停に応じなかったり離婚や慰謝料の支払いを拒否したりすれば不成立となります。
離婚訴訟(離婚裁判)
離婚訴訟は、原則として当事者が裁判所に出廷して行われます。
ただ、弁護士に対して委任している場合には、証人尋問を実施する場合は除き、訴訟当事者が裁判所に出廷することはありません。
離婚訴訟では、短くても1年程の時間を要します。
証人尋問を実施したり、手続が控訴審まで移行しているような場合には、さらに時間を要してしまいます。
そのため、訴訟手続の長期化により、精神的に過大な負担が生じることがよくあります。
訴訟手続では、双方が述べた言い分や提示した証拠を裁判官が精査して、認定した事実を基礎に判決を出します。
しかし、先程述べた長期化による不都合を避けるために、裁判官は和解協議を提案することが多くあります。
モラハラを理由に離婚したい場合には弁護士に相談を

モラハラ行為を理由として離婚請求には、上述したとおり、事前の証拠収集が非常に重要となります。
しかし、モラハラを行う配偶者と同居している期間、弁護士や専門家に相談する機会もないかもしれません。
ただ、配偶者の言動や対応に異常さを感じ始めたのであれば、第三者に対してまずは相談してみましょう。
そのうえで、専門的な判断や対応を必要とするのであれば、ぜひ当事務所にご相談下さい。
当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。
対応地域は、大阪市、東大阪その他大阪府全域、和歌山県、奈良県、その他関西圏全域となっています。
お気軽にご相談下さい。