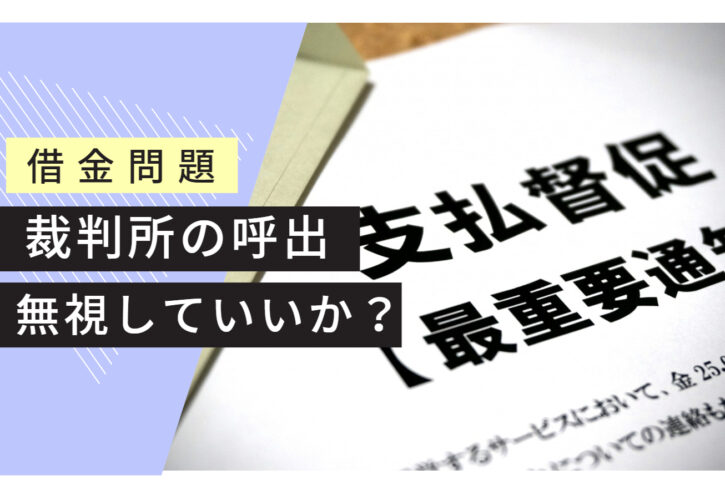クレジットカードのリボ払いやキャッシング、消費者金融などを、ついつい無計画に利用してしまう方も多いかと思います。
収入の範囲を超えた借入を続け、これを放置してしまうと、いつの間にか借金が手に負えない程に膨らんでしまい、最終的に取り返しのつかないことになる場合もあります。
まずは、自転車操業とならないよう、借入を放置することなく適切な対応をすることが重要です。
金融機関の請求を放置してしまうと、消滅時効の主張や過払い金の請求をする機会を失います。また、安易に金融業者の請求を認めたり、支払の猶予を求めてしまうと不利な立場になるかもしれません。
本記事では、裁判所からの呼出を無視した場合のリスクを、借金問題を得意とする弁護士が解説します。
借金問題を放置したときのリスク
借金問題を放置することによって生じる不利益は、以下のようなものがあります。
- 遅延損害金の発生
- 債権者からの督促通知とブラックリストへの登録
- 支払督促や訴訟提起がなされ、消滅時効や過払い請求ができなくなる
以下では、借金を放置していると生じる不利益を具体的に解説していきます。

1:遅延損害金が発生する

借金を放置すると遅延損害金を発生させます。
遅延損害金とは何なのかを解説していきます。
利息との違い
まず、遅延損害金と似た概念として約定利息があります。
借金をする場合、通常約束された利息を支払う契約となっています。
金融機関との間で利息の割合は約定されています。
約定がなければ利息は発生しませんが、通常金融機関からの借入の場合には、約定利息が生じることは契約内容となっています。
ただ、利息制限法という法律によって、約定利息の割合には一定の制限が設けられています。
具体的には、10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%とされており、これを超える利息は無効となります。
遅延損害金とは
これに対して、遅延損害金とは約束された返済日に借金を返済しない場合に生じるものです。
遅延損害金の割合は、金融機関との約定がなければ、年3%の割合となります。
しかし、通常金融機関との取引であれば、遅延損害金の割合が契約内容とされています。
一般的には20%で設定されていることが多く、通常の約定利息よりも高いことから、債務者にとっては大きなペナルティとなります。
また、クレジットカードは滞納から2~3日程度で利用停止され、その後は新規の借り入れもできなくなります。


2:金融機関からの催促とブラックリストの登録
借金の滞納を放置していると、金融機関からの支払いの催促を受けるだけでなく、いわゆるブラックリストに登録されるおそれがあります。
金融機関からの催促
返済期日から数日が過ぎても、返済せずに滞納が続いていると、借入先の金融機関から電話やメールなどで催促の通知が届くようになります。
通知を無視し、なお、滞納を続ければ、職場にも電話による催促が行われたり、金融機関の担当者が自宅に直接訪問してくる場合もあります。
金融機関からの督促により、ご自身が消費者金融などから借入をしていることやこれを滞納している事実を職場の同僚や家族に知られてしまう可能性があります。
また、滞納を続けることで、期限の利益が喪失し、借金の一括請求を受ける場合もあります。
さらに、連日の督促により精神的にダメージを受けることもあります。
金融機関からの連絡を受ければ、無視せずに催促の内容を早急に確認するようにしましょう。手に負えない状況になれば、弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすることで、金融機関は本人に対する督促をすることができなくなります。
金融機関からの督促状・催告状
金融機関からの催促を放置していると、次の段階に移ります。
催促の通知にも応じない債務者には、金融機関から督促状が送られます。
通常、督促状は一度きりではなく、数回にわたって送付されることが多いですが、それでも滞納を続ける債務者には最後通告としての催告書が送られます。
これと並行して、債務者やその就業先に対する支払いを求める電話を継続されることがほとんどです。
催告書の送付を受けてもなお、これに応じない場合には、金融機関は支払督促や訴訟提起といった借金を回収する法的手段に移行させることになります。
信用情報へ事故情報の登録がなされる
借金の支払いを放置し、金融機関からの催促も無視し続けると、信用情報に事故情報として登録されてしまいます。
ブラックリストとは?
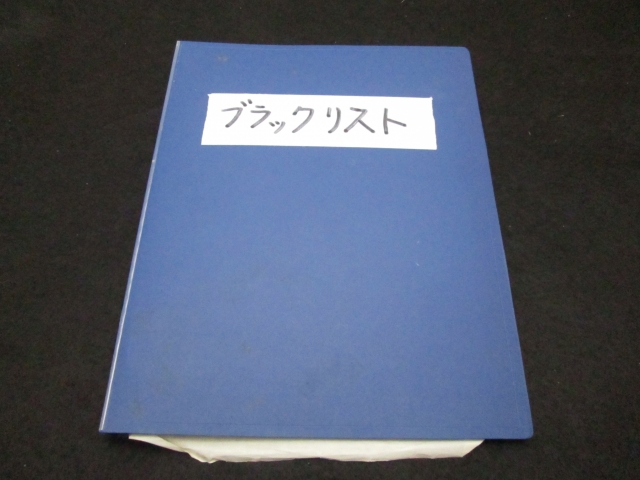
滞納から2~3カ月を過ぎた段階で、信用情報機関における事故情報として、滞納者の名前が記載されます。
皆さんも、ブラックリストという単語を聞いたことがあると思います。
しかし、ブラックリストとはあくまでも通称であって、そのようなリストがあるわけではありません。
信用情報のうち、長期間の延滞、債務整理をした事実、代位弁済といった事故情報が登録された部分をいわゆるブラックリストと呼んでいます。
信用情報とは
信用情報機関には、JICC、CIC、全国銀行協会があり、各金融機関等の属性に応じてそれぞれの信用情報機関に加盟します。
例えば、JICCであれば、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社、信販会社、金融機関、全国銀行協会であれば、三菱UFJ銀行、三井住友銀行などの大手銀行に加え、ネット銀行が加入しています。
金融機関等は、ローンやクレジットの利用といった信用取引に関する取引事実を示す情報をいいます。
各機関の信用情報は、それぞれ共有されます。例えば、JICCに登録された情報をCICでも確認することができます。
そのため、金融機関は、信用情報機関の信用情報を通じて、個人の延滞情報等を確認することができるため、事故情報(ブラックリスト)の登録がなされると滞納先の金融機関以外からも新規の借入が困難となります。
3:裁判所から訴状が届く
金融機関からの督促を無視し続けると、支払督促、少額訴訟や通常訴訟の提起という債権回収のプロセスに移ることがあります。
| ① 支払督促 ② 少額訴訟 ③ 通常訴訟 |
①支払督促とは
督促状や催告書にも応じなければ、今度は金融機関ではなく裁判所から借金返済を求める通知が届きます。
借金の返済を法的に求める方法には、訴訟提起をすることが一般的ですが、訴訟手続はその審理が長期に及ぶことがよくあります。
そこで、借金の早期回収のために、金融機関は支払督促を選択することが多いです。
支払督促の手続
支払督促の手続は、金融機関などの債権者が簡易裁判所に対して支払督促の申立てを行います。
これを受けた簡易裁判所の裁判所書記官が、申立人が提出した書類を審査し、理由があると判断できれば、借金をしている人などの債務者に対して、金銭の支払いを命じるものです。
支払督促の場合、相手方からの反論や証人尋問等の審理を経ずに、申立人から提出された書類のみを根拠に判断されることから、非常に簡易で迅速な手続と言えますが、他方で、債務者側には反論の機会は与えられませんので、これを放置することは非常に不利な結果を招きます。
異議申立て
支払督促が届いたら、債務者は異議申し立てを起こすか、督促にしたがって借金を返済するか二者択一を迫られます。
この異議申立ては、支払督促が発せられた時と、支払督促に仮執行宣言が付された時にそれぞれ行う機会があります。つまり、異議申立ては二段構えになっています。
まず、最初の異議申立て(督促異議)は、支払督促を受け取ってから2週間以内にしなければなりません。
支払督促を放置して2週間の期限を徒過してしまうと、支払督促に仮執行宣言が付されてしまいます(仮執行宣言付支払督促)。ただ、2週間目の翌日から30日以内に、債権者が仮執行宣言の申し立てをしない場合には、支払督促の効力は失います。
仮執行宣言が付されてから、2週間以内に異議申立てをすると、通常訴訟に移行しますが、これも放置してしまうと、支払督促は、確定判決と同じ効力を持つことになりますから、仮執行宣言に基づき強制執行を受けることになります。
②少額訴訟を提起される
金融機関からの督促を放置することで、金融機関から少額訴訟を提起されるケースもあります。
少額訴訟とは、請求額が60万円以下の裁判で、原則として1日で審理が終了し判決が出る迅速・簡易ば裁判手続きです。
少額訴訟では、一審限りで終結し、控訴することはできません。判決書を受けた日から2週間以内に異議申立てをしなければ、判決は確定してしまい、消滅時効や過払い金の請求ができなくなります。異議申立てをした場合には、通常の訴訟手続きに移行することになります。
ただ、異議申し立てにより再審理が行われ、これを踏まえて判決が出された場合には、これ以上に異議申立てをすることはできなくなります。
③通常訴訟を提起される
債権者による督促を放置していると、通常訴訟を提起されることも多いです。支払督促と同様に、これを放置していると不利な結果を招くおそれがあります。
裁判所からの送達は拒絶できない
債権者が訴状を提出した先の裁判所から債務者の自宅住所に訴状が送達されます。
支払督促の場合も含め裁判所からの送達手続は、特別送達という郵送方法で行います。
相手方となった債務者は、これの受領拒否することはできません。
特別送達とは
特別送達は、郵便配達員から相手方に対して、ポスト投函ではなく、直接手渡しされ、印鑑を押すかサインをして受け取る郵便です。
相手方がこれを受け取らなかったとしても郵便配達員がその場で差し置くことで送達が完了したものとされてしまいます。
仮に、相手方が受領せず、あるいは、居留守を使った場合には、郵便配達員はその場に差し置かないで、一旦持ち帰る可能性があります。この場合には、送達は完了していませんが、通常、土曜日あるいは日曜日に再度送達されます。
付郵便送達とは
それでも、送達ができない場合には、付郵便送達という特殊な送達方法で送達されます。
付郵便送達は債務者が送達先に居住しているにもかかわらず、裁判所から郵便された書類を受け取らなかったため、裁判所に返送されてしまったような場合に行う送達手続です。
付郵便送達を行うにあたっては、その住所地に相手方が居住している事実を客観的な資料をもって説明できなければなりません。通常、住民票や附表に記載された住所、外観から見た生活感、郵便ポストの状況、電気・ガスメーターの状況、隣人からの聴き取りなどを根拠とした報告書を提出します。
付郵便送達による送達がなされると、実際に債務者が裁判所からの書類を受け取っていないとしても、郵便物を発送した時点で送達が完了されたものとみなされます。
そのため、書類を受け取っていないことを理由に、漫然と放置すると、いつの間にか支払督促や判決が出されていることもあります。
就業先送達と公示送達とは
住民票を移さずに転居し、新住所を債権者に届け出なかった場合、就業先送達や公示送達という手続により裁判手続が進んでしまう可能性があります。
多重債務で苦しんでいる債務者の方であれば、金融機関等からの連日の催促から逃れたいあまり、無届で転居をすることはよくあります。
この場合、債権者は、訴状を送達できる住所を知ることができません。
就業先送達
その場合にまず検討するのは、債務者の勤務先への送達です。
債務者の住所が分からない、あるいは、現住所に送達したが受領を拒否する場合で、債権者が債務者の職場を知っている場合には、債権者の職場に送達することもできます。
借入時に、金融機関等の債権者に対して、収入証明として給与明細や源泉徴収票を提出している場合には、債権者は債務者の就業先を把握しています。
しかし、債権者に対して就業先を伝えていない、あるいは、借入時に就業先を伝えたものの、借入後に転職をし新しい職場を伝えていない場合には、就業先への送達はできません。
公示送達
この場合には、公示送達という送達を行います。
公示送達を行うにあたっては、被告の住所地や就業先が分からないことを客観的な資料をもって説明できなければなりません。通常、住民票や附表の内容、外観上生活感がないこと、郵便ポストの状況、電気・ガスメーターの状況、隣人からの聴き取りなどを根拠とした報告書を提出します。
被告とされる債務者が訴状を受領しないとしても、書類を裁判所の掲示板に掲示し、掲示後2週間経過した時点で送達したものとされます。
公示送達のより送達がなされると、裁判手続を行なわれていることを知ることはほぼ不可能です。
そのため、債務者はの知らない間に債権者の請求を認める判決が確定してしまいます。
訴訟提起された時の手続の流れ
訴訟手続とは、個人間の法律上の問題、例えば、お金を返してくれない、浮気をされて精神的苦痛を受けたなどの問題について、中立の立場にある裁判官が、当事者双方の言い分を聞き、証拠を調べたりした後に、判決を出すことによって紛争解決を図ろうとするものです。
以下では、債権者が訴訟提起をしてから解決するまでの流れを紹介します。
訴状の送達と答弁書の提出
訴状が被告に対して送達されると、初回の口頭弁論期日が記載された呼び出し状が同封されています。
呼出状には、答弁書の書式も入っていますので、初回期日の1週間前に答弁書を提出するようにします。
この答弁書の提出期日を過ぎたとしても答弁書を提出できなくなるわけではありません。
ただし、初回期日までに答弁書を提出せずに欠席してしまうと、債権者である原告の請求を認めたものと扱われることがあります。
そのため、初回期日までに答弁書は必ず出すようにします。
答弁書には、原告の請求を認めるのか認めないのかを最低限記載するようにします。
請求を基礎付ける請求原因が正しいのか正しくないのかに関する認否については、第2回目の期日以降に準備書面によりしても構いません。
第1回期日(初回期日)
答弁書を提出できれば、初回期日は必ずしも出頭する必要はありません。
初回期日に限り、被告は欠席しても答弁書の提出をもって裁判に出席したものとみなされます。
これを陳述擬制と呼んでいます。
第2回期日以降
第2回目の期日以降、原告と被告がそれぞれ交代しながら準備書面を提出します。
つまり、第2回目期日には被告が書面を提出し、これを受けて第3回目期日には原告が書面を提出するといった具合です。
和解の提案と判決
その後、主張立証を尽くした段階で、裁判官から和解の提案があります。和解が成立できない場合には、証人尋問を行った上で、判決がなされます。
裁判所の通知を放置することのリスク
裁判所から支払督促・訴状が届いたにもかかわらず、これを放置すると反論する機会を失い、差押えを受けるリスクがあります。
消滅時効の主張ができなくなる
裁判所からの連絡を放置すると、消滅時効の主張ができなくなります。
消滅時効とは何か?
借金をはじめとする債務には時効があります。
時効期間が到来した場合、消滅時効の援用、つまり、時効の完成によって債務が消えることを主張することができます。
2020年4月以降に成立した貸金の債務の場合、債務の性質に関わらず、原則として5年の時効期間となります。
借金の場合には、最後の取引日から5年が経過していれば時効となります。
最後の取引日とは、最後に借入をした日、あるいは、最後に返済した日を指します。
時効の更新(中断)
先程の消滅時効の期間が到来する前に、時効の更新(中断)が生じると、その時から改めて時効期間が進行することになります。
例えば、時効完成前に、借金の一部を返済した場合や借金の支払いの猶予を求めた場合には、債務の存在を認めたものとして、時効更新の事由の一つである『承認』となります。
その他にも、時効完成前に、債権者が支払督促や訴訟提起をした場合には、『裁判上の請求』として時効の完成猶予となります。判決の確定等により時効の更新となります。
裁判の放置は時効を援用できなくなる
裁判所からの通知を放置すると、支払督促や判決が確定します。
確定判決がなされた借金は、10年の時効期間となります。
そのため、借入が消滅時効の期間を迎えており、時効の援用により消すことができるにも関わらず、裁判所からの通知を放置して確定させてしまうと、以後、時効期間が再度到来するまで、時効援用できなくなります。
なお、民法改正に伴って、2020年4月1日以降に成立した債権については、貸主が金融機関なのか、そうでないのかに関わらず、時効期間は5年に短縮されています。
2020年4月1日までに成立した債権について、金融機関との取引による債権であれば、時効期間は5年ですが、信用金庫や保証協会を債権者とする債権であれば、その時効期間は10年となります。
過払金の請求
平成18年頃よりも以前から消費者金融やキャッシングを利用されている場合、金融機関に対して過払金の請求をすることができます。
2010年に貸金業法が改正・施行されました。これにより、改正前の利息制限法を超えて高い金利を支払ってきた場合には、金融機関に対して不当利得として過払い金の請求ができます。
過払金そのものに加えて、過払金に対する現在までの遅延損害金も発生しますから、これらを合わせるとかなりの高額になることがあります。
また、仮に過払金が発生しないとしても、利息制限法に沿った利息の引き直し計算をすると、借金の金額を減額できることがあります。
しかし、裁判所からの送達を無視したり、公示送達による送達がなされると、過払金の請求等をする機会がなくなります。確定判決の既判力により過払い金の請求が難しくなります。
本来は過払金の発生により、貸金請求は認められない事案であるにも関わらず、裁判所からの呼び出しを無視してしまうと、貸金請求が認められてしまう結果となります。
和解による解決の機会を失う
金融機関による貸金請求の場合、それ程大きな法律上の争点がないことが多いことから、早期の段階で、和解成立後の利息や遅延損害金を免除した上で、和解時点の元利金を分割払いする内容の和解が成立することが多いです。
裁判所からの呼出を無視すると、債権者との和解交渉を行う機会を失いますので、注意が必要です。
差押え通知が届く
判決や支払督促の確定により、債務者は最終的に強制執行を免れることができなくなります。
支払督促や判決がなされたとしても、自動的に債権者が借金の回収を実現できるわけではありません。
ここはよく誤解のあるところですが、裁判所などの国の機関が債権者の代わりに財産を見つけてきて、そこから徴収することはありません。
支払督促や判決を受けて、債務者が任意に支払うのであれば別ですが、債務者が任意に支払うわないのであれば、債権者は支払督促や判決の内容を実現させるために差し押さえ等の強制執行をする必要があります。
差押えの対象となる財産
差押えの対象には、預貯金の口座残高、自宅不動産だけでなく、債務者の勤務先の給与や取引先の売掛金、退職金も含まれています。
給料の差押えにより、勤務先に借入の事実やこれを滞納している事実を把握されてしまいます。
ただ、債権者において、差押えをする財産を調査しなければいけません。
個人情報の関係で、債務者の財産を調査することは容易ではありません。
そのため、債権者が債務者の財産を差押える場合、引落口座に指定していた銀行預金口座、借入時に提出していた収入資料を根拠とした勤務先に対する給与債権を対象とすることが多いです。
裁判所からの通知に対する対応方法
裁判所からの通知に対しては、無視することなく所定の手続きを取ることが大切です。
放置することは、本来主張できる主張が出来なくなるなど、様々な不利益を生じさせるため厳禁です。
支払督促の場合
支払督促には「督促異議申立書」が同封されています。
督促異議申立書を提出すれば、少なくとも支払督促による強制執行は免れることができるので、必ず2週間以内には提出するようにしましょう。支払督促を無視することは回避しましょう。
訴訟提起の場合
訴状が届いた場合も、原則として裁判所に出廷しなければなりません。
遠方の場合には、電話会議システムを利用することで弁論準備期日に出席することができます。
督促異議の申立書を提出した場合も通常の訴訟に移行することになるので、訴状が届いた場合と同様、訴訟手続が進行することになります。いずれにしても、裁判所から通知が届くということは、何らかの法的な手段が取られていることを意味します。
法律に対する知識が乏しい場合、自力でこれに対抗することは困難といわざるを得ません。
ですから、時効の援用などの有利な主張をすることで債権者の請求を排除するためにも、強制執行による不利益を免れるためにも、裁判所から通知が届いた際は弁護士など専門家に相談してしっかりと対応していくべきでしょう。
移送申立てをする
係属する裁判所が、遠方のため指定された期日に出頭できない場合や住所に間違いがある場合には、自分の住所地を管轄する裁判所に事件を移すよう求めることを検討します。これを移送申立てといいます。
住所地に間違いがある場合の移送申立は認められやすいですが、それ以外の理由による移送申立ては、相手方の了解を得られない限り難しいことが多いでしょう。仮に裁判所が遠方であったとしても、電話会議システムを利用することで、裁判期日に出席することは十分に可能です。
裁判所からの通知を受けたら弁護士に相談を

多重債務を負っている場合、ついつい借金から目を背けたくなるかと思います。
しかし、借金から目を背けると、様々な不都合が生じます。
できるだけ早い時期に適切な対応をすることが大事です。まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。お気軽にご相談下さい。対応地域は大阪府全域、和歌山県、奈良県その他関西圏です。