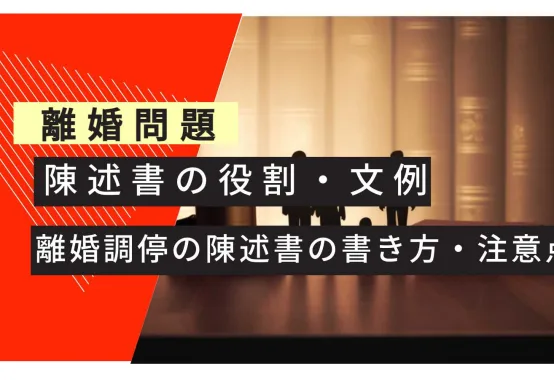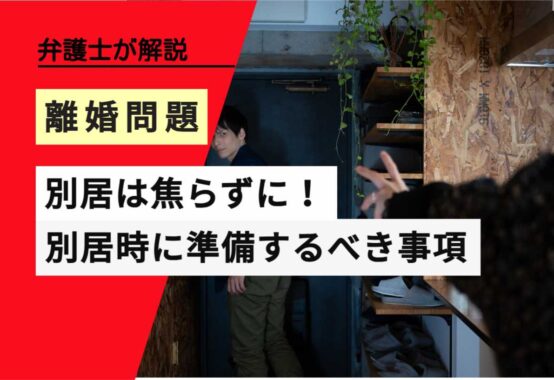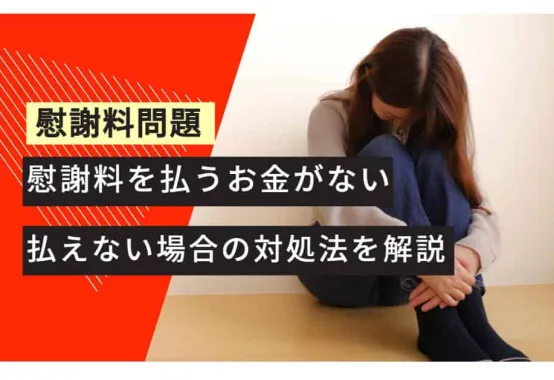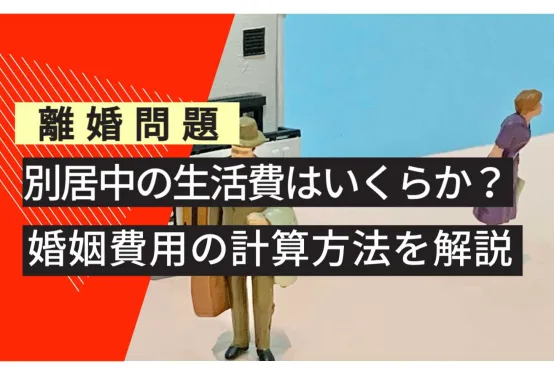妊娠中であれば、新しい家族を迎えるため、辛い時期もありますが、幸せな期間でもあるはずです。
しかし、マタニティブルーやモラハラなどの様々な要因により、妊娠中であっても夫婦仲が悪化し離婚を考えなくてはならないケースもあります。
妊娠中の離婚である場合、将来産まれてくる子どもの養育費の問題に加えて、財産分与、慰謝料、年金分割等の離婚条件を解決しなければならず、妊娠中の身には大変な負担になることが予想されます。
本記事では、妊娠中であっても離婚する場合の離婚問題を、離婚問題に注力する弁護士が解説します。
妊娠中でも離婚できるのか??

子どもを妊娠中だからと言っても、離婚は可能です。
民法770条には離婚の要件として不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な理由があることなどを挙げていて、妊娠を理由に離婚が制限されることはありません。
妊娠中に離婚したいと思う理由としては次のようなものがあります。
妊娠中に離婚したい理由
- マタニティーブルー
- 不倫・不貞
- DV
- モラハラ
マタニティーブルー
マタニティーブルーは妊娠中や出産後に起こる、うつ症状のことです。
ホルモンバランスの急激な変化、悪阻(つわり)等による体調不良、親になることへの不安を多くの女性が経験し、精神的に不安定な状況となってしまい、中には「離婚したい」と思い詰めてしまうケースもあるようです。
背景には、妊婦である妻の抱えている不安を夫が理解してくれないことや互いのコミュニケーション不足による不満などがあります。
マタニティーブルーの状態になるのは女性だけでありません。
男性の中にも、妻の妊娠や出産に対して強い不安を覚える人がいることが分かっています。中には、将来に対する不安や悩みに押しつぶされて仕事に行けなくなってしまう人や、責任から逃げるために「離婚」を申し出る人もいます。
マタニティーブルーは離婚原因となるのか
ただ、マタニティブルーになったこと、あるいは、これを理由に夫婦間の信頼関係が崩れてしまったことが法律上の離婚原因に当てはまるかというと、該当しません。
離婚原因については、夫婦の両方がこれを争わない場合であれば問題ありませんが、夫婦のうち一方が離婚原因の存在を争う場合には、離婚を求める側で離婚原因が存在することを証明しなければなりません。
マタニティブルーというのは、夫婦の内面的な事情であり、これを離婚原因として証明することは非常に難しいからです。
そのため、相手方が、マタニティブルーを理由とした協議離婚に応じる場合は問題ありませんが、相手方が離婚に応じない場合には、離婚することは難しいでしょう。
この場合には、妻側としては、夫との話し合いを重ねるか、話し合いの余地がないのであれば、別居をした上で婚姻費用等の請求を速やかにするなどして、生活の安定を図るべきでしょう。
夫の不貞(不倫・浮気)
子を身籠ると、悪阻や精神的な不安定さから夫婦のスキンシップが減ってしまい、セックスレス(性交拒否)となってしまいがちです。
そのような原因から、妊娠中に夫が妻以外の女性と不貞行為をしてしまい、離婚に至るケースも少なくありません。中には、妻の妊娠中に他の女性を妊娠させてしまうケースや、他に本気で好きになる女性ができてしまうケースもあります。
妊娠中に突然夫から離婚を切り出される場合には、夫の不貞が関係していることもあるかもしれません。
不貞行為は慰謝料の対象となる
不貞行為は、民法で規定された離婚原因の一つですから、不貞行為を理由に離婚請求をすることは認められます。また、不貞行為を理由とした慰謝料請求も認められます。慰謝料請求は不倫相手に対しても認められます。
ただ、不貞行為とは、配偶者以外の異性と性行為またはこれに準じる行為に及ぶことです。
そのため、キスやラインのやり取りだけでは不貞行為となることはありません。
また、不貞行為が存在していたとしても、不貞行為があることを裏付ける客観的な資料を提示できなければ、相手方が不貞行為の存在を認めない限り、不貞行為が認定されることはありません。
関連記事|不倫・浮気の慰謝料の相場とは?不貞慰謝料の計算方法を弁護士が解説します
関連記事|不貞行為とは何か?どこからが不貞行為かを弁護士が解説します
DV
妊娠中に夫から暴力を受けたことがきっかけで離婚となるケースもあります。
妊娠をきっかけに夫婦間の関係性に変化が生じてしまい、夫から暴力や暴言などのDVを受けることも珍しくありません。
夫から離れないと、自分だけでなく子どもを守れないと考え、離婚を決断する人もいるようです。
DVには身体的な暴力だけでなく、経済的な暴力もあります。
DVは慰謝料の請求対象となる
DVの事実も、夫婦関係を継続し難い事情として離婚原因になり得ます。さらに、離婚慰謝料の請求も認められます。
しかし、先ほどの不貞行為と同じように、相手方が離婚に応じないような場合には、DVが継続して行われてきたことを客観的な資料により証明する必要があります。
具体的には、暴力により出来た傷跡の写真、整形外科の診療録や診断書が挙げられます。また、接近禁止命令が発令されている場合には、これに関する資料も証拠となります。
さらには、DV被害がある度に作成されていた日誌やメモもDVの裏付けとなります。ここで注意点として、その都度DVの事実を書き残しておくことが重要ということです。過去の事実を振り返って一気に日誌等に記録したとしても、記憶が曖昧となっている可能性もあるため、その内容に信用性が認められない可能性があります。
関連記事|DVの慰謝料請求の相場は?DVの慰謝料請求について弁護士が解説
モラハラ
DVのような暴力まではないものの、暴言を吐いたり、相手をおとしめる言動を述べたり、無視し続けるといった精神的な攻撃・暴力、いわゆるモラハラを理由に離婚をしたいと考えるケースも増加しています。
DVと同様、モラハラを行う人は自己愛が強く、モラハラをしている自覚が乏しいケースが多いため、被害者がモラハラを指摘したとしても、改善されることは余りありません。
そのため、妊娠中であったとしても、相手方からのモラハラによる攻撃から回避するために、離婚を決意することがあります。
関連記事|モラハラを原因とした離婚請求が認められるのか弁護士が解説します
妊娠中に離婚するデメリット
妊娠中に離婚する理由は様々ですが、妊娠中に離婚することのデメリットは様々あります。特に、妊娠をしている女性におけるデメリットが顕著といえます。
経済的な負担が生じる
妊娠中に限らず離婚により生活費や教育費の不足が生じる可能性があります。
婚姻関係にあれば、夫は妻を扶養する義務を負いますので、離婚成立まで妻の生活費も含めた婚姻費用を負担しなければなりません。
離婚により、夫は子供の養育費のみを負担し、妻の生活費を負担する義務から解放されます。
さらに、妻は、妊娠や出産に伴い自由に就労することが難しくなります。ひとり親世帯となることで就職活動に制限が生じることもあるかもしれません。
このように、妊娠中に離婚を決断することで、経済的に困窮することがあり得ます。
精神的な負担が生じる
妊娠中に離婚することで様々な精神的な負担が生じるかもしれません。
円満に離婚できれば良いですが、離婚条件で対立する場合には、離婚問題が長期化するおそれがあります。離婚協議が進展しなければ、離婚調停や離婚裁判を行わざるを得ません。たとえ代理人弁護士に一任していたとしても心理的な負担はゼロに出来ません。
さらに、出産直後からひとり親として子供の育児をしなければなりません。特に、子どもの預け先となる両親や親族が近くにいない場合には、育児に伴う精神的な負担は大きくなりがちです
出産後に後悔する
妊娠に伴うホルモンバランスの乱れや環境の急激な変化により、婚姻関係を我慢できなくなり、離婚を決意してしまうことがあります。
しかし、夫婦関係の悪化は一過性のもので、出産後、心身の安定を取り戻してから、離婚を後悔することがあります。
後悔のないように、親族や女性相談センター、カウンセラーに相談するなどして、ご自身の心境と見つめ合うことも必要でしょう。
妊娠中に離婚した場合の戸籍と親権の問題
妊娠中に離婚をするケースでは、子どもの戸籍や親権の扱いが複雑になります。
また、妊娠中に離婚した場合、財産分与や慰謝料はどのように請求できるのでしょうか。くわしく解説していきます。
妊娠中に離婚した子どもの戸籍
元夫が父親になる離婚して婚姻関係がない状態で生まれた子どもは、母親の単独親権となります。
しかし、子どもの戸籍の扱いは離婚した時期により異なります。
まず、離婚届を出してから300日以内に子供が生まれた場合は、元夫を父親として出生届けを出さなければなりません。
ただし、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が作成され、その内容から推定される懐胎時期の最も早い日が離婚後であることが分かる場合には、元夫を父としない出生届を提出することができるとされています。
一方、300日以上たって出産した場合は、戸籍の父親の欄が空白になります。
この場合、父親に子どもを扶養する義務は生じません。父親から養育費を受け取る場合は、父親に「認知届」を出してもらうようにします。
元夫が任意による認知に応じない場合には、家庭裁判所に対して認知を求める調停または審判の申立てを行います。
元夫の戸籍に入籍する
戸籍法には、『子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する』と定められています。
そのため、離婚後300日以内に生まれた子供は、父親の苗字を名乗ることになります。
その結果、離婚後に生まれた子は、離婚した夫が筆頭者の戸籍に入籍することになります。
子供の親権者が母親であったとしても、元夫の戸籍に入籍します。
そして、父親に子供の親権はないものの、一時的に子どもは夫の名字を名乗ることになり、子どもを育てている母親と子どもの名字が異なってしまいます。
そこで、子どもを母親の戸籍に入籍するためには、家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申し立て」をしなければなりません。
母親が婚姻時の父親の苗字を離婚後も継続して名乗っている場合、つまり、離婚後の父の苗字と離婚後の母の苗字が同じであっても、離婚後に生まれた子は元夫の戸籍に入るため、この場合でも、氏の変更許可申立ての手続は必要になります。
戸籍謄本等の必要書類を手配して申立てをするようにしましょう。
TIPS!非嫡出子と嫡出子とは
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にある父母の間に生まれた子のことをいいいます。
離婚してから300日以内に生まれた子は嫡出子となります。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。
別の男性の子供である場合
離婚後300日以内に別の男性の子どもを出産した場合も、嫡出推定により元夫の子供であると推定されるため、生まれてきた子どもは元夫の戸籍に入籍します。
しかし、元夫と子供との間には生物学的な親子関係がないため、戸籍の記載は正しいものではありません。
そこで、嫡出否認の調停申立てをすることによって、子供であることの推定を否定させる必要があります。
しかし、この嫡出否認の手続は、元夫のみ行うことができます。
母や血縁上の父から手続を取ることはできません。
その上、元夫が子の出生を知ってから1年以内に申立てをしなければなりません。
ただ、嫡出推定が及ばない特段の事情を証明することができれば、嫡出否認の手続を行うことなく、子供やその親権者である母親は、家庭裁判所に親子関係不存在の調停あるいは認知を求める調停を申し立てることができます。
特段の事情としては、
- 離婚前から既に夫婦関係が破綻しており事実上の離婚状態であったこと
- 遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである場合
- 夫が刑務所に在監している場合
- 性交渉不在が外観上明白な場合
- 血液型に違いがある場合
が挙げられます。
子どもの親権
妊娠中に離婚した場合、離婚後に出産することになりますから、子どもの親権者は母親になります。
他方で、離婚問題が長期化したことで、離婚前に出産した場合には、子どもの親権は母親と父親の共同親権となります。
そのため、離婚手続きに時間を要したことで離婚前に出産すると、子どもの親権問題が勃発する可能性がありますので注意が必要です。
妊娠中に離婚した子どもの養育費

養育費の決め方離婚後300日以内に出産した場合、嫡出推定により元夫が子供の父親になります。
当然ながら元夫に子どもを扶養する義務が生じます。
また、離婚の成立後300日を経過してから生まれたとしてと、元夫の認知により、元夫には子供を扶養する義務が生じます。
養育費の額は夫婦で決めることとなります。
しかし、元夫が養育費の支払いを拒む場合や養育費の金額に隔たりがある場合には家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることもできます。
養育費の支払いについては口約束だとあいまいになり、途中から元夫が払わなくなるケースもあります。
このような事態にそなえて養育費の取り決めについては公正証書を残しておくのがおすすめです。
養育費の金額について
養育費の金額は、養育費を払う義務のある父の収入と養育費を請求する権利を持つ母の収入を踏まえて計算されます。
一般的に、母親が無職で収入がゼロであったとしても、就労により収入を得ることができるのであれば、母親の収入として100万円から120万円程が認定されることが多いです。
しかし、お子さんが産まれたばかりであれば、母親は働きたくても働けない状況でしょうから、この場合には母親の収入はゼロとなります。
ただ、働けないとしても育児休業給付金を受給している場合には、この給付金は収入として認定されます。また、児童手当も養育費の基礎収入には当たりません。
なお、養育費の問題と一緒に問題となり易いのが、子どもの面会交流です。お互いに負担にならないように、面会交流の条件を調整することが大切です。
養育費の計算方法に関する詳細な解説はこちらのコラムを参照ください。
養育費の減額や増額
養育費の金額を一度決めると、何が生じても変更できないわけではありません。
予測していない将来の事情が生じた場合には、これに応じて養育費の金額も変更する必要があります。
養育費の権利者である母が離婚後に再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、養育費の支払義務はなくなります。
他方で、養育費の義務者である父が離婚後に再婚した場合や新しい子供を授かった場合には、扶養の対象者が増えるため、養育費の金額が減る可能性があります。
出産費用を請求できるのか
夫は、実際に要した出産費用から出産育児一時金を控除した残額を婚姻費用として負担する義務を負います。
婚姻費用とは、婚姻期間中、収入の多い配偶者が少ない配偶者に対して負担する生活費をいいます。この婚姻費用の中には、住居費、食費、教育費、医療費に加えて「出産費用」も含まれています。
他方で、出産費用については、公的扶助として出産育児一時金が支給されます。令和5年4月から、出産育児一時金の支給額は、42万円から50万円に引き上げられています。
出産育児一時金を受給している場合には、実際に発生した出産費用から出産育児一時金を控除した残額を夫婦間で負担することになると解されています。
【横浜家庭裁判所平成24年5月28日決定】出産育児一時金は、公的補助金であるから出産費用はまず一時金によって賄われるべきであるから、不足する出産費用のうち相手方が負担すべき金員を控除した金額は、婚姻費用の前払とみなすのが相当である。
妊娠中の離婚の場合の財産分与
離婚問題全般で対立が生じやすい問題が財産分与です。
財産分与の基礎知識について説明します。
財産分与とは何か?
財産分与とは、婚姻関係にある期間、夫婦で共同して築いてきた財産を貢献度によって分ける仕組みです。
財産分与の対象財産は、同居を開始させた時期から別居した時までに築いた財産です。
夫婦でともに築いた動産・不動産・預貯金などが該当し、夫の単独名義の不動産であっても夫婦で共同して購入したものならば財産分与の対象です。
他方で、結婚する前から有していた財産や結婚前の財産を原資として購入した財産は特有財産として財産分与の対象から除外されます。
また、婚姻中に取得した財産であっても、親族から贈与や相続した財産は財産分与の対象からは外れます。
財産分与には、期限があります。離婚をした日の翌日から2年以内に財産分与の請求をする必要があります。
そのため、離婚時に財産分与に関する合意をしていない場合には、2年の期限には注意をしてください。
扶養的財産分与とは?
本来、財産分与は、夫婦共有財産を一方の配偶者から他方に分与する清算的な意味合いを持っています。
しかし、これまで育児や家事に専念してきた専業主婦が、離婚によって生活の基盤を一切失ってしまうことは酷です。
そこで、専業主婦であった妻の生活を支援するため、もともと扶養義務のあった夫が妻に対して支払われるものが扶養的財産分与です。
一般的には離婚後1年から3年程の期間の婚姻費用相当額が離婚時に支払われることが多いです。
| 財産分与の調停に関する裁判所の解説はこちら |
妊娠中に離婚した場合の慰謝料
妊娠中に離婚するだけでは、これだけを理由として慰謝料は発生しません。
慰謝料は、婚姻関係を破綻する重大な不法行為があった際に、不法行為をした人に対して請求できます。
性格の不一致で離婚するケースでは慰謝料を請求することは難しいでしょう。
ここで言う「不法行為」とは元夫の不貞行為や暴力、生活費を渡さないなどの経済的DVが該当します。
妊娠中に夫の不貞行為で離婚をして中絶を余儀なくされたケースでも、慰謝料の請求は可能です。
逆に妻が有責配偶者となる場合は、夫側から慰謝料を請求されることもあり得ます。
なお、妊娠中に夫の不貞行為やDVが原因で離婚をする場合の慰謝料は、相場よりも高くなることが多いです。
妊娠中に離婚した場合の年金分割
婚姻期間中、夫が会社員または公務員であった場合は、妻は厚生年金部分の分割請求をすることができます。妻が専業主婦であった場合だけでなく共働きであったとしても年金分割は認められます。
あくまでも年金分割は、厚生年金や共済年金部分だけで、かつ、年金受給額そのものが分割されるのではなく婚姻期間中の厚生年金等の納付記録のみが分割されますので、注意を要します。
年金分割を請求するには、離婚をした日の翌日から2年以内に請求手続をする必要があります。
離婚時に年金分割の手続をしなかった場合には、この2年の期限を徒過しない間に手続を行うようにしてください。
年金分割の按分割合については、当事者間で協議により決めますが、相手方との協議が整わない場合には年金分割に関する調停申立てをすることになります。
平成20年4月1日以後の厚生年金記録については、合意をせずに必要とされる書類を準備して年金事務所に提出すれば足ります。
ほとんどの事案では、年金分割の按分割合は5:5とされます。
年金分割の詳細については、こちらのコラムで解説していますのでご参考ください。


シングルマザーの公的支援
母子家庭の平均年収は240万円とそれており、一般の子育て家庭に比べて少なくないのが実態です。そこで、母子家庭向けの公的な支援を積極的に活用することで、離婚後の生活不安を解消していきましょう。
子供の養育には多くのお金が必要となります。受けられる支援は可能な限り受給するようにしましょう。
シングルマザーの支援制度は以下のようなものがあります。
シングルマザーの公的支援
- 児童扶養手当
- 生活保護の申請
- 社会保険料の減免
- 自立支援訓練給付金
- 高等職業訓練促進給付金等事業
児童扶養手当
児童扶養手当はひとり親家庭の子どもに対して支給される手当で、0歳から18歳に到達したあとの3月31日まで受け取れます。
児童扶養手当は、子どもを育てる親の所得額により「全額支給」「一部支給」「不支給」となります。
「全額支給」の場合だと1人目の子どもは月額4万3160円、2人目の子どもは月額1万190円が加算、3人目以降の子どもは1人あたり月額6110円の加算となります。
一部支給の場合、1人目の子供は月額1万180~4万3150円、2人目の子供は月額1万180~4万3150円、3人目以降の子供は月額3060~6100円を加算となります。

所得制限とは
上記のとおり児童扶養手当には所得制限があります。

扶養人数とは、扶養している子供の人数のほか、ひとり親が親自身の親(子供からみて祖父母)やきょうだい等の親族を扶養している場合には、その扶養人数に含まれます。
扶養人数0人というのは、ひとり親である母親が子供と一緒に暮らしているものの、父親の扶養に入っているような事案や前年末の時点で子どもが生まれていなかった事案を想定しています。
所得制限における所得とは給与収入の額面ではなく、額面の収入額から所定の経費や養育費相当額等を控除することで導き出される所得を言います。
児童扶養手当で審査される所得の計算方法
児童扶養手当が支給されるかは所得額によります。
その所得額の計算方法は以下のとおりです。
①所得(収入-必要経費)+②養育費の8割-③8万円-④諸控除①について
収入から必要経費を引いた残額の所得とは、会社員等の給与所得者であれば、源泉徴収票における「給与所得控除後の金額」、個人事業主の場合には、確定申告書における「所得金額」が当たります。
②について
養育費の8割というのは、前年に養育費を受け取っている場合には、受給額の8割を所得に加算されます。
③について
「8万円」は一律に控除される金額となります。
④について
諸控除には、以下のものがあります。
控除一覧
障害者控除:27万円
特別障害者控除:40万円
勤労学生控除:27万円
小規模企業共済等掛金控除:地方税法で控除された額
配偶者特別控除:地方税法で控除された額
医療費控除:地方税法で控除された額 など
生活保護の申請
幼い子どもを養育監護していれば、思うように就職活動が進まず就労できないことも想定されます。
夫から支払われる養育費や支給される児童手当・児童扶養手当だけでは、最低生活費に不足が生じるのであれば、積極的に生活保護の利用をするべきです。
ただし、資産を保有している場合や養育費・児童扶養手当の金額が最低生活費を超えている場合には、生活保護の受給は認められません。
社会保険料の減免
前年度の所得が少ない場合、国民年金保険料と国民健康保険料が免除あるいは減額になります。
また、出産予定日がある月の前の月から4カ月間は、国民年金保険料や国民健康保険料が免除となります。
社会保険料の減免を受けるためには、年金事務所か市区町村の年金窓口に申請をしなければなりません。
自立支援訓練給付金
自立支援訓練給付金とは、ひとり親の主体的な能力開発の取組みを支援するため、20歳未満の子どもを育てているひとり親家庭の親に対して、児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準の場合に受けられる就業支援です。
具体的には、対象教育訓練を受講し、これを修了した場合に、その経費の60%が支給されます。
対象となる講座はあらかじめ決められています。
高等職業訓練促進給付金等事業
高等職業訓練促進給付金等事業は、看護師や保育士、歯科衛生士や介護福祉士、保健師、助産師など就職に有利となる資格を身につける際に、学費や生活費の負担を軽減するための給付金を受け取れる制度です。
制度の対象となるのは自立支援訓練給付金同様、20歳未満の子どもを育てているひとり親家庭の親で、児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準の人です。ここに挙げたのは一例です。多くの自治体がシングルマザーの子育てを支援する取り組みを行っています。
くわしくは自治体の保健師や民生委員、産婦人科のスタッフなどに問い合わせてみるとよいでしょう。
妊娠中に離婚するための離婚手続き
夫婦が離婚するための離婚手続きには以下の3種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
離婚手続の基本的な知識を以下で整理します。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いをした上で、離婚届を提出することで離婚を成立させるプロセスです。
離婚時に子供が生まれていないのであれば、親権者を決める必要はありませんが、将来生まれてくる子供の養育費の金額や終期等は話し合いをしておくことが重要です。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停の申立てをした上で、調停続きを通じて離婚を成立させる手続です。
調停手続とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員2人で構成される調停委員会による仲裁の下、申立人とその相手方が話し合いを進める手続です。
調停委員が間に入って、双方の言い分を聞き、条件の調整をしますので、当事者が直接対峙して話し合うことはありません。
裁判離婚
調停手続を進めたものの、離婚条件の調整ができなければ、調停手続は不成立となります。
その場合、一方の配偶者が、離婚を求めるのであれば、他方の配偶者を被告とした離婚訴訟を提起することになります。
訴訟手続では、調停のような話し合いの要素は薄く、双方が主張と反論を繰り返し、これらを踏まえて、裁判官が離婚原因の有無を認定していきます。
ただし、訴訟手続においても、裁判官の仲裁を通じて離婚条件を協議した上で、裁判上の和解により解決するケースも非常に多いです。
裁判官の仲裁によっても解決できない場合には、離婚の是非は判決により判断されることになります。
妊娠中の離婚問題はご相談ください

妊娠中の離婚には、そもそも離婚できるのかという問題だけでなく、離婚後の養育費や戸籍問題等の様々な問題が待ち受けています。
幼い子どもの養育監護に追われ、これら問題を直視できず放置してしまうと、得られるはずの経済的な利益を失うおそれがあります。
一人で抱え込んでしまうと、精神的な負担が大きくなってしまいます。
また、当事者間での協議は、多くのトラブルを招いてしまうリスクもあります。
弁護士に依頼するメリット
- 妊娠中の離婚問題を解決できる
- 離婚問題全般を一任できる
- 適切な養育費を合意できる
- 自身に有利な条件で解決できる
大変な時期かと思いますが、後悔しないためにも、まずは弁護士に相談することを検討してください。
当事務所は、離婚・男女問題に注力しており、数多くの離婚相談をお受けしています。
初回相談30分を無料で実施しており、土日祝日も対応しております。
一人で悩まずにお気軽にご相談下さい