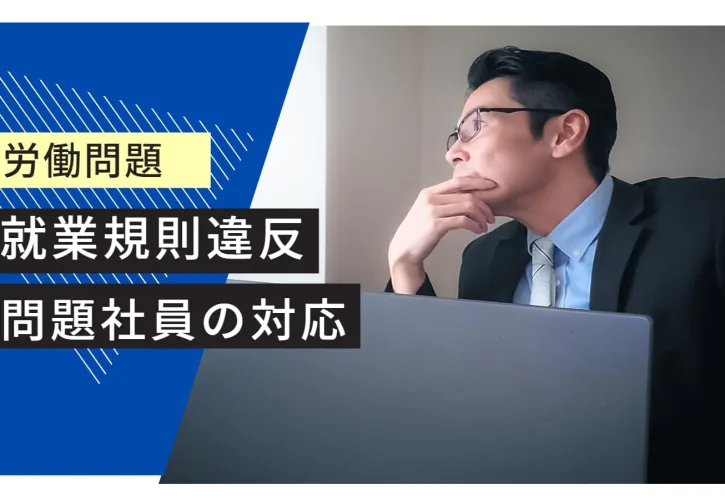従業員が就業規則に違反したからといって、解雇できるものではありません。裁判例でも懲戒解雇を認めるものと認めないものがあります。
一口に「就業規則違反」といっても、個別的な状況によって企業のとるべき対処方法が異なるので、正しい知識をもっておきましょう。
今回は就業規則違反があった場合の解雇の有効性や企業のとるべき対処方法を弁護士が解説します。
解雇が関わる問題は、雇用主側にとっても解雇予告手当・退職金・助成金に大きな違いが出てきます。解雇と退職の違いや、会社都合退職と自己都合退職の違いについては、下記のコラムを参考になさってください。
関連記事:解雇と退職の違いとは?会社都合退・自己都合退職の違いとは?
関連記事:解雇予告手当の計算方法|解雇予告手当の支給日や免除されるケースを解説します
就業規則は社内に通用するルール
就業規則は会社が定める社内のルールです。
常時10人以上の労働者がはたらく事業所では、必ず就業規則を策定して従業員へ周知しなければなりません。
いったん就業規則を定めると、その内容は労働契約の一部となり、従業員を拘束します。
ただし法令に反することはできません。たとえば労働基準法の定める最低要件に満たない条件を就業規則に規定しても無効になります。
具体的な内容は会社によっても異なりますが、厚生労働省から「モデル就業規則」が発表されており、だいたいは似通った内容になっているケースが多数です。
就業規則違反でよくある例
就業規則違反でよくある例を示します。
- 会社の機密情報や顧客情報を持ち出した
- 無断欠勤や遅刻
- タイムカードを不正に打刻した
- クレームを隠蔽した
- 不正な経費精算を行った
- 業務命令違反をした
- 故意や不注意により、会社に損害を与えた
- 取引先から個人的にリベートを受けとった
- パワハラやセクハラ行為を行った
- 副業が禁止されている企業で無断副業を行った
- 転勤を予定されている労働者が転勤を拒否した
無断欠勤が続く社員への対応については、下記のコラムで解説しております。
関連記事:無断欠勤が続く社員をどう対応すべきか?解雇することはできますか?


就業規則違反を放置するのはNG

従業員の就業規則違反は決して放置してはいけません。
就業規則違反を漫然と放置することは、会社に諸々の損失を招きます。
企業秩序の乱れを招く
就業規則は、会社内のルールです。これに抵触する行為があるにもかかわらず、これを放置すれば、会社内の企業秩序が乱れてしまいます。
そのような会社の姿を目にした従業員は、会社に対する忠誠心を失い、モチベーションを低下させます。結果的に、優秀な従業員の離職を引き起こします。
さらに、従業員の就労環境の乱れにより、優秀な人材の雇用も困難となり、会社の生産性を低下させます。
損害賠償を受けるリスク
就業規則違反の放置には、被害従業員から損害賠償を受けるリスクもあります。
従業員のパワハラやセクハラの場合、加害行為を行う従業員と被害を受ける従業員がいます。
会社は、会社内のハラスメントを排除し、従業員の職場環境を整備する義務を負っています。
それにもかかわらず、会社が加害従業員のハラスメントを漫然と放置すると、被害者である従業員の損害を拡大させます。その結果、会社は、被害従業員から、先ほどの就労環境整備義務の違反を理由として損害賠償請求を受ける可能性があります。


就業規則違反に対する対応
就業規則違反を行った従業員に対して、懲戒処分を行うべきです。
懲戒処分とは、会社が問題行動をとった従業員へ与えるペナルティです。
従業員が就業規則に違反したにもかかわらず、何らの対応もせずに放置すれば会社の規律は乱れ、様々な不具合が生じます。
そこで会社は従業員に懲戒処分として、ペナルティを与えられるのです。ただ、就業規則違反の程度やこれまでの勤務態度等によっては、懲戒処分ではなく、口頭による注意や反省文の提出に留めることはあります。
懲戒解雇は、こうした懲戒処分の中でももっとも重い処分の一つです。
懲戒処分の種類
懲戒処分の種類を軽いものから順番にみてみましょう。
戒告
問題行動を行った従業員に注意する処分です。
減給
給料を一定額、減額する処分です。ただし減額できる限度額は労働基準法によって定められているので、その基準を超えてはなりません。
①1回の額(すなわち、1件の懲戒事案についての減給額)が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
②数件の懲戒事案について減給処分を行う場合、その総額がひと月の給与総額の10分の1を超えてはならない。
出勤停止
一定期間、出勤停止とする処分です。出勤しない日の給料を支払う必要はありません。
なお、これとは異なる業務命令の一つである自宅待機命令の場合には、待機中の給与を支払う必要が生じます。
降格
現在の役職を解いたり引き下げたりする処分です。降格に伴う賃金の引き下げの場合には、減給処分のような制限は及びません。
ただし、降格処分によっても業務内容等に何らの変化もない場合には、賃金の引き下げは許容されないこともあります。
諭旨解雇
懲戒解雇を前提としながらも、いきなり解雇するのではなく自主退職を促す処分です。
解雇すると退職金が不支給となるケースも多いので、まずは自主退職を試みます。
従業員側が退職に応じなければ懲戒解雇を行います。
懲戒解雇
従業員の行った違背行為が重大な場合、懲戒解雇を行って労働契約を解消します。
就業規則違反で「解雇」できる条件
従業員が就業規則違反の行為をしたとしても、必ず解雇できるわけではありません。
解雇するには以下の条件を満たす必要があります。
有効な就業規則がある
有効な就業規則がなければ就業規則違反の懲戒処分はできません。
最低限、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項が含まれていて、労働基準監督署へ提出する必要があります。従業員への周知も行われていなければなりません。
また労働基準法をはじめとする法令に違反する内容は無効となります。
就業規則に懲戒規定が定められている
懲戒処分を行うには、就業規則に懲戒規定が必要です。
懲戒に関する規定をおいていなければ、違反があっても懲戒処分できません。
就業規則違反の非違行為が存在する
従業員が実際に就業規則違反の非違行為をした事実がなければ懲戒できません。
たとえばセクハラやパワハラが疑われたとしても、事実確認できていないなら懲戒してはなりません。
就業規則に沿った懲戒手続きを行う
就業規則で懲戒手続の進め方について規定されている場合、規定に沿った方法で懲戒手続きを進めなければなりません。
たとえば就業規則では「従業員側に弁明の機会を与える」と書かれているのに弁明を聞かずに懲戒すると、無効になる可能性が濃厚です。
違反行為と懲戒解雇のバランスがとれている
従業員による就業規則違反の行為と懲戒解雇にバランスがとれていることも必要です。
軽い就業規則違反に対して解雇を行うと無効になる可能性が高いでしょう。
たとえば副業を禁止している会社で従業員が副業をしていたとき、業務にまったく支障が出ていないにもかかわらずいきなり解雇すると無効になる可能性があります。
就業規則違反を発見した場合の対処方法
会社が従業員による就業規則違反を発見したら、以下のように対応しましょう。
事実確認を行う
まずは就業規則違反の行為があったのか、事実確認すべきです。
- 遅刻や欠勤があった場合には理由や事情を確認する
- セクハラやパワハラが疑われる場合にはプライバシーにも配慮しながら調査する
- 副業した場合には内容や副業による収入額、顧客情報の持ち出しの有無や業務時間などを調査する
- 横領行為が疑われる場合には実際に横領があったのか、いついくら横領されたのか調べる
上記のような方法で確認を進めましょう。
戒告、始末書を提出させる
軽い就業規則違反であれば厳重注意とするか、懲戒処分である戒告処分とし、「始末書」を提出させて終わらせることも可能です。
減給、降格などの懲戒処分を適用する
戒告のみで済ませるべきではないケースであれば、減給や出勤停止処分も検討しましょう。
場合によっては今の役職を解いて降格させることも検討すべきです。
セクハラやパワハラ、人間関係の問題がある場合には異動させると問題を改善できるケースもあります。
退職勧奨を行う
就業規則違反の行為が重大で労働契約の解消もやむを得ない場合、懲戒解雇も検討すべきです。
ただしいきなり解雇するのではなく、まずは「諭旨解雇」として退職勧奨を行う方法があります。
懲戒解雇にすると、従業員側から「解雇無効」「不当解雇」として争われる可能性があります。
一方退職勧奨によって自主的に退職させた場合、基本的には不当解雇になりません。
また懲戒解雇の場合には退職金が不支給となるケースが多数ですが、自主退職なら一定額は支給されるので従業員側にもメリットがあります。
従業員側と話し合い、自主的な退職届の提出を求めましょう。
懲戒解雇する
従業員が退職勧奨に応じない場合や諭旨解雇すら相当でないと考えられる場合には、懲戒解雇を行います。
就業規則違反を予防するためには
従業員の就業規則違反は、従業員側の原因のみで生じるわけではありません。
会社側の不十分な労務管理によって、就業規則違反を招いている可能性もあります。
就業規則違反を防ぐためには
- 定期的な就業規則の変更
- 就業規則の周知徹底
- モチベーションの向上
定期的な就業規則の変更を行う
就業規則を定期的に改訂することが重要です。
一度、就業規則を作成した以降、就業規則を変更することなく作りっ放しにすることはよくあります。
しかし、就業規則は、会社内のルールですので、会社の事業規模、従業員の人数や構成といった組織構造に適したものであることが必要です。
また、労働関連法令は毎年のように改正されます。すべての法改正に就業規則を対応させる必要まではありませんが、重要な法改正があれば、これに対応する形で就業規則を変更させなければなりません。
そのため、就業規則が社内のルールとして十分な役割を果たすためには、定期的に変更・改訂を行うようにします。
就業規則の周知を徹底させる
就業規則を従業員に周知させた上で、その遵守を徹底させます。
就業規則の周知は、就業規則が効力を生じるための条件です。
しかし、従業員が就業規則を見たことがない、どこにあるのか知らないといったケースも散見されます。このような状態では、従業員が、知らず知らずのうちに就業規則に違反してしまっている可能性もあります。
そこで、従業員に就業規則を配布したり、就業規則の保管場所を知らせて就業規則の内容を周知させるようにします。
その上で、朝礼や定例会議、セミナー受講を通じて、就業規則の役割、就業規則に違反した場合のペナルティを従業員に認識させます。これにより、就業規則の遵守を徹底させます。
従業員のモチベーションの向上を図る
従業員のモチベーションの維持と向上に努めます。
従業員の会社に対する忠誠心(ロイヤリティ)が低ければ、いくら就業規則を周知させても、就業規則を守ろうとする意欲が生まれません。
そのため、従業員の忠誠心とモチベーションを改善するように努めることが重要です。
• 人事評価制度を明確にする
• 目標を達成した従業員を表彰する
• 挑戦する機会を与える
• 就労環境を改善する
以上の施策を織り交ぜながら、従業員のモチベーションの改善を図ります。
懲戒解雇の場合の退職金
懲戒解雇する場合、退職金の一部や全部を不支給とできる可能性があります。
ただしすべての事案で一律に不支給とできるわけではありません。
まずは就業規則や退職金規定において「懲戒解雇となった場合には退職金の減額や不支給ができる」と定められている必要があります。
また「退職金を不支給とするほどの重大な背信性」が必要です。
実際に多くの裁判例では、懲戒解雇が認められる程度の問題行動があっても、退職金の全額不支給までは認められていません。
そもそも不支給が認められるのか、何割カットとすべきかは個別的な状況に応じて判断する必要があります。迷ったときには弁護士までご相談ください。
当事務所では企業の労務管理や労働トラブルの解決支援に力を入れています。就業規則違反の従業員への対処はお任せください。
問題社員の対応は弁護士に相談を
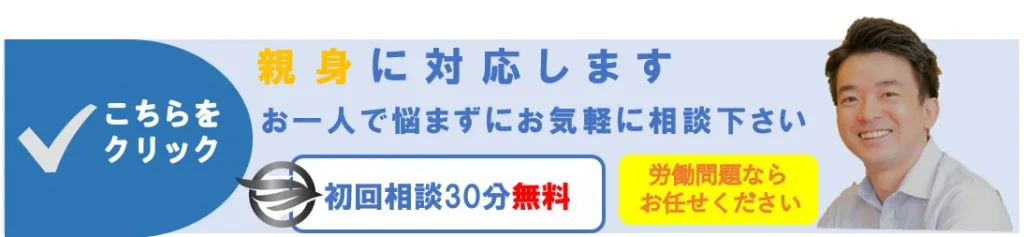
就業規則に違反する問題社員を放置することは、事業運営に数々の支障を生じさせます。
かといって、拙速な対応は、想像以上の負担を強いられてしまいます。
問題社員の対応には、慎重な対応が重要です。
当事務所では、数多くの労働問題を扱っております。
初回30分相談無料にてお受けしています。
お気軽にご相談ください。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。