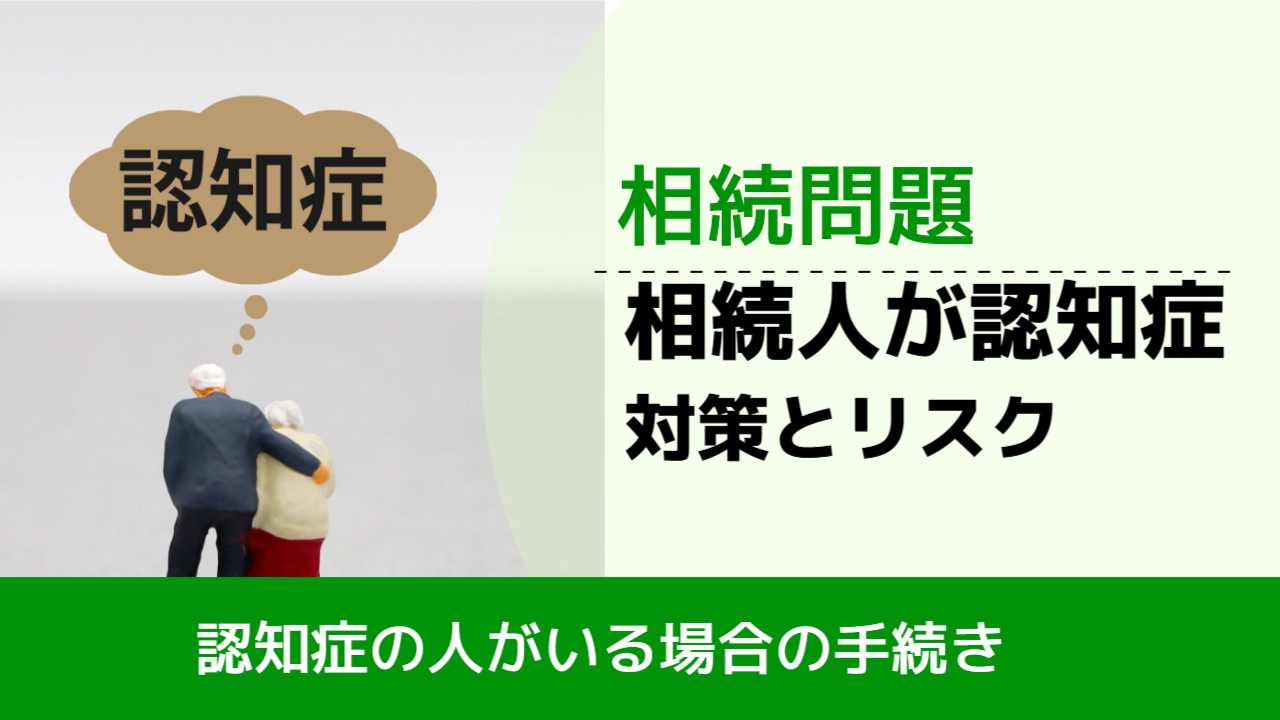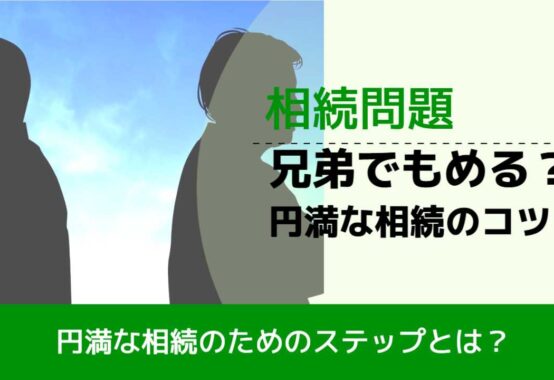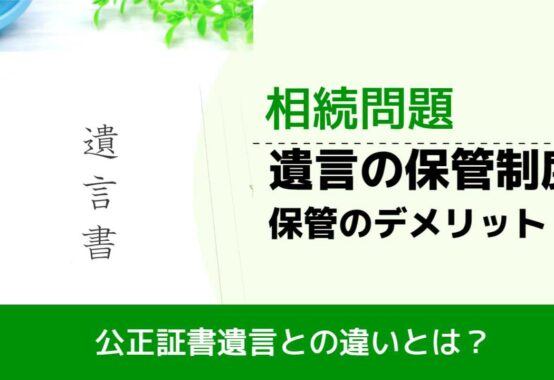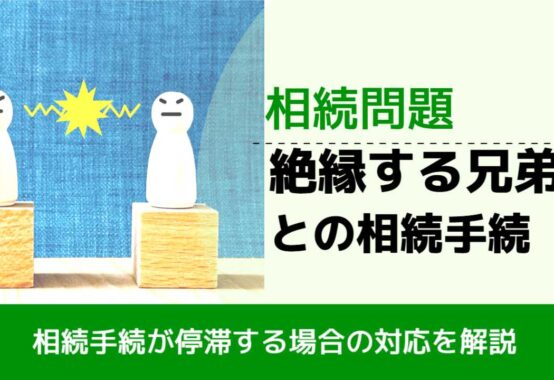相続の手続きは煩雑になりがちです。特に、もし相続人の中に、認知症を患っている方がいらっしゃる場合、さらに複雑な問題に直面することも少なくありません。
「遺産分割協議がスムーズに進まないのでは?」
「成年後見制度って、どうすれば良いの?」
そのような不安や疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、認知症の方がいる状況での相続について、知っておくべき手続きや、遺産分割で困らないための対策をわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
相続人が認知症だと相続手続きが止まる?まず知っておきたい問題点
相続手続きを進める上で、特に重要なのが「遺産分割協議」です。相続人の中に認知症の人がいる場合に、具体的にどのような問題が発生するのでしょうか。以下の項目で詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議が進められず無効になってしまう
相続手続きを進める上で、特に重要なのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要な手続きです。相続人が一人でも欠けていたり、全員の合意が得られなかったりした場合には、遺産分割協議は成立しません。特に、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、物事を判断する能力である「意思能力」がないと見なされる可能性があります。
意思能力を欠く者が参加した遺産分割協議は、法的に無効となるため注意が必要です。ただ、相続人が認知症であるからといって、当然に遺産分割協議が無効になるわけではありません。認知症の影響により、遺産の内容を把握して、誰がどの遺産を取得するのかを認識・判断できるだけの能力が欠けている場合に、遺産分割協議が無効となります。たとえ認知症を患っていても、このような能力があれば遺産分割協議は無効になりません。
仮に、認知症により判断能力を欠く相続人から署名や押印を得たとしても、後になってその合意が有効ではないと判断されるケースもあります。遺産分割協議において不適切な行為があった場合、協議が無効になるだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあります。
このように遺産分割協議が無効と判断されてしまうと、相続手続きは停滞し、遺産分割ができない状態に陥ってしまうリスクが生じます。
預貯金の解約や不動産の売却ができない
故人の預貯金解約や不動産売却には、原則として相続人全員の同意が必要です。特に預貯金については、以前は相続分に応じて当然に分割されると考えられていましたが、最高裁判例の変更により、遺産分割協議の対象となることが明確化されました。このため、相続人全員の合意がなければ、金融機関は払い戻しに応じないのが実務上の対応となっています。
認知症の相続人がいる場合、認知症の程度によっては、法律行為に必要な意思能力が欠けていると判断されれば、このような同意を得ることができません。結果として、故人の銀行口座を解約したり、あるいは空き家となった実家を売却して現金化できないといった問題が発生します。
このような状況では、相続財産が「塩漬け」状態となり、相続税の納税資金を確保するのが困難になるばかりか、不動産であれば固定資産税や維持管理費がかさむばかりというリスクが生じます。
相続放棄など本人の意思が必要な手続きが不可能に
相続放棄は、故人に借金などの負の財産がある場合に、それらを引き継がないための重要な手続きです。しかし、相続放棄は、相続人自らが「相続しない」と明確に意思表示することが不可欠な法律行為です。
認知症により意思能力(判断能力)が不十分だと判断されると、この意思表示は有効と認められなくなります。具体的には、相続財産の内容を把握し、誰がどの遺産を取得するのかを認知、判断する能力がなければ、相続放棄の意思表示を有効に行うことができないとされます。
もし相続放棄ができない場合、故人に多額の借金があったとすれば、認知症の相続人がその負債を背負うという深刻な事態になりかねません。また、プラスの財産の範囲内で負の財産を相続する「限定承認」のような、本人の意思表示を必要とする手続きも同様に進めることができません。


【相続発生後】認知症の相続人がいる場合の対処法「成年後見制度」

相続人の中に認知症の方がいる場合、有効な遺産分割協議を進めることは困難であり、預貯金の解約、不動産の売却、相続放棄といった相続手続きも滞ってしまいます。このような状況を法的に解決し、停滞した相続手続きを前に進めるための手段が「成年後見制度」です。
以下は、この成年後見制度の具体的な手続きの流れや、利用する際の注意点について詳しく解説します。
成年後見制度とは?家庭裁判所が代理人を選任する仕組み
成年後見制度は、認知症などで判断能力が著しく低減している人の財産や権利を法的に保護し、支援するための公的な制度です。成年後見制度では、家庭裁判所が「成年後見人」を選任し、ご本人(被後見人)の代理人として、遺産分割協議への参加や財産管理といった法律行為を行います。
成年後見人の職務は、主に「財産管理」と「身上監護」の2つに大別されます。それぞれの内容は以下の通りです。
| 区分 | 概要および具体例 |
| 財産管理 | 預貯金の管理や不動産の売却など、本人の財産を守り適切に管理する業務です。 |
| 身上監護 | 生活、医療、介護に関する契約手続きなど、本人の生活に関わる事項を適切に進める役割を担います。 |
後見人には、親族を候補者として申し立てることも可能です。しかし、家庭裁判所はご本人の利益を最優先し、公正な立場から最も適任と判断される者を選任します。そのため、弁護士や司法書士といった法律専門家が選任されるケースも少なくありません。特に、被後見人に大きな資産があるような場合には、たとえ親族を後見人候補者として推薦しても、弁護士や司法書士が後見人に選任されることがあります。
知っておくべき成年後見制度の注意点
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護するための重要な仕組みですが、利用に際してはいくつかの注意点があります。
まず、後見人は家庭裁判所が選任するため、申立て時に親族を候補者として挙げても、必ずしもその親族が選任されるとは限りません。本人の利益を最優先するため、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に就くケースが多くあります。専門家が後見人に選任された場合、被後見人の財産から継続的な報酬が発生します。その報酬額は、管理する財産額に応じて計算されます。
また、成年後見人の役割は、本人の財産を保全し、本人にとって不利益が生じないよう管理することです。そのため、積極的な資産運用、相続税対策を目的とした生前贈与、不動産の売買・投資といった、財産管理は原則として行えません。その上、一度後見開始されると、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで、原則として任意に成年後見を終了させることはできません。
既に成年後見人が就任している場合
被相続人が亡くなり相続が開始された時点で、既に法定相続人に成年後見人が就いているケースもあります。この場合には、新たに成年後見の申立てをする必要はありません。既に就任している成年後見人が相続人の法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
特別代理人の選任が必要となることも
ただ、成年後見人も、被後見人と同様に相続人である場合には、特別代理人の選任が必要となります。
成年後見人も相続人である場合、成年被後見人と利益相反してしまい、成年後見人として本人の利益を十分に守ることができないと考えられます。この場合には、特別代理人の選任申立てを家庭裁判所にすることになります。ただ、後見人の他に後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が後見人に代わって代理することになります。
成年後見制度を使わない選択肢と、それに伴うリスク

以下では、成年後見制度を使わずに相続を進める場合に想定される具体的なリスクについて、詳しく解説していきます。
法定相続分での相続|不動産が共有名義になる問題とは
成年後見制度を利用しない状況でも、不動産を法定相続分で相続登記することは可能です。法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をしなくても相続登記することが認められています。ただし、この場合、不動産は相続人全員の「共有名義」となります。
しかし、不動産が共有名義になると、その後の活用や処分は非常に困難になります。売却、賃貸、あるいは担保設定といった重要な法律行為には、共有者全員の同意が不可欠だからです。
もし共有者の中に認知症の方がいらっしゃると、意思能力が不十分なため、同意を得ることが難しくなります。その結果、不動産は事実上「塩漬け」状態となり、不動産の管理や売却ができなくなるリスクが生じます。
さらに、共有状態のまま次の相続が発生すると、共有者は年を追うごとに増加し、権利関係は一層複雑化します。これにより、将来的に問題を解決することはますます困難になり、親族間のトラブルに発展する可能性もあります。
預貯金の解約と預金の仮払い制度
相続人の1人が認知症により意思能力を欠いている場合には、遺産分割を成立させることができないため、遺産である預貯金を引き継ぐこともできません。
その上、遺産分割協議をせずに棚上げにして、預貯金口座にかかる相続手続を放置すると、10年間の経過により休眠口座になってしまいます。休眠口座になっても預金の相続手続はできますが、口座履歴が取れなくなったり、手続に時間を要してしまうこともあります。
ただ、相続人に重度の認知症の人がいても、預貯金の一定額であれば、遺産分割をせずに引き出すことが認められています(預貯金仮払制度)。引き出せる預金額は以下のうち少額の金額となります。
- 死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
- 150万円
金融機関ごとに計算されるため、複数の預金口座を開設している場合には、その分引き出せる預金額は増えることになります。
相続税の申告で不利になるケースも
遺産分割協議がまとまらない「未分割」の状態で相続税を申告すると、税額を大幅に軽減できる複数の特例が適用されず、結果として納税額が高額になる可能性があります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期間内に遺産分割が完了していないと、税制上の優遇措置を受けられない可能性があるのです。
特に影響が大きいのは、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」と「小規模宅地等の特例」の二つです。配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないという重要な制度です。しかし、この特例は原則として、申告期限までに遺産分割が確定していないと適用できません。
また、被相続人の自宅などの土地評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」も、誰がその土地を相続するかが決まっていなければ適用が認められません。これらの特例が適用できない場合、本来であれば納める必要のなかった多額の相続税が発生し、納税資金の確保に困窮する可能性が出てきます。遺産分割の遅れは、税負担の増大という形で家計に重くのしかかるため、問題を放置せず、早期の対策を講じることが重要です。
元気なうちに遺言書を書いておく
成年後見制度には複数の注意点があり、一度利用を開始すると原則として本人が亡くなるまで終了できないことや、柔軟な財産管理が難しいという側面があります。
そこで重要になるのが、相続開始前の生前対策です。
遺言書は、ご本人の意思を明確に残すことができる、最も強力な生前対策の一つです。この書面があれば、相続人全員による遺産分割協議が不要となり、認知症の相続人がいる場合でも、本人の意思能力が問われることなく手続きを進められる点が、大きなメリットです。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二種類があります。法的な不備による無効のリスクが低く、最も確実なのは公証人が作成する「公正証書遺言」です。
それぞれの概要と費用は以下のとおりです。
| 遺言書の種類と費用の目安 |
| 自筆証書遺言:本人が自筆で作成します。費用を抑えられますが、法的な不備により無効となるリスクがあります。 |
| 公正証書遺言:公証人が作成するため、法的な確実性が非常に高いです。 ご自身で手続きを進める場合:10万円~15万円程度 専門家へ依頼する場合:20万円~50万円程度 |
ただし、遺言書は、遺言者に「遺言能力」がある、すなわち遺言を作成できる判断能力が明確なうちに作成する必要があります。認知症が進行してからでは、遺言が無効と判断される可能性があり、早期の準備が不可欠です。また、他の相続人の遺留分を侵害する内容にしてしまうと、かえってトラブルの原因となる恐れがあります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家と相談しながら、慎重に作成することをおすすめします。
被相続人(亡くなった方)が認知症だった場合はどうなる?
これまで、相続人が認知症を患っている場合に生じる問題とその対策について解説しました。ここでは、被相続人(亡くなった方)が認知症だった場合について焦点を当てます。
被相続人が生前に作成した遺言書、生前贈与などが相続トラブルの原因となるケースは少なくありません。特に、それらの行為が、被相続人の認知症により無効とならないかが争点となることは珍しくありません。
被相続人が亡くなる前に作成した遺言書は、その有効性が争点となることがあります。遺言が法的に有効と認められるためには、遺言作成時に本人が「遺言能力」、つまり遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力を備えている必要があります。認知症が進行し、遺言能力がないと判断される状態で作成された遺言は、後日、他の相続人から無効を主張され、裁判で遺言無効が認められる可能性があります。
遺言書以外の法律行為についても、同様の問題が発生するリスクがあります。例えば、被相続人が認知症に罹患している状態で、特定の相続人へ生前贈与した場合や不動産の売買契約を締結した場合などがこれに該当します。これらの契約も、契約当事者である被相続人が行為当時「意思能力」を欠いていたと判断された場合、法律上無効となる可能性があります。
相続人が認知症の場合のよくある質問
以下では、認知症の相続人がいるケースで、よく寄せられる質問について、Q&A形式で一つずつ丁寧にお答えしていきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、より深い理解と具体的な解決策を見つけるための一助として、ぜひご活用ください。
認知症の症状が軽ければ、遺産分割協議はできますか?
相続人が高齢であれば、症状の程度に差はありますが、認知症を患っていることは珍しくありません。認知症に罹患していれば常に意思能力がないと判断されるわけではありません。
認知症に罹患していたとしても、遺産分割をすることができるだけの判断能力を持ち合わせていることも多くあるからです。
また、相続人が要介護認定を受けていたとしても、それだけで意思能力が否定されるわけでもありません。要介護認定には1~5段階まであり、その上、要介護は認知機能だけでなく身体機能の低下により認定されることもあるため、要介護認定を受けている事情だけで意思能力がないと単純に判断することもできません。逆に、要介護認定を受けていなくても、意思能力を欠いているケースもあります。
成年後見人には、家族や親族がなれるのでしょうか?
成年後見人には、ご家族や親族が就任することも可能です。しかし、最終的に誰が成年後見人に選任されるかは、ご本人の利益を最優先する観点から、家庭裁判所が決定します。そのため、申立ての際に希望した候補者が必ず選ばれるとは限りません。
一般的に、成年後見人が選任されるケースは、状況によって異なります。
①親族が選任されやすいケース
・管理すべき財産が比較的少なく、その管理が単純である場合
・親族間で財産を巡る争いがなく、協力体制が整っている場合
②専門家(弁護士や司法書士など)が選任される傾向にあるケース
・管理財産が多い場合
・不動産の売却など複雑な手続きが見込まれる場合
・親族間で利害の対立がある場合
これは、財産の不正利用を防ぎ、中立な立場で公正な財産管理を行うためです。
近年では、親族以外の弁護士等が成年後見人等に選任される割合が大幅に増加しています。
相続手続きで困ったときは誰に相談すればいいですか?
相続手続きで困った際、どこに相談すれば良いか迷われる方も少なくありません。抱えている問題に応じて、適切な専門家を選ぶことが、解決への近道となります。
相続トラブルの予防や解決、成年後見制度の申し立て、遺産分割協議といった法的な手続き全般については、弁護士が専門家です。弁護士は複雑な法律問題を扱い、最適な解決策を提案してくれます。
一方、相続税の申告や、土地・建物の評価など、税金に関する事柄で悩んでいる場合は、税理士に相談するのが適切です。税務の専門知識に基づき、正確な申告をサポートしてくれるでしょう。
遺産分割協議の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、相続人に認知症の方がいる場合に起こりうる問題と、その具体的な対処法について解説いたしました。
意思能力を欠く状態では遺産分割協議が進められず無効になってしまうこと、また、故人の預貯金解約や不動産の売却、さらには相続放棄といった重要な手続きも不可能になるリスクをご理解いただけたことと存じます。
相続発生後に直面するこれらの問題に対し、法的な対処法の一つとして成年後見制度がありますが、これは費用負担や財産管理において制約がある面も持ち合わせています。
相続は、家族にとって、精神的にも肉体的にも大きな負担となる可能性があります。特に、認知症の相続人がいる場合は、その複雑さが増し、問題解決に時間と労力を要するケースも少なくありません。ご家族だけで悩みを抱え込まず、状況に応じて弁護士に相談することが、円満な相続を実現するための近道となります。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。