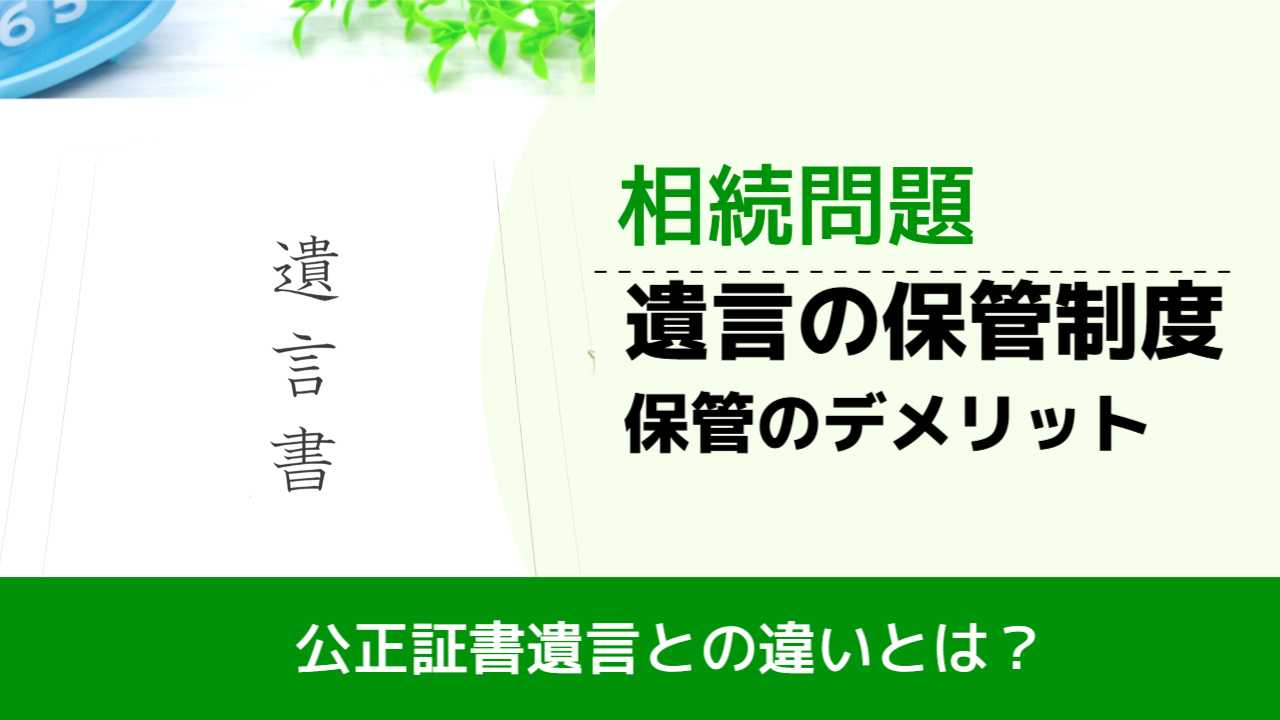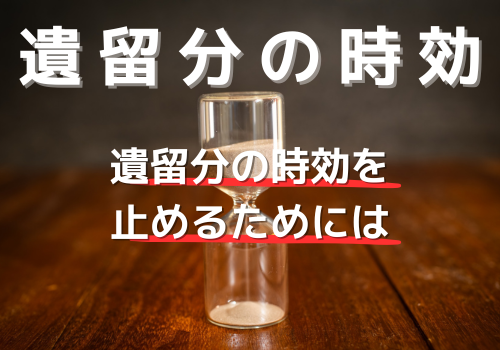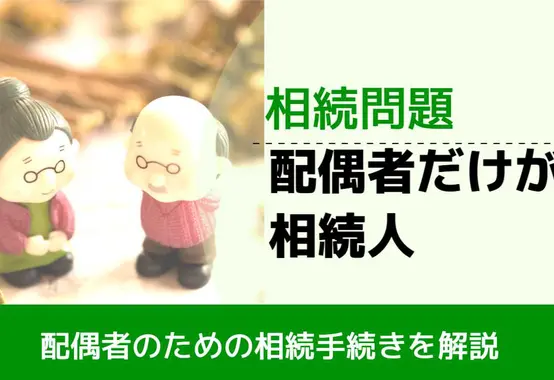自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言方法として知られています。しかし、せっかく作成した遺言書も、保管方法を間違えてしまうと、紛失したり、死後に発見されなかったりなど、期待された役割を果たすことができません。そこで活用したいのが、法務局における保管制度です。
この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らせますが、デメリットがないわけではありません。本記事では、自筆証書遺言を法務局に預ける際の注意点や、制度の落とし穴について詳しく解説します。賢く制度を利用するための情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
まずはおさらい!自筆証書遺言の法務局保管制度とは?
まず、自筆証書遺言の法務局保管制度の概要について確認しましょう。
以下では、法務局の遺言書保管制度と従来の自宅保管との具体的な違いについて詳しく解説していきます。
自宅で保管する従来の自筆証書遺言との違い
自宅で保管する自筆証書遺言と、法務局保管制度を利用した場合では、「保管の安全性」「相続開始後の手続き」「作成時の形式チェック」という3つの点で大きな違いがあります。
・「保管の安全性」
・「相続開始後の手続き」
・「作成時の形式チェック」
まず、「保管の安全性」です。自宅保管の遺言書は、紛失や改ざん、隠匿のリスクが常に伴います。しかし、法務局保管制度では原本が法務局に安全に預けられるため、これらの心配がなくなります。
次に、相続開始後の「手続き」における違いです。自宅保管の遺言書は、相続発生後に家庭裁判所での「検認」手続きが必須となります。これは、遺言書の偽造や変造を防ぐための大切な手続きですが、相続人にとっては時間と手間がかかる負担です。一方で、法務局保管制度を利用した遺言書は、この検認が不要となるため、相続開始後の手続きが大幅に簡素化されます。
また、作成時の「形式チェック」も重要なポイントです。自宅で作成・保管する自筆証書遺言は、法的要件の確認が不十分となり、形式不備で無効になるリスクがあります。一方、法務局保管制度では、遺言書の「作成日付の有無」,「遺言者の氏名」,「押印の有無」,「本文は自書であるか否か」等の形式的な要件を確認するため、形式不備を避けることができます。ただ、あくまでも形式的な要件の確認のみであり、内容の正当性まで保証されるものではないことは留意するべきです。
法務局が遺言書を安全に預かってくれる公的なサービス
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の保管に関する不安を解消するための公的なサービスです。この制度は、2020年7月10日から全国の法務局で運用が開始されました。その主な目的は、自身で作成した遺言書が将来的に紛失したり、第三者による改ざんを受けたり、あるいは意図的に隠匿されたりするリスクを根本から防ぐことにあります。
法務局は、遺言書を単に預かるだけでなく、その原本を厳重に保管します。さらに、その内容は画像データとしても保存され、原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間という長期にわたり厳正に管理されます。これにより、遺言書が確実に保存され、必要な時にその存在が明らかになる信頼性の高い仕組みが構築されます。この制度は、遺言者自身の意思を未来へ確実に伝えるための重要な選択肢となるでしょう。


【本題】知っておくべき法務局保管制度の5つのデメリット
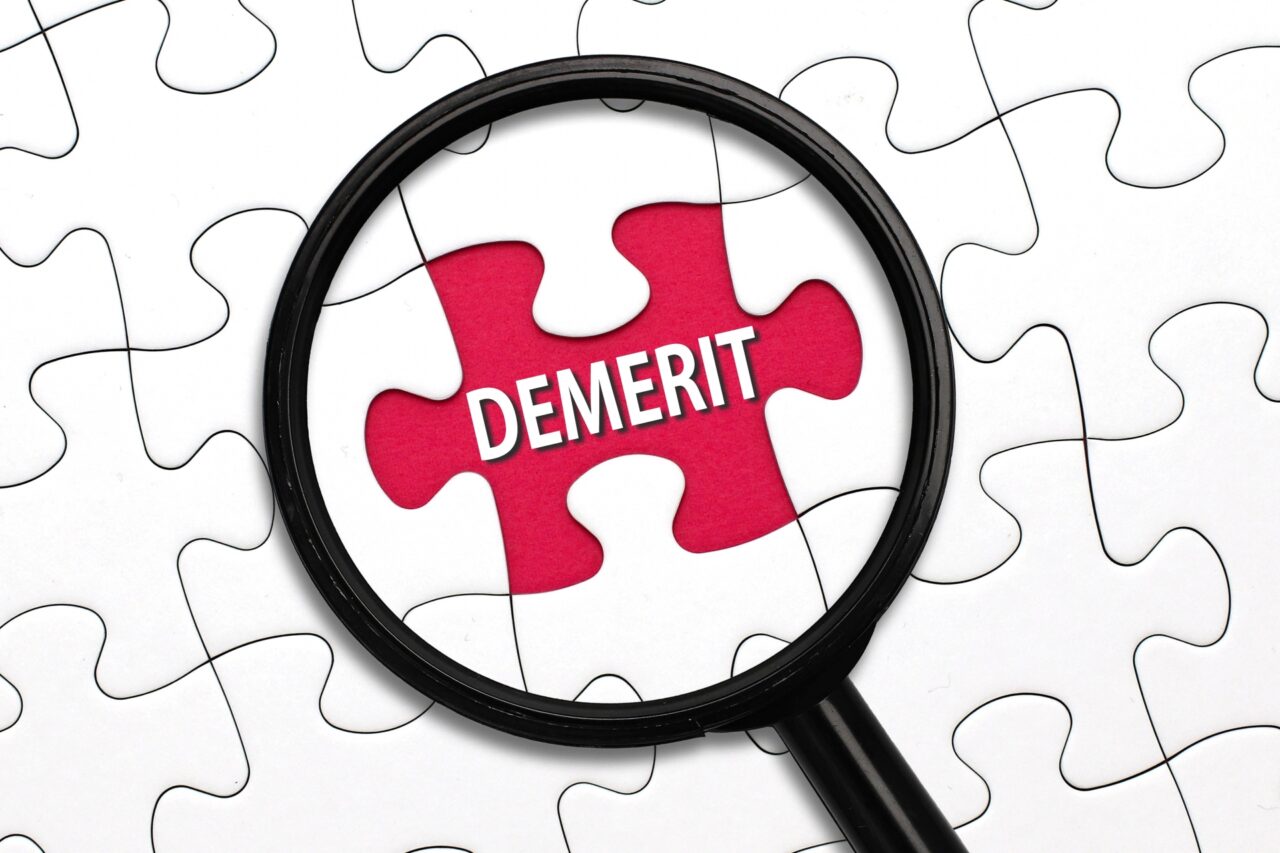
自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言書の確実な保管や相続手続きの簡素化など、多くの利点を持つ画期的な仕組みです。一方で、利用者が事前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。
以下では、特に重要な5つのデメリットについて詳しく解説します。
デメリット1:遺言の内容が有効かどうかは保証されない
自筆証書遺言を法務局に保管する際、多くの方が遺言内容の有効性が保証されると誤解しがちです。しかし、法務局の役割は、民法で定められた遺言書の形式要件、すなわち日付、署名、押印などが適切に記載されているかを確認し、その原本を安全に保管することに限定されます。
遺言書に書かれた内容が、民法に照らして有効か、あるいは実現可能であるかといった「内容」の審査は一切行われません。例えば、不明瞭な内容の記載であれば、遺言書の意思が判然としないため遺言執行することができません。法務局は遺言書の内容に関する相談に応じることができないため、内容の適法性や有効性まで踏み込んだ確認はしてもらえません。
このため、遺言書の内容に法的な不備があった場合、たとえ法務局で保管されていても、遺言者の死後に遺言が無効と判断されたり、相続人同士で争いが起きたりするリスクは残ります。実際に、遺言能力の欠如や記載の不明確さなどにより、遺言が無効とされたケースも存在します。
デメリット2:申請は必ず本人が法務局に出向く必要がある
自筆証書遺言を法務局に保管申請する際、注意すべき点の一つは、遺言者本人が法務局へ直接出向く必要があることです。この制度では、代理人による申請や郵送での申請は一切認められていません。これは、なりすましといった不正行為を防ぐため、法務局の職員が厳格な本人確認を行う必要があるためです。
この点は、特に高齢者の方や、病気、身体的な理由により外出が難しい方々にとって、大きな負担となり得ます。法務局まで移動する身体的な負担だけでなく、手続きの準備や心理的なハードルも生じるでしょう。その結果、制度の利用自体を諦めてしまうケースも少なくありません。
一方で、公正証書遺言の場合、遺言者の状況に応じて、公証人が病院や自宅へ出張し、遺言書を作成してくれる制度もあります。そのため、移動が困難な状況にある場合は、自筆証書遺言の法務局保管制度よりも、公正証書遺言の作成を検討する方が適しているかもしれません。
デメリット3:住所や氏名が変わった際の変更手続きが面倒
自筆証書遺言を法務局に保管した後、遺言者の住所、氏名、本籍などに変更が生じた場合は、速やかに法務局へ「変更の届出」をする必要があります。
この変更手続きは、遺言書を保管申請した時と同様に、原則として遺言者本人が法務局に出向く必要があります。また、変更の事実を証明する公的書類の準備も求められます。ただ、郵送による変更も可能とされています。
転居や結婚といったライフステージの変化があるたびにこれらの手続きが必要となるため、場合によっては大きな負担となることがあります。
デメリット4:遺言の撤回や内容変更には再度手続きが必要になる
自筆証書遺言は遺言者の意思を反映するものであり、状況の変化に応じて内容を変更したり、撤回したりする可能性があります。
過去の遺言を預けたまま、新たな遺言書の保管申請をすることも可能ですが、複数の遺言が保管されることになり混乱を招きかねません。そのため、遺言の内容を変更したい場合は、現在保管されている遺言書の「保管申請の撤回」手続きを行い、遺言書を返還してもらうことが望ましいです。その後、新たに作成した遺言書を再び法務局に「保管申請」するといった一連の手続きを最初からやり直します。
この「保管申請の撤回」をするためには、遺言書原本を保管する法務局で予約をした上で、遺言者本人が撤回書を提出するといった手間がかかります。このように、遺言書の内容を変更したり、保管を取りやめたりする際には、それなりの手間と時間がかかる点を理解しておくことが重要です。
デメリット5:費用がかかる
法務局に遺言書を保管しなければ、遺言書の保管費用はかかりません。一方で自筆証書遺言を法務局に預けると、一件につき3900円の手数料が発生します。また、保管後の保管申請の撤回、遺言書原本の閲覧、にも1700円ほどの費用が発生します。
そのため、保管制度を利用することで多少の費用負担が生じます。ただ、それほど大きな経済的な負担ではありませんので、保管によるメリットを踏まえると、大きなデメリットとまでは言えないでしょう。
デメリットだけじゃない!法務局保管制度の4つの大きなメリット
ここまで、自筆証書遺言の法務局保管制度におけるデメリットについて解説してきました。しかし、この制度は従来の自筆証書遺言が抱えていた問題を解消し、それを上回る大きなメリットがあります。
メリット1:紛失・改ざん・隠匿のリスクがなくなる
自筆証書遺言を自宅で保管する場合、紛失のリスクが常につきまといます。どこに置いたか忘れてしまったり、火災や地震といった災害で焼失したりする可能性も考えられます。実際に、遺言書が見つからないという事例も多く見受けられます。また、特定の相続人が自分に有利になるよう内容を改ざんしたり、あるいは不利な内容の遺言書を隠匿・破棄したりするリスクも無視できません。遺言書の偽造や改ざんが行われるケースは、自筆証書遺言で発生しているのが実情です。
法務局の保管制度を利用すれば、これらのリスクを根本から解消することが可能です。法務局が遺言書の原本と画像データを厳重に管理するため、物理的な紛失や災害による焼失を防ぐことができます。また、公的な機関が保管するため、相続人による改ざんや隠匿、破棄を未然に防ぐことが可能です。これにより、遺言者の最終的な意思が確実に守られ、相続を巡る無用なトラブルの発生を防ぎ、円滑な相続手続きへとつながるという、本質的なメリットが得られます。
メリット2:相続人の負担になる「検認」が不要に
自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、遺言者の死後、その遺言書を開封する前に、家庭裁判所での「検認」手続きが法律で義務付けられています。この検認は、遺言書の偽造や変造を防ぎ、その形状や内容を明確にするための重要な手続きです。しかし、相続人にとっては一定程度の負担となる側面があります。
検認手続きを進めるには、まず家庭裁判所に申立てを行い、必要な戸籍謄本などの書類を収集しなければなりません。その後、相続人全員に裁判所から遺言書の存在が通知され、全員が検認期日に裁判所へ出向く必要があります。これらの手続きは、相続開始後の多忙な時期に、相続人の時間的、精神的な負担となりがちです。
一方で、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、この検認手続きは法律上不要となります。法務局が遺言書の原本を厳重に保管し、かつ形式的な要件を確認しているため、従来の検認の目的が果たされているとみなされるためです。
検認が不要となることで、相続人の手間と時間が削減されます。これにより、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続開始後のさまざまな手続きを迅速に進めることが可能となり、相続人の時間的、精神的な負担を軽減できる大きなメリットとなります。
メリット3:公正証書遺言に比べて費用を抑えられる
自筆証書遺言を法務局に保管する制度は、費用面で大きなメリットがあります。保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円と定額で、一度支払えばそれ以降の保管料はかかりません。作成時にのみ費用が発生するため、長期にわたる保管費用を気にせず利用できる点が魅力です。
一方、公正証書遺言の作成費用は、遺言の対象となる相続財産の価額に応じて変動します。主な公証人手数料は以下の通りです。
| 相続財産価額 | 公証人手数料 |
| 100万円未満 | 5,000円 |
| 200万円超500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円~3,000万円 | 23,000円 |
また、財産総額が大きくなるほど手数料も高くなり、数万円から数十万円程度かかる場合も珍しくありません。さらに、病気などの理由で公証人に出張を依頼する場合、手数料が増えることもあります。
このように、相続財産額が多いほど、法務局保管制度は公正証書遺言と比べて費用を大幅に抑えられるメリットがあります。
メリット4:死後、相続人に遺言書の存在が通知され発見漏れがない
自筆証書遺言を法務局に保管する大きなメリットの一つに、遺言者の死亡後にその存在が関係者に通知される「死亡時通知制度」があります。これは、遺言者本人が亡くなった際、事前に指定した人に対し、法務局から遺言書が保管されている旨を通知するものです。
この通知制度により、従来の自宅保管でしばしば発生していた「遺言書が見つからない」「一部の相続人に隠匿されてしまう」といったトラブルを未然に防ぐことが可能になります。遺言者の意思が確実に相続人に伝わり、故人の願いが実現されやすくなるでしょう。
さらに、死亡時通知の対象者として指定されなかった他の法定相続人等にも、誰かが遺言書情報証明書の発行を請求したり、遺言書を閲覧したりした際には、後日法務局から関係遺言書保管通知が発せられる仕組みです。
これにより、遺言書の存在が広く関係者に知らされるため、遺言が執行されないリスクを大幅に減らせます。
結局どちらを選ぶ?法務局保管と公正証書遺言を徹底比較
法務局保管制度のメリット・デメリットを理解された上で、自筆証書遺言の法務局保管と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか迷われている方もいらっしゃるかもしれません。以下では、公正証書遺言との比較について詳しく解説します。
「費用」で比較|手数料はどれくらい違う?
自筆証書遺言の法務局保管制度と公正証書遺言を比較する上で、費用は重要な検討材料の一つです。法務局保管制度にかかる費用は、遺言書1通あたり一律3,900円の保管手数料のみと定められています。
一方、公正証書遺言の作成費用は、遺言の対象となる相続財産の価額に応じて変動する公証人手数料が基本です。さらに、公正証書遺言では、基本手数料のほかに、遺言加算、証人の日当、遺言書の謄本代といった追加費用が発生する可能性があります。また、遺言者が病気などの理由で公証役場に出向けず、公証人に出張を依頼する場合は、手数料が増額することもあります。
したがって、遺言書作成と保管にかかる費用を可能な限り抑えたいと考える方にとっては、法務局保管制度が有利な選択肢であると言えるでしょう。
| 項目 | 法務局保管制度の費用 | 公正証書遺言の費用 |
| 基本料金 | 遺言書1通あたり一律3,900円(保管手数料のみ) | 相続財産の価額に応じて変動する公証人手数料(例:100万円未満で5,000円) |
| 追加料金 | なし | 遺言加算、証人の日当、遺言書の謄本代など |
| 出張の場合 | なし | 公証人への出張依頼で手数料が1.5倍となる可能性あり |
| その他 | 申請時に一度支払えばそれ以降の保管料は不要 | 一般的な目安は10万円から15万円程度(ご自身で手続きの場合) |
「確実性」と「手間」で比較|あなたに合うのはどっち?
遺言書作成の「確実性」と「手間」は、遺言方法を選ぶ上で特に重要な要素です。まず確実性の面では、自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言書の形式的な要件(日付、署名、押印など)を確認するにとどまります。遺言内容が法的に有効であるかまでは担保されないため、内容に不備があれば、たとえ保管されていても無効になったり、相続争いの原因となったりするリスクが残る点は理解しておく必要があります。
一方、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者と面談し、遺言能力の確認や、内容が法的に有効であるかを精査しながら作成します。これにより遺言が無効になるリスクは極めて低いと言えるでしょう。
次に作成の「手間」について比較してみましょう。法務局保管制度を利用する場合、遺言書の本文だけでなく、保管申請書なども全てご自身で作成し、必要書類を揃えて本人が直接法務局へ出向く必要があります。これには相応の時間と労力がかかります。一方、公正証書遺言は、公証人との打ち合わせは必要ですが、遺言書自体は公証人が作成してくれるため、遺言者自身の作成負担は軽減されます。また、遺言者が病気などで公証役場に出向けない場合は、公証人が自宅や病院へ出張して作成してくれるため、身体的な負担も少ないと言えます。
これらの比較から、遺言内容の法的な確実性を最優先し、将来的な相続トラブルを最大限避けたい場合は公正証書遺言が適しています。一方で、費用を抑えることを重視し、ご自身で手続きを進める手間を厭わない方には、自筆証書遺言の法務局保管制度が向いているでしょう。
| 項目 | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
| 費用 | 3,900円 | 財産額に応じて変動 |
| 作成の手間 | 本人出頭必須 | 公証人出張も可能 |
| 法的な確実性 | 形式確認のみ | 公証人関与により確実 |
| 死後の手続き | 検認不要、通知あり | 検認不要、通知なし |
法務局保管制度を利用する流れと必要書類・費用
自筆証書遺言を法務局へ保管申請をする際には、いくつかのステップと準備が必要です。ここでは、遺言書の作成から申請完了までの具体的な流れを、必要書類や費用と合わせて解説します。手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひご参照ください。
STEP1:遺言書と申請書を作成する
自筆証書遺言を法務局へ保管する最初のステップは、遺言書本体と保管申請書を作成することです。遺言書は、民法で定められた厳格な形式要件を満たす必要があります。具体的には、以下の項目を遺言者自身が自筆し、押印することが必須とされています。
- 遺言書の全文
- 日付
- 氏名
また、法務局での保管制度を利用する場合、用紙のサイズや余白にも指定があります。用紙はA4サイズを使用し、上下左右にそれぞれ上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する必要があります。財産目録については例外的にパソコンなどで作成することが認められていますが、この場合は財産目録の全てのページに遺言者の署名と押印が必要です。
遺言書とは別に、「遺言書保管申請書」を作成する必要もあります。この申請書の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードでき、ご自宅のパソコンで作成したり、手書きで記入したりすることが可能です。各種書類を不備なく作成することが、その後の手続きをスムーズに進めるための大切な準備となります。
STEP2:法務局を選んでオンラインで予約する
自筆証書遺言を法務局へ保管申請する際は、まず申請先の法務局を決め、事前に予約をする必要があります。申請可能な法務局は、以下のいずれかの場所を管轄する法務局の中から、ご自身の都合の良い場所を選べます。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
法務局での手続きは、必ず事前の予約が必要です。予約は、法務省が提供する「法務局手続案内予約サービス」を利用したオンライン予約が基本となります。オンラインでの操作が難しい場合は、直接、希望する法務局へ電話または窓口で予約することも可能です。
| 書類・持ち物 | 備考 |
| ご自身で作成した遺言書 | 封をせずに持参、ホッチキス止めも不要 |
| 遺言書保管申請書 | |
| 本籍の記載がある住民票の原本 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの公的書類 |
| 手数料分の収入印紙 |
STEP3:必要書類を揃えて法務局で申請する
事前の予約が完了次第、指定された日時に遺言者本人が必要書類を持参の上、法務局へ出向き、申請手続きを行います。自筆証書遺言の保管申請は、代理人や郵送による手続きが認められていません。そのため、遺言者ご本人が必ず来庁する必要がある点にご注意ください。
申請当日に持参する主な書類や持ち物は以下の通りです。
法務局の窓口では、まず職員が遺言書の外形的な形式(日付、署名、押印など)に不備がないかを確認します。その後、本人確認が行われ、持参した収入印紙によって手数料を納付します。全ての確認と手続きが滞りなく完了すると、遺言書が保管されたことを証明する「保管証」が交付され、一連の手続きは終了します。
| 手続き内容 | 費用(1回または1通につき) |
| 遺言書のモニター閲覧 | 1,400円 |
| 遺言書の原本閲覧 | 1,700円 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1,400円 |
必要となる費用は申請手数料の3,900円のみ
自筆証書遺言を法務局に保管する際にかかる費用は、遺言書1通につき申請手数料の3,900円のみです。この手数料は、申請時に法務局の窓口で収入印紙を購入して納付します。収入印紙は、法務局の庁舎内や郵便局などで購入できます。
ただし、申請手数料以外にも、状況に応じて別途費用が発生するケースがあります。
| 法務局保管制度が保証する内容 | 法務局保管制度が保証しない内容 |
| 遺言書の形式が民法ルールに準拠しているか | 遺言書の内容の法的有効性 |
| 遺言書の安全な保管 | 相続トラブル発生のリスク防止 |
| 遺留分など、相続人の権利侵害の有無 | |
| 財産の記載漏れや曖昧な表現の有無 |
遺言書の内容に不安が残るなら弁護士への相談も検討しよう
自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言書が民法で定められた形式に沿っているかを確認し、安全に保管する公的なサービスです。しかし、遺言書に書かれた内容の法的な有効性や、相続トラブルのリスクまで保証するものではありません。
特に、遺留分など法律で定められた相続人の権利を侵害していないか、財産の記載漏れや曖昧な表現はないかなど、ご自身で作成した遺言書に少しでも不安が残る場合は、弁護士への相談が有効な解決策となるでしょう。
法律の専門家である弁護士に相談することで、法的に不備がなく、ご自身の意思が正確に反映された遺言書を作成できます。弁護士は、遺言内容の解釈に疑義が生じないようサポートします。
| 確認項目 | 法務局の保管制度 | 専門家(弁護士・司法書士) |
| 形式要件(日付、署名、押印など) | 確認します | 確認します |
| 内容の法的有効性 | 保証されません | 精査し、法的有効性を高めます |
| 遺言者の意思能力 | 確認しません | 確認します |
| 遺留分など相続法規への対応 | 確認しません | 踏まえて適法性を精査します |
| 相続トラブル予防のアドバイス | 提供されません | 提供します |
遺言書の作成は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、自筆証書遺言の法務局保管制度について、そのメリットとデメリットを詳しく解説しました。遺言書の保管制度は、ご自身で作成した遺言書を法務局が厳重に保管する公的なサービスです。費用を抑えながらも、従来の自筆証書遺言が抱えていた多くの課題を解決できる点が大きな魅力です。
一方で、デメリットも存在します。最も重要なのは、法務局が遺言書の形式的な要件(日付、署名、押印など)は確認するものの、遺言内容の法的な有効性までは保証されない点です。遺言書の内容に不備があった場合、相続が無効になったり、遺留分を巡るトラブルに発展したりするリスクが残ります。
遺言書の内容や手続きに少しでも不安が残る場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、法律の専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士の知見を活用することで、法的に不備がなく、ご自身の意思が正確に反映された遺言書を作成し、遺されたご家族が安心して相続手続きを進められるようになるでしょう。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。