賃料値上げの通知は、慎重に進める必要があります。
近年、経済状況の変化や修繕費用の増加などを背景に、賃料の見直しを考える大家さんが増えています。しかし、一方的な値上げはトラブルの原因となります。
そこで、正しい知識と準備を持って賃料値上げの交渉に臨むことで、双方にとってより良い結果に繋げることが可能です。
この記事では、賃料値上げのルールを踏まえつつ、具体的な交渉の進め方や、入居者の方に納得してもらうためのポイントを、わかりやすくご紹介します。ぜひ、参考にしてください。
賃料値上げの法的な根拠とは?
賃貸物件の大家さんが賃借人に対して家賃の値上げを求めることは、法律上認められている権利です。
その根拠となるのが、借地借家法に定められている賃料増額請求権です。この権利は、賃貸借契約で定めた賃料が、その後の事情の変化により不相当になった場合に、将来に向かって賃料の増減を請求できるというものです。
この権利は「形成権」とされており、大家さんから賃借人への一方的な意思表示によって法律上の効果が発生します。一方、賃借人には増額請求された賃料額が不相当だと判断した場合に異議を申し立てることができ、その場合は現行賃料を支払い続けることができます(借地借家法第32条第2項)。ただ、増額賃料が確定した場合には、賃借人は賃料増額の請求時から差額の賃料と遅延損害金(年10%)を支払う必要があります。
賃料値上げ、いつ検討すべき?判断基準とタイミング
「いつ」「どのような状況になったら」賃料の値上げを検討すべきなのか、判断に迷う大家さんも多いのではないでしょうか。
賃料値上げのタイミングはいつ?
賃料値上げのタイミングは、法的に定められていません。現在の賃料が不相当になれば、賃料増額請求をすることは認められます。
ただ、賃料の値上げを通知するタイミングとしては賃貸借契約の更新時に合わせて通知をすることが多いでしょう。その他にも、賃料の合意をしてから、長期間が経過している場合や固定資産税等の租税公課が増えた場合も賃料値上げのタイミングとなり得ます。
賃料値上げの理由は何か?
賃料値上げをする理由には様々ありますが、現在の賃料が賃料の合意をしてから長期間が経過していても、現在の賃料が不相当となる理由がなければ賃料増額を求めることはできません。
借地借家法では、以下の賃料値上げの理由が定められており、これらが存在しなければ賃料増額請求は認められないため、注意が必要です。
- 租税その他の負担の増減
- 土地や建物の価格の変動
- 近隣の賃料と比較して不相当になった場合


賃料値上げの通知をする時に押さえるべき注意点
賃貸物件の賃料について、大家さんが値上げを求めることは、法律上認められた権利の一つです。しかし、この権利は無制限ではなく、適切に行使するためには法的に定められた手続きを遵守する必要があります。以下では、貸主様が賃料の値上げを通知する際に、特に押さえておくべき重要な注意点を解説します。
口頭ではなく内容証明等の文書で通知する
賃料の値上げを通知する際は、口頭ではなく書面で行うことが不可欠です。口頭での通知は「言った言わない」のトラブルに発展しやすく、後々の紛争の原因となる可能性が高いからです。通知を行ったという事実やその内容を明確に証明するためにも、必ず書面にて行いましょう。
その上で、賃料値上げの通知方法として望ましいのは、内容証明郵便を利用することです。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰から誰へ送付したかを郵便局が公的に証明してくれるため、法的な証拠能力が非常に高いというメリットがあります。
もちろん、普通郵便や手渡しなど、内容証明郵便以外の書面で通知することも法律上は可能ですが、後日の「通知を受けていない」「内容は違う」といった争いを避けるためには、配達記録が残り、かつ文書の内容が証明される内容証明郵便が最も確実な方法と言えます。
冷静な対応を心がけること
賃料の値上げ通知は、借主にとって受け入れにくいものであり、感情的な反発を招きやすいものであることを十分に理解しておく必要があります。そのため、通知の文面を作成する際はもちろん、実際に借主と顔を合わせてやり取りする際も、高圧的な態度や一方的な物言いは避け、常に丁寧で落ち着いた言葉遣いを心がけましょう。
たとえ借主と意見が対立する状況になったとしても、感情的にならず、物件の評価額の状況、周辺の家賃相場、法的な根拠などに基づいた事実を冷静に提示し、根気強く話し合いを進めることが、円満な解決へと繋がる鍵となります。
賃料増額時期に余裕を持たせること(2~3か月前)
賃料増額を通知する時期について、法律上の明確な定めはありません。そのため、通知をした時点から賃料の増額を求めることは可能です。
しかし、スムーズに手続きを進めるためには、ある程度の時間的な余裕を持つことが大切です。賃料増額までの猶予期間を設けることで、借主は値上げに対する心の準備をし、今後の収支の計画を立てる時間を持つことができます。
また、時間的な余裕を持つことで、借主との間で十分に話し合いの機会を持つことができ、円満な合意に至りやすくなるかもしれません。
そのため、賃料増額の時期を、即時ではなく2〜3か月先とすることも検討しましょう。
賃料増額の理由・根拠を示すこと
賃料の値上げを借主に納得してもらうために、賃料増額が必要な具体的な理由や根拠を明確に伝えることが不可欠です。単に「経営が苦しいから」「物価が上がったから」といった抽象的な説明では、借主の理解や同意を得ることは難しいでしょう。
物件の評価額の推移、固定資産税の増額、近隣の賃料相場の上昇、維持管理費や修繕積立金などの必要経費の増加などの客観的なデータを挙げることが重要です。これらの根拠を示すことで賃貸人の説明に説得力が増します。
あまりにも高額な増額請求はかえって事案を複雑にさせる
あまりにも相場とかけ離れた高額な賃料増額請求は、借主に強い不信感を抱かせ、感情的な対立を生む原因となりかねません。
一度関係性が悪化すると、その後の話し合いは著しく難航し、本来であれば協議により解決できるはずであった事案が、調停や訴訟といった法的な手段に発展するリスクが高まります。調停や訴訟となれば、結果的に、問題解決までに長い時間と労力を要するだけでなく、弁護士費用や裁判上の手続きにかかる費用など、双方にとって大きな負担が生じることになるでしょう。
賃借人からの反論に備えておくこと
賃貸人の賃料増額請求に対し、賃借人は必ずしもその請求通りに応じる義務はありません。借地借家法第32条第2項により、請求された増額賃料が不相当であると考える場合、増額を正当とする判決が確定するまでは、賃借人は自ら相当と認める賃料額を支払っていれば、賃料不払いを理由に契約解除されるリスクを回避できます。
仮に、賃借人と合意できない場合には、民事調停や訴訟といったプロセスを経なければならず、上述したように様々な負担を強いられてしまいます。
そこで、賃貸人としては、これらの賃借人の権利や取り得る手段を事前に理解しておくとともに、賃借人が賃料増額に応じないことをあらかじめ想定した上で、反論できるだけの材料や最大限譲歩できる増額賃料額を検討しておくことが大切です。
借地借家法32条2項
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
賃借人に納得してもらう賃料値上げ通知書の書き方
円満な賃料改定を実現するには、賃借人に向けた「賃料値上げ通知書」の作成が鍵となります。賃借人に納得してもらえる通知書の具体的な書き方や作成ポイントを、例文を交えながら徹底解説していきます。
通知書の基本構成とは
賃料増額請求の通知書は、賃借人へ正確な情報を伝え、理解と協力を得るための最初のステップです。
効果的な通知書を作成するには、いくつかの必須事項を含める必要があり、その内容は以下のとおりです。
- 宛名
- 差出人
- 発送日
- 表題
- 本文
宛名・差出人・日付・表題
まず、書類の冒頭で、誰から誰への通知であるかを明確にするため、賃借人の住所と氏名を宛名として記載します。そして、賃貸人の氏名・名称、住所、連絡先を差出人として明記しましょう。通知書を発送した日付も正確に記載することが重要です。
次に、通知の目的が一目でわかるように、「賃料改定のお願い」や「賃料増額のお願い」といった件名を簡潔に記載します。これにより、賃借人はすぐに通知の内容を把握できます。
宛名・差出人・日付・表題の例文
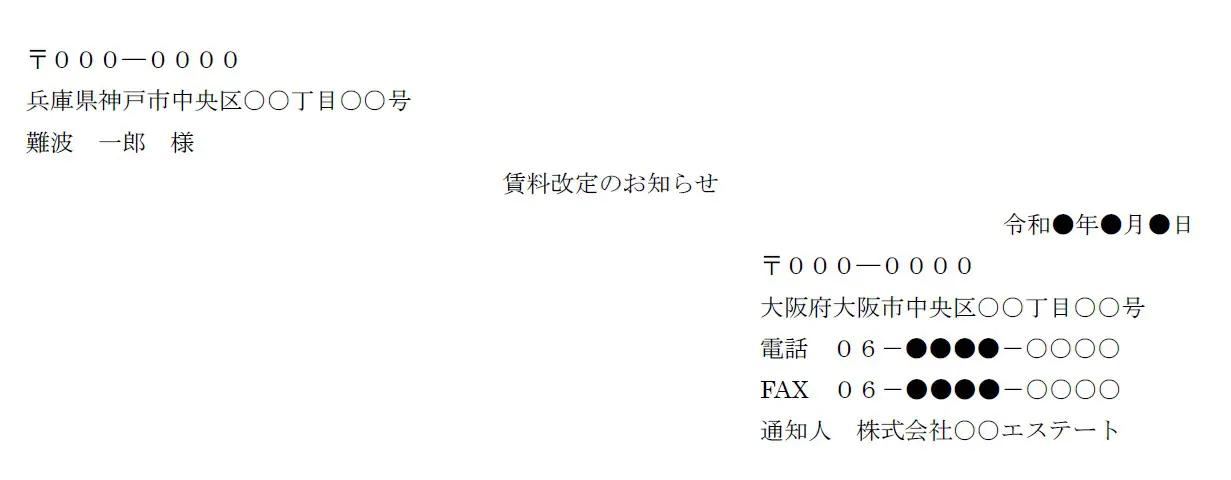
本文に書くべき内容
通知書の本文には、賃料改定に関わる重要な情報を漏れなく記載する必要があります。まず、賃貸借契約の具体的な情報を記載します。契約締結日、合意賃料額、対象物件の情報及び賃料増額に関係する特約を記載します。
その上で、賃料増額を必要とする事情を記載するようにします。なぜ賃料増額を必要とするのかを賃借人ができる限り納得できるように説明するように心がけます。そして、現在の賃料額をいくらに増額するのか、増額賃料がいつから適用されるのかを明記するようにしましょう。賃借人からの回答が必要な場合には、回答期限を設定し、その旨を明記すると丁寧です。協議ができない場合には、調停や訴訟に移行することも示唆しておくことで、賃貸人側の本気度を伝えることも可能となります。
本文の例文
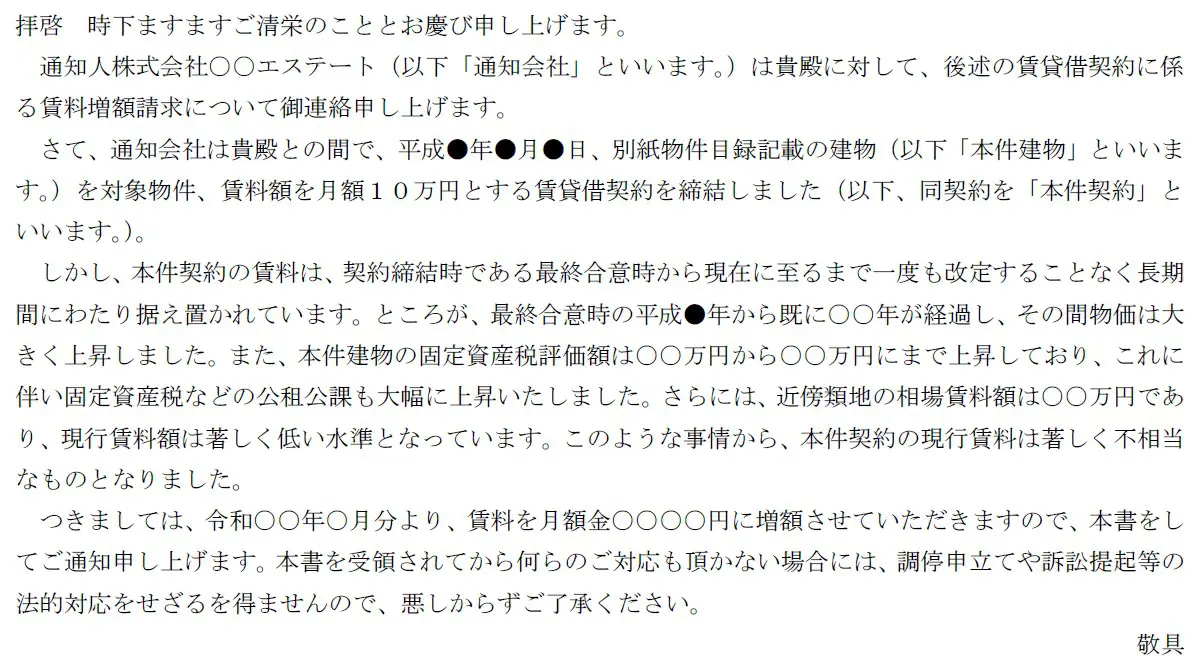
賃料値上げに応じてもらえない時の法的対応
賃料値上げに関する交渉が残念ながら合意に至らなかった場合、賃貸人としては法的な対応を検討せざるを得ません。借主との合意が実現しない場合の取るべき対応を紹介します。
内容証明郵便による再通知
賃料値上げの話し合いがまとまらなかったり、賃借人からの応答が得られない場合、調停手続に移行させる前に、内容証明郵便による再通知を検討します。
内容証明郵便を受け取った賃借人は、賃貸人が法的な手段も視野に入れている可能性を感じ取り、心理的なプレッシャーを受けることが多いと言えます。これにより、無視を続けていた賃借人が交渉に応じたり、賃料改定に向けて何らかの反応を示すきっかけとなる効果が期待できます。特に、初回の賃料増額請求をした際に普通郵便やメールを用いている場合には、内容証明郵便を使用して再通知をすることは効果的といえます。
民事調停(家賃調停)の概要と手続きの流れ
賃料値上げをめぐる話し合いがまとまらない場合、法的な解決手段の一つとして「民事調停」があります。賃料増額請求の場合、いきなり訴訟提起をすることはできず、まず調停手続きを経由させる必要があります(調停前置)。
調停手続は、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が、当事者双方の間に入り、話し合いによる解決を試みる手続です。訴訟とは異なり非公開で行われ、手続きはより柔軟かつ簡易で、費用や期間も訴訟に比べて抑えられる傾向にあります。
調停が開始されると、裁判所から指定された調停期日に出廷し、調停委員会を介して話し合いを行います。調停委員には弁護士や不動産鑑定士といった専門家が選任されることも多く、その上、中立的な立場で当事者双方から意見を聞き、解決に向けた調整や提案を行います。期日を重ねながら、双方が納得できる合意点を見つけることを目指します。
話し合いの結果、合意に至った場合は、その内容を記載した「調停調書」が作成され、確定判決と同じ法的な効力を持つことになります。これにより、合意内容が法的に拘束力を持つため、将来的なトラブルを防止できます。
しかし、何度か話し合いを重ねても合意に至らない場合、調停は「不成立」として終了します。調停が不成立となった場合は、次の法的手段として「訴訟」に進むことを検討することになります。
訴訟による賃料増額請求とその進め方
民事調停でも合意に至らなかった場合、最終的な解決手段として賃料増額請求訴訟を提起することになります。訴訟は、当事者双方からの主張と提出された証拠に基づいて、裁判官が適正賃料を判断する手続きです。訴訟手続きでは、適正賃料額を立証するために、不動産鑑定士による鑑定意見書を証拠として提出することが一般的です。ある程度の審理が尽くされた場合には、裁判官から和解の勧告がなされます。しかし、訴訟手続きを通じても裁判上の和解が成立しない場合には、裁判所が指定する不動産鑑定士による鑑定(公的鑑定)を実施した上で、これに踏まえて裁判官が終局的な判断を示すことになります。
訴訟は一般的に長期化する傾向があり、解決まで1年以上かかるケースも見られます。上記のとおり裁判上の和解が成立しない場合は、最終的に裁判所の判決により適正賃料額が決定され、確定判決には法的な拘束力が生じます。訴訟手続きは複雑なため、必要に応じて弁護士に依頼することも有効な選択肢です。
賃料値上げの通知は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、賃貸物件の賃料値上げを通知する際に、賃貸人が知っておくべき手順、賃借人との円満な交渉を進めるための実践的なテクニックについて詳しく解説しました。
賃料の値上げは、賃貸人にとって収益を確保し、物件の価値を維持していく上で必要な経営判断の一つです。しかし、それを一方的に進めるのではなく、賃借人に値上げの理由を具体的に、かつ丁寧に伝えること、そして誠意あるコミュニケーションを通じて理解と協力を得ることが、賃料増額の合意を成立させる近道となります。
交渉が難航した場合でも、内容証明郵便による再通知や、民事調停、あるいは訴訟といった法的な手段があることを知っておくことは重要ですが、これらの手続きは時間や費用を要し、賃借人との関係を損なう可能性も伴います。
賃料の値上げに困った時は当事務所にご相談ください。



























































































