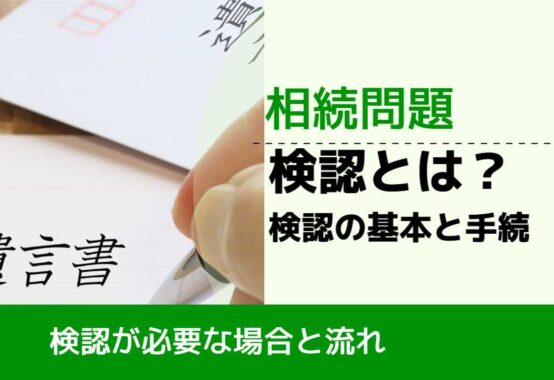相続が発生した際、故人から生前に特別な贈与を受けていた相続人がいる場合、「特別受益」として考慮されることがあります。しかし、この特別受益には時効があるのでしょうか?
特別受益に当たるかもしれないと思われた方は、相続開始から10年の期限に注意が必要です。
この記事では、特別受益の時効について、民法改正の内容もふまえながらわかりやすく解説します。知っておくことで、きっと相続トラブルの解決に役立つはずです。ぜひ最後までお読みください。
【結論】特別受益そのものに時効はない!ただし主張には10年の期限があるので注意
まず結論として、特別受益という概念そのものには、民法上の「消滅時効」のように、一定期間が経過すると権利が失われるといった明確な期限は設けられていません。亡くなった方(被相続人)が特定の相続人に対して生前に行った贈与や遺贈などの「特別な利益」は、時間が経ってもその事実がなくなるわけではないためです。
ただし、特別受益を考慮して遺産を分けること(これを「持ち戻し」と呼び、生前の贈与分を相続財産に加えて具体的相続分を計算します)を、遺産分割協議で主張できる期間には一定の制限があります。それは「相続開始から10年」という期限です。この期限を過ぎてしまうと、特別受益の主張ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
この「相続開始から10年」という期間制限は、2023年4月1日に施行された民法改正(民法第904条の3)によって導入された新しいルールです。改正前は、何十年も前の贈与であっても特別受益として主張できましたが、遺産分割協議が長引いたり複雑になったりするのを防ぐため、この期間制限が導入されました。改正後は、相続開始から10年が経過した後に遺産分割を行う場合、原則として特別受益の主張は認められなくなり、法定相続分に基づいて遺産が分割されることを理解しておく必要があります。
さらに、この新しいルールには経過措置も存在します。2023年4月1日時点で、すでに相続開始から10年が経過していた場合でも、相続開始の時から10年を経過する時または施行日から5年を経過する時のいずれか遅い時までに遺産分割調停や審判の申立てをすれば、特別受益の主張は認められます。


そもそも「特別受益」とは?相続での不公平をなくすための制度
特別受益の時間的な制限を解説する前に、特別受益とはそもそも何か、相続分の計算方法といった基本的な事項を解説します。
特別受益とは何か?
特別受益」とは、亡くなった方(被相続人)が、特定の相続人に対して生前に与えた特別な利益を指します。具体的には、以下のような贈与が特別受益に該当します。
- 遺贈
- 婚姻や養子縁組のための贈与
- 住宅購入資金や開業資金といった生計の資本としての贈与
この制度の目的は、相続人間での公平性を保つことです。特定の相続人が生前に多額の財産を受け取っていたにもかかわらず、それが考慮されずに遺産が分割されると、他の相続人との間で不公平が生じてしまうためです。
特別受益は、いわば遺産の「前渡し」とみなされる性質を持ちます。このような生前の利益を、遺産分割の際に一度相続財産に加算し、それぞれの相続分を再計算する手続きを「持ち戻し」と呼びます。
相続財産に生前の贈与などを足して計算する「持ち戻し」
「持ち戻し」とは、故人が特定の相続人へ生前に行った贈与や遺贈(特別受益)を、相続開始時の財産に足し戻して、相続財産の総額を計算し直す制度です。
この持ち戻し計算によって算出された財産総額は、「みなし相続財産」と呼ばれます。この「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の本来の相続分が算定されます。
最終的な相続分の計算では、特別受益を受けた相続人は、「みなし相続財産」から算出された自身の法定相続分から、すでに受け取った受益額が差し引かれる仕組みです。これにより、特別受益を受けた分だけ、その相続人の実際の取得分が調整され、結果として相続人全員の公平性が図られることになります。
【重要】特別受益と時効の関係性|知っておくべき「10年」という2つの期間
特別受益そのものには時効がありませんが、相続の実務では「10年」という期間が非常に重要な意味を持ちます。
以下の項目で、10年という期間の内容をさらに詳しく見ていきましょう。
原則:遺産分割協議なら何年前の贈与でも主張可能
遺産分割協議で特別受益を主張する場合、原則として「時効」は適用されません。そのため、被相続人が生前に行った贈与が何十年も前のものでも、原則として特別受益の「持ち戻し」を主張できます。例えば、30年前に遡る住宅購入資金の援助なども、対象となることがあります。
ただ、あまりに古い贈与の場合、その事実を客観的に示す証拠(預貯金通帳、贈与契約書、不動産登記など)を確保することが非常に困難になるという現実的な課題があることも理解しておく必要があります。
注意点1:相続開始から10年経過すると主張が制限される(2023年4月法改正)
2023年4月1日に施行された改正民法により、特別受益の主張に関する重要な変更が導入されました。この改正により、相続開始(被相続人が亡くなった時)から10年が経過すると、特別受益の主張が制限されることになりました。
具体的には、相続開始から10年を経過した後に遺産分割を行う場合、原則として法定相続分に基づいて遺産が分割されます。つまり、特別受益を考慮した「具体的相続分」での計算ができなくなるため、過去の贈与などを主張して相続分を調整することは非常に困難になります。
このようなルールが設けられた背景には、長期間にわたり遺産分割が未了のまま放置される事案を減らし、早期に法律関係を安定させるという目的があります。いつまでも過去の贈与に遡って遺産分割ができない状態を解消することで、相続人間の紛争を予防し、円滑な相続手続きを促す狙いがあります。
第904条の3【期間経過後の遺産の分割における相続分】
前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
一 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
注意点2:遺留分の計算では相続開始前10年以内の贈与が対象に
遺産分割協議における特別受益の主張とは異なり、最低限の遺産を確保する権利である「遺留分」を計算する際には、特別受益の扱いに異なる期間制限が設けられています。
遺留分侵害額を請求する場合、持ち戻しの対象となる特別受益は、原則「相続開始前の10年間に行われた贈与」に限定されます。これは民法第1044条第3項によって明確に定められており、被相続人が亡くなる前10年以内に行われた贈与でなければ、遺留分の計算に含めることはできません。
ただし、この10年という期間制限には例外も存在します。被相続人と贈与を受けた相続人の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っている場合、10年より前の贈与であっても遺留分の計算対象となります。
他方で、遺留分権利者に対する生前贈与については、遺留分請求の義務者のような10年の期間制限はないものと解されます。
10年を経過していても例外的に特別受益を主張できるケース
先ほど解説したように、相続開始から10年が経過していると、遺産分割において特別受益の主張をすることが制限されます。しかし、10年が経過していても例外的に特別受益の主張が認められる場合があります。
まずは、相続人間で特別受益を踏まえた具体的相続分により遺産分割することに合意した場合です。相続人が具体的相続分での遺産分割を認めるのであれば、相続人間の不公平は問題にならないからです。
また、相続開始時から10年が経過する前に家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判の申立てをした場合には、特別受益の制限はされません。
さらには、相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産分割請求できないやむを得ない事由があった場合には、その事由の消滅した時から6か月経過前に遺産分割請求を家庭裁判所にした時も、例外的に特別受益を考慮した具体的相続分により遺産分割をすることができます。ここで、「やむを得ない事由」とは、被相続人が死亡したことをおよそ知ることができない場合や判断能力が無くなっているものの、成年後見人が選任されていない場合、相続開示後10年経過してから他の相続人が相続放棄した場合などが想定されます。
他の相続人に特別受益を主張したいときに取るべき3つの行動
特別受益は、遺産分割において自動的に考慮されるわけではありません。特別受益があったことを主張する側が、具体的に主張立証する必要があります。スムーズかつ公平な遺産分割を実現するためには、以下の3つのステップを順に進めることが重要となります。
ステップ1:まずは証拠を集める
特別受益を考慮することで公平な遺産分割を実現するためには、客観的な証拠が不可欠です。感情的な「言った言わない」の水掛け論を避け、具体的な事実に基づいて話し合いを進めたり、家庭裁判所での手続きを有利に進めるためには、証拠の有無が結果を大きく左右します。特別受益の主張側が立証責任を負うため、早期かつ計画的な証拠収集が重要となります。
特別受益の主張に有効な証拠の例を以下に示します。
| 贈与の種類 | 有効な証拠例 |
| 金銭の贈与 | 預金通帳の取引明細、振込用紙の控え、贈与契約書、誓約書 |
| 不動産の贈与 | 登記事項証明書、贈与契約書 |
| 自動車の贈与 | 車検証、贈与契約書 |
| その他 | 被相続人の日記、手紙、メールなどのやり取りの履歴、遺言書 |
これらの証拠は、遺品整理の際に被相続人の手元から見つかる可能性があります。また、金融機関への取引履歴の開示請求や、法務局での登記情報の取得も検討すると良いでしょう。金融機関によっては10年以上前の取引履歴も保存している場合があるため、まずは問い合わせてみてください。
もし手元に証拠が見当たらない、あるいは収集方法が分からない場合でも、諦める必要はありません。弁護士に相談すれば、弁護士会照会を利用して、金融機関や関係機関から必要な情報を取得できる場合があります。専門家のサポートを得ることで、よりスムーズな証拠収集が期待できるでしょう。
ステップ2:遺産分割協議で冷静に主張する
遺産分割協議は、親族間で感情的な対立が生じやすい場であることを認識し、冷静に対応することが重要です。ステップ1で収集した預金通帳の取引明細や贈与契約書など、客観的な証拠に基づいて事実を伝えます。感情的な言葉ではなく、具体的な資料を示し、特別受益の存在と金額を誰もが理解できるよう説明しましょう。口頭での説明では伝わりにくいことも多いため、文書でまとめて特別受益に関する主張をするようにします。
全員が納得できる合意形成を促すため、相手の意見にも耳を傾け、一方的な主張に終始しない柔軟な姿勢が求められます。互いの感情を刺激せず、建設的な議論を心がけることで、円満な解決への道が開かれるでしょう。
ステップ3:話がまとまらない場合は家庭裁判所での手続きへ
遺産分割協議で当事者間の話し合いがまとまらない場合、次の手段として家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。遺産分割調停とは、遺産の分割方法について争いがある場合に、裁判官1人と調停委員2人で構成される調停委員会が間に入り、当事者の意見を聞き、調整や解決案の提示を行うことで、相続人全員の合意を目指す話し合いの手続きです。当事者間では感情的になりやすいケースでも、中立な第三者が関与することで円満な解決が期待できます。
しかし、調停でも話し合いがまとまらず不成立となった場合は、自動的に「遺産分割審判」という手続きへ移行します。遺産分割審判では、家庭裁判所の裁判官が、提出された証拠や一切の事情を総合的に考慮し、法的な判断として遺産の分割方法を決定(審判)します。これにより、最終的な遺産分割の解決が図られます。
特別受益に関するよくある質問
特別受益に関する期限について解説してきましたが、その他にも特別受益に関係する論点は多くあります。以下では、特別受益に関するよくある質問をまとめてみました。
持ち戻しが免除されるケースとは?
特別受益の持ち戻しは、相続人間の公平を実現させる制度ですが、免除されるケースもいくつか存在します。主なケースは次の3つです。
- 被相続人が生前に持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合
- 婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産(またはその取得資金)の贈与や遺贈があった場合
- 相続人全員が遺産分割協議で、持ち戻し免除に合意した場合
まず、被相続人が生前に遺言書などで「持ち戻しを免除する」という明確な意思表示をしていた場合です。被相続人の意思は尊重されるため、遺言書にその旨が記載されていれば、遺留分を侵害しない範囲で特別受益の持ち戻しは行われません。
次に、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与や遺贈があった場合には、原則として持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。この推定規定は、長年連れ添った配偶者の老後の生活保障を目的として導入された制度です。
最後に、相続人全員が遺産分割協議で、特別受益として持ち戻さないことに合意した場合です。この場合も、持ち戻しは免除されます。
相手が特別受益を認めない場合はどうすればいい?
他の相続人から特別受益を認めないと言われた場合でも、まずは収集した客観的な証拠を提示し、冷静な話し合いを試みることが重要です。特別受益の主張には、証拠に基づく論理的な説明が不可欠です。これらの資料を示し、感情的にならずに再度理解を求める機会を設けましょう。
当事者間の話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続で特別受益の存在を確定させるしかありません。いずれの段階においても、法的な主張や証拠の提出が結果を左右するため、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応方法について専門的なアドバイスを受けることが、問題解決への最も効果的な道となるでしょう。
弁護士に相談するタイミングは?
特別受益に関する問題は、複雑な法律知識と交渉力を必要とするため、一人で抱え込まずに専門家である弁護士に相談することが早期解決への近道です。ご自身の状況と照らし合わせ、相談すべきか判断できるよう、特に以下の3つのタイミングでは、弁護士への相談を検討されることをお勧めします。
遺産分割協議が難航している時
相続人間での話し合い(遺産分割協議)が感情的になり、なかなか結論が出ない、または他の相続人が話し合いに応じない場合、弁護士が代理人として介入することで状況が好転する可能性があります。弁護士は第三者の立場で冷静に交渉を進め、法的な観点から適切な解決策を提案してくれるでしょう。弁護士の介入により平行線だった協議が成立に至ったケースや、公正な遺産分割ができたケースも多数報告されています。
遺産分割調停や審判を検討している時
遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での遺産分割調停や審判に進むことになった場合、法的な手続きを有利に進めるには専門知識が不可欠です。
弁護士は調停申立ての準備から、主張書面の作成、証拠収集のアドバイス、そして調停や審判における効果的な主張の組み立てまで、手厚くサポートしてくれます。これにより、ご自身の権利を適切に守りながら手続きを進められるため、安心して任せられるでしょう。
証拠が不足している、または相手が弁護士を就けた時
特別受益を主張するための客観的な証拠が手元にない場合や、相手の相続人がすでに弁護士を立てている場合は、速やかに弁護士に相談すべきです。弁護士は有効な証拠収集について具体的なアドバイスを提供したり、弁護士会照会などの制度を活用して情報を取得したりすることが可能です。相手が弁護士を立てている状況では、同等の専門家を立てることで、交渉を対等に進めることができるでしょう。
特別受益の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、特別受益自体に「時効」という概念は存在しませんが、その主張には期限が設けられている点について解説しました。
特別受益に関する問題は、相続人間の感情的な対立を招きやすく、当事者間での解決が困難なケースが少なくありません。生前の贈与の有無やその評価、さらには法改正によって加わった期間制限など、複雑な法律知識が求められる場面も多いため、一人で抱え込まずは弁護士へ相談することをお勧めします。
何よりも重要なのは、問題解決に向けた「早期の行動」です。特に「相続開始から10年」という主張期限を考慮すると、時間が経過するほど特別受益の主張は困難になるリスクが高まります。証拠の散逸や関係者の記憶が曖昧になることも避けられないためです。まずは一度弁護士に相談し、ご自身のケースにおける具体的なアドバイスを受けることを強く推奨します。適切なタイミングで専門家のサポートを得ることで、公平な遺産分割への道が開けるでしょう。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。