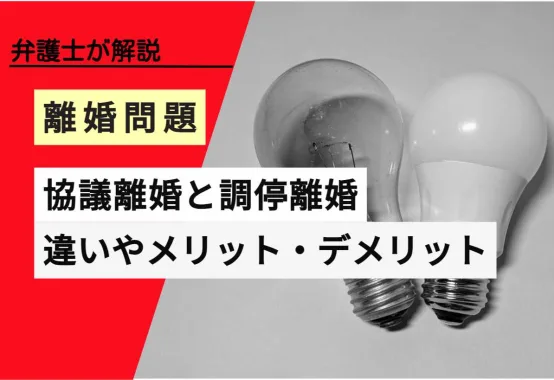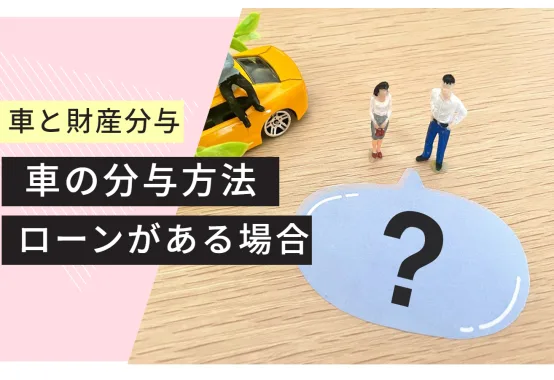離婚調停を申し立てる際に、どこの裁判所に申立てをすればよいのか悩むことがあると思います。
離婚調停の手続は、家庭裁判所に対して申立書類を送付することで開始されます。
しかし、管轄裁判所がどこなのかを理解していないと、誤った裁判所に申し立てをしてしまい、余計な時間と費用を要してしまう可能性があります。
管轄を正しく理解することによって、スムーズな手続きを進めるための第一歩となります。
本記事では、離婚調停を申し立てる際の裁判所の場所、すなわち管轄について解説します。
離婚調停の管轄(どこの裁判所に申し立てるのか)
離婚調停の申し立てをする際に重要な点が、「どこの裁判所に申し立てるか」という点です。
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間の離婚問題を家庭裁判所の調停委員の仲裁により解決を図る手続をいいます。
通常、夫婦間の離婚協議から開始されますが、離婚協議が功を奏しない場合、離婚調停の申立てが行われます。他方で、離婚協議の結果、夫婦間で合意に至れば協議離婚となりますので、離婚調停の申立ては行われません。
管轄とは?
管轄とは、特定の事件を特定の裁判所が取り扱う権限のことを指します。
管轄には、職分管轄、土地管轄の3つがあります。どの場所の家庭裁判所に申し立てをするのかはこの土地管轄の問題となります。
管轄の異なる裁判所に調停の申立てをすると、管轄違いを理由に移送されるのが原則です。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
離婚調停の申し立ては、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
離婚調停の申し立てをするためには、離婚調停の手続を行うことのできる管轄家庭裁判所に対して離婚調停の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所の管轄については、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所のいずれかの家庭裁判所と定めています。つまり、申立人が大阪市に居住し、相手方が東京23区に居住している場合、夫婦間で大阪家庭裁判所を管轄裁判所とする合意が成立していない限り、申立人は東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
| 家事事件手続法245条1項家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。 |
相手方の住所地とは
管轄裁判所の基準となる住所地とは、相手方の生活の本拠をいいます。
生活の本拠は住民票上の住所を指します。
しかし、住民票上の住所に居住しておらず生活の本拠ではない場合、実際に居住している場所が住所となります。
当事者が合意で定めた家庭裁判所
離婚調停の申立てに際して、当事者同士が合意すれば、相手方の住所地ではない他の家庭裁判所を管轄として定めることが可能です。
例えば、相手方は東京都に居住し、申立人は大阪府に住んでいる場合、双方が合意して大阪家庭裁判所を管轄裁判所とすることができます。
合意管轄が認められるためには、申立ての前に、当事者間で特定の家庭裁判所を管轄裁判所とする合意書を作成した上で、管轄合意を証するものとして合意書を裁判所に提出します。

管轄合意がない場合の離婚調停の対応
離婚調停を進める上で、夫婦間の関係性が悪化していることから、調停を行う管轄裁判所の場所について合意できない場合は多くあります。
ただ、夫婦の合意が得られない場合でも、調停手続きを円滑に進めるための方法がいくつか存在します。
自庁処理の上申
管轄裁判所ではない家庭裁判所に対して、調停手続を受理するように自庁処理の上申をします。
管轄裁判所ではない以上、管轄のある家庭裁判所に移送されるのが原則です。
しかし、当事者の状況やその他の事情を考慮して特に必要があると認められる場合には、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所自らが処理することがあります。これを自庁処理といいます。
申立人は、家庭裁判所に対して申立てをする際に、自庁処理するべき具体的な事情を記載した上申書を提出して、自庁処理を求めます。
裁判所は、申立人から自庁処理の申立てがあったときは、相手方の意見を聞いた上で自庁処理するべきか判断します。
高齢の両親や子供の養育監護のために遠隔地の裁判所に出頭できない場合には自庁処理が認められる可能性はあります。ただし、後述する電話・ウェブ会議システムの利用により遠方の裁判所に出向く必要がなくなったため、自庁処理が認められるケースはそこまで多くはないと考えます。
電話会議・ウェブ会議システムの利用
電話会議やウェブ会議のシステムを活用することで、遠方の裁判所に出向かずに調停手続に参加することができます。
電話会議システムでは、家庭裁判所に出席せずに電話を通じて調停委員とのやり取りを行います。
ウェブ会議システムでは、Teamsやその他のアプリケーションを用いて、パソコン画面を通じて、調停委員とのやり取りを行います。家庭裁判所によっては、ウェブ会議システムの」導入をしていないケースもありますから、その場合には、電話会議により対応することになります。
これらのシステムにより、当事者は自宅や弁護士事務所など、安心できる環境から調停に参加できるため、精神的な負担を軽減することが可能です。また、遠方の裁判所まで出向くための費用や時間の負担も軽減させることができます。
電話会議やテレビ会議システムの利用は、遠距離でも効率的に調停手続きを進める手段として非常に有用なものです。


離婚訴訟の管轄裁判所
離婚訴訟において、管轄裁判所は、被告の住所地の裁判所だけでなく原告の住所地の裁判所も含まれます。
離婚調停の不成立となる場合、調停手続が終了します。当然に離婚裁判に移行するわけではありません。
離婚を求める配偶者が家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起することで訴訟手続が開始されます。
離婚訴訟では、夫婦双方が離婚原因や財産分与などの主張や立証を尽くして審理を進め、裁判所による終局的な判断を下すプロセスです。
離婚訴訟では、離婚調停とは異なり相手方の住所地だけでなく原告の住所地の家庭裁判所も管轄裁判所に含まれています。
そのため、離婚訴訟を提起するにあたっては、家庭裁判所の管轄をよく確認して、管轄裁判所が複数ある場合には、どちらの裁判所が有利かをよく検討するべきでしょう。
離婚調停の場所に関するよくある質問
離婚調停の申立書はどこにありますか?
離婚調停の申立てを行うためには、申立書や事情説明書などの書類を管轄裁判所に提出しなければなりません。
申立書や事情説明書の書式は家庭裁判所によって異なります。
申立関係書類は、家庭裁判所の窓口で受け取ることができます。
また、インターネットで、管轄裁判所+離婚調停申立書と検索し、家庭裁判所ごとの書式のファイルをダウンロードすることで、申立書類を入手することができます。
そのファイルを用いて申立書や事情説明書を作成します。
離婚調停には必ず出席する必要がありますか?
離婚調停の調停期日には出席する必要があります。
離婚調停に欠席しなければ、調停が不成立となる可能性があります。また、申立人側が申立てをしておきながら理由もなく欠席を続ければ、離婚調停の申立てが、調停なさずとして調停手続が終了する可能性もあります。
そのため、調停手続には、欠席せずに出席するようにしましょう。仮に、欠席する場合には必ず事前に連絡するか、代理人弁護士に委任し、弁護士に代わって出席してもらいましょう。
離婚調停の問題は弁護士に相談を

離婚調停の問題は専門知識が求められるため、弁護士に相談することが重要です。
離婚調停の手続には複雑な要素が多く、自分だけで進めるのは難しい場合が多いです。また、相手方との交渉には、大きな精神的な負担を伴います。そこで、弁護士に相談することで、離婚調停をよりスムーズかつ有利に進められます。弁護士は法律事務の専門家であり、具体的な事例に基づいたアドバイスを提供します。