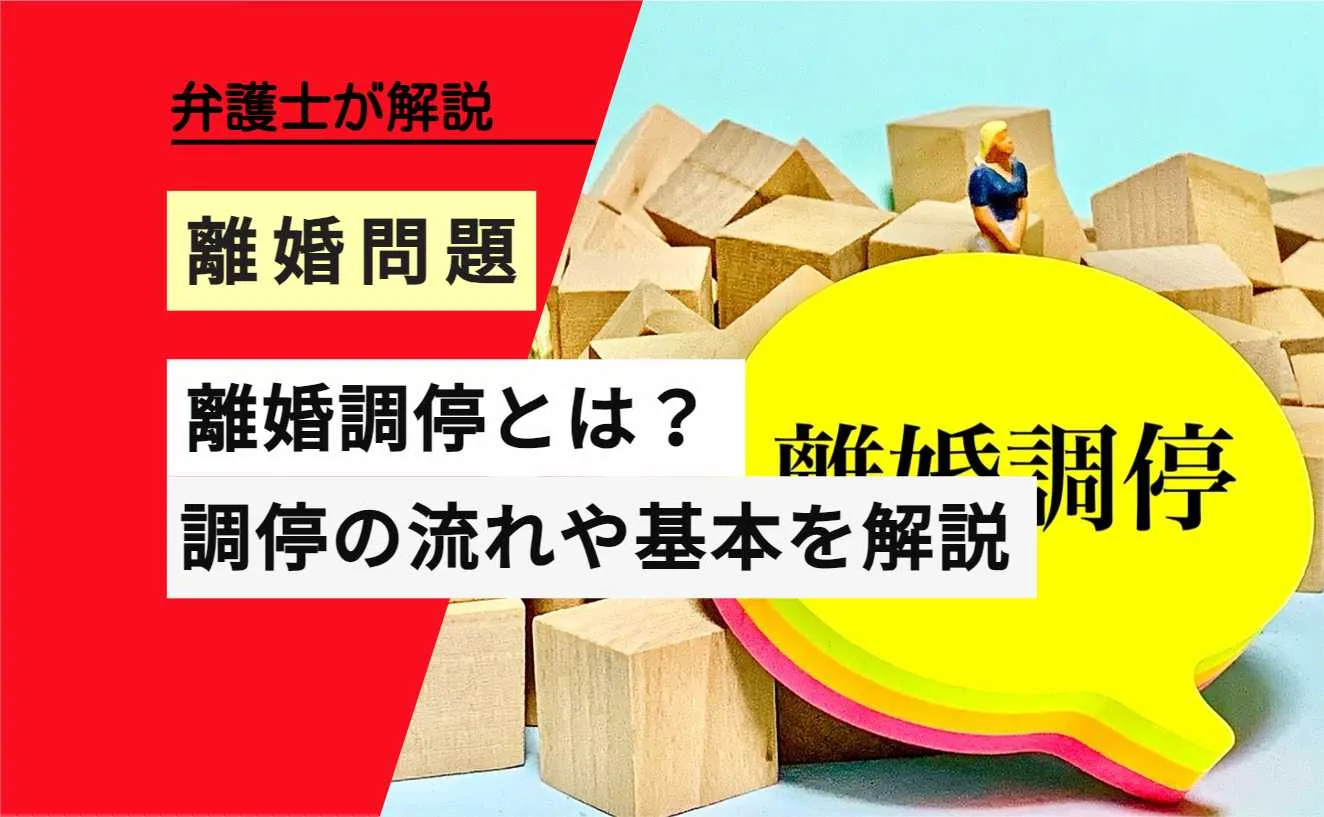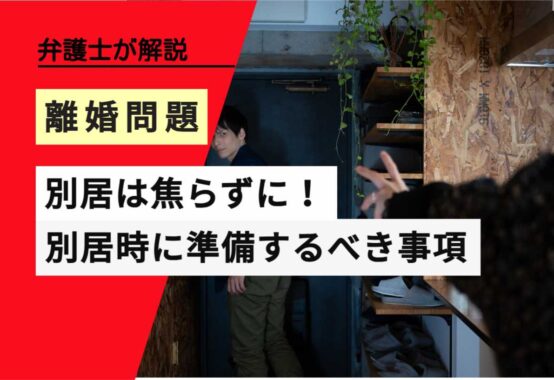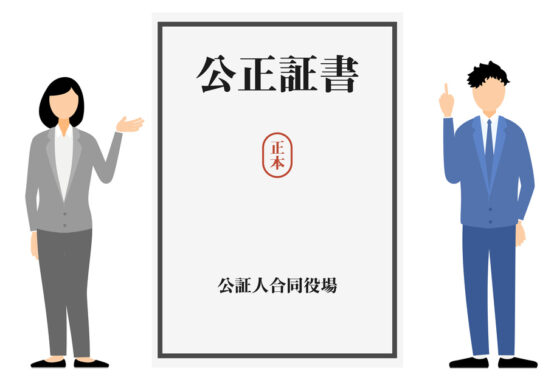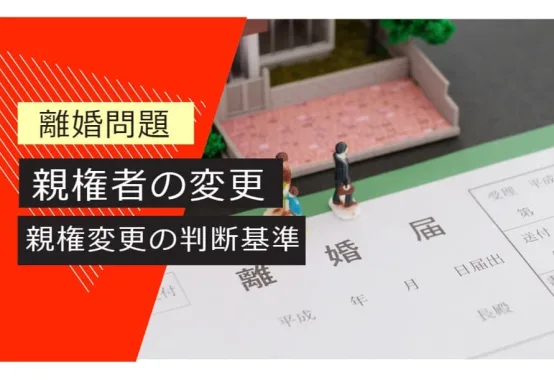「離婚したいけれど、配偶者との話し合いが進まない」
「離婚することについては合意を得たけれど、離婚条件について揉めている」
このような場合に活用できる法的手段が、離婚調停です。
離婚調停を申し立てれば、家庭裁判所の調停委員が間に入り、離婚の話し合いを進めてくれます。
調停委員からのアドバイスも交えて冷静に話し合えるので、納得のいく条件で離婚できる可能性を高めることが可能です。
本記事では、離婚調停とは何か、手続きの流れや必要な書類と費用などについて、分かりやすく解説します。離婚調停を有利に進めるためのポイントや注意点もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
離婚調停とは?何をする?
離婚調停とは、家庭裁判所で離婚問題の当事者が話し合い、合意による解決を目指す手続きのことです。
以下で、離婚調停について詳しく解説します。
離婚調停とは「家庭裁判所で話し合うこと」
離婚調停とは、家庭裁判所の調停手続きをもとに離婚問題について話し合うことです。正式名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。
家庭裁判所で話し合うとはいっても、当事者が直接話し合うわけではありません。家庭裁判所の調停委員会が仲介役となり、話し合いを進めます。
調停委員会は、裁判官1名と調停委員2名(夫婦関係調整調停では男女1名ずつ)で構成され、主に2名の調停委員が当事者双方から話を聞く形で話し合いを進めていきます。
話し合う内容は、離婚問題全般です。まずは離婚するかどうかについて話し合い、当事者双方が離婚することに合意すれば、親権や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚条件についても話し合いを進め、合意による解決を目指します。
離婚調停と離婚裁判の違いについて
離婚調停と離婚裁判は、どちらも家庭裁判所を利用した離婚手続きです。しかし、具体的には、以下のようにさまざまな違いがあります。
| 離婚調停 | 離婚裁判 | |
| 解決方法 | 話し合いによる合意(調停) | 裁判所による強制的な判断(判決)。当事者が合意すれば和解も可能 |
| 進行役 | 調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)。主に調停委員2名が進行。 | 裁判所(裁判官1名) |
| 公開・非公開 | 非公開 | 公開 |
| 証拠の要否 | 不要ただし証拠がなければ不利になる可能性がある。 | 必要 |
| 法定離婚事由の要否 | 不要 | 必要 |
| 有責配偶者からの申立て | 可 | 可。ただし、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない |
| 不服申立ての可否 | 不可。ただし、審判が下された場合は即時抗告が可能 | 判決に対しては控訴が可能和解が成立した場合は不可 |
| 離婚成立時の作成書面 | 調停調書 | 判決書和解が成立した場合は和解調書 |
離婚裁判は、基本的に当事者が提出した主張と証拠に基づいて裁判所が判決を下すことにより、白黒をつける手続きです。勝訴すれば、相手の同意がなくても強制的に離婚できるというメリットがあります。
それに対し、離婚調停は話し合いであるため、相手の同意がなければ離婚はできません。しかし、調停委員を交えてじっくり話し合うことにより、離婚裁判よりも柔軟な解決が可能というメリットがあります。
離婚裁判でも和解協議はできますが、判決の見通しを念頭に置いて交渉することになりがちです。そのため、柔軟に交渉するのは容易ではありません。
なお、離婚問題については裁判を提起する前に調停を申し立てる必要があり、このことを「調停前置主義」といいます。
どのような場合に離婚調停を行ったほうがよいのか
夫婦の話し合いだけでは離婚問題を解決することが難しい場合には、離婚調停を行った方がよいでしょう。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
・相手が離婚に反対し、話し合いに応じてくれない
・離婚条件について意見が対立し、話し合いが平行線になっている
・DVやモラハラなどで相手と直接話し合うことが難しい
・感情的に対立していて、冷静な話し合いが難しい
・相手が不倫や浮気の事実を認めないため、離婚の話し合いが進まない
このようなケースでも離婚調停を申し立てれば、裁判所からの呼び出し受けて相手が調停に出頭し、話し合いが成立する可能性が高くなります。
調停では、中立・公平な調停員が仲介するため、冷静な話し合いが可能になります。
また、不倫や浮気の事実関係を確定させたい場合、離婚裁判を提起する前提として離婚調停を申し立てることも考えられます。
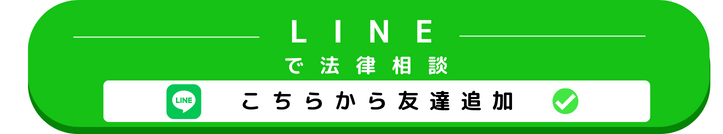
離婚調停で必要となる書類と費用

離婚調停を申し立てるためには、さまざまな書類や費用が必要となります。ここで、必要書類と費用をあらかじめ確認しておきましょう。
離婚調停の必要書類について
離婚調停を申し立てる際には、以下の書類が必要です。
| 書類 | 必要となるケース | 入手方法 |
| 申立書 | すべてのケース | 裁判所の窓口で入手する。裁判所のホームページからのダウンロードも可能 |
| 事情説明書 | すべてのケース | 裁判所の窓口で入手する。裁判所のホームページからのダウンロードも可能 |
| 子についての事情説明書 | 未成年の子がいる場合 | 裁判所の窓口で入手する。裁判所のホームページからのダウンロードも可能 |
| 進行に関する照会回答書 | すべてのケース | 裁判所の窓口で入手する。裁判所のホームページからのダウンロードも可能 |
| 送達場所等届出書 | すべてのケース | 裁判所の窓口で入手する。裁判所のホームページからのダウンロードも可能 |
| 非開示の希望に関する申出書 | 相手方に開示されたくない書面を提出する場合 | 裁判所の窓口で入手する。裁判所のホームページからのダウンロードも可能 |
| 夫婦の戸籍謄本 | すべてのケース | 市区町村の役所で申請する。 |
| 年金分割のための情報通知書 | 年金分割を請求する場合 | 相手方の年金を運営している機関(年金事務所など)で申請する。 |
| 夫婦の財産状況が分かる書類 | 財産分与を請求する場合 | 書類によって異なる 。 |
| 夫婦の収入が分かる書類 | 養育費を請求する場合 | 書類によって異なる 。 |
| 離婚原因が分かる書類 | 相手方が離婚原因を作った場合 | 書類によって異なる 。 |
すべての書類について、ご自身の控えとしてコピーを1通とっておきましょう。申立書については、さらに相手方用としてコピー1通が必要です。
裁判所ホームページの以下のページでは、離婚調停の必要書類について詳しく説明されていますので、ご参照ください。
こちらのページでは、裁判所が配布している申立て関係書類の書式をダウンロードして使用できます。
参考:裁判所|家事調停の申立て
なお、以上の書類に加えて「陳述書」を提出すると離婚調停を有利に進めやすくなり、おすすめです。陳述書とは、離婚に至る経緯や離婚原因などを物語形式で分かりやすくまとめた書面のことです。陳述書を提出すると、ご自身の主張を調停委員にあらかじめ伝えることができます。
こちらの記事では、陳述書の書き方や注意点、文例などを分かりやすく解説していますので、ぜひご参照ください。
離婚調停の際に必要となる費用
離婚調停を申し立てる際に必要な費用は、以下のとおりです。
| 内訳 | 金額 |
| 申立て手数料(収入印紙代) | 1,200円 |
| 郵便切手代(連絡用) | 1,000円前後※裁判所によって異なります。大阪家庭裁判所の場合は1,130円です。 |
| 夫婦の戸籍謄本の取得費用 | 450円 |
申立人は、上記の費用を納める必要があります。
上記以外にも、裁判所の窓口で申立て書類を提出する場合は交通費、申立て書類を郵送する場合は送料がかかります。
調停が始まると、出頭するための交通費や、遠方であれば宿泊費もかかるかもしれません。調停終了後、調停調書の謄本を取得するためには、1通につき150円の手数料がかかります。これらの費用は、各自が負担します。
また、弁護士に離婚調停を依頼する場合には、弁護士費用が別途必要です。弁護士費用の金額は弁護士によって異なるので、依頼前に確認しましょう。


離婚調停のおおまかな流れ

離婚調停は、以下の流れで進められます。
・家庭裁判所への調停申立て
・1回目の調停期日
・2回目以降の調停期日
・調停成立
以下では、調停申立て前に準備すべきことと、離婚成立後に行うべき手続きも併せ含めて、詳しくご説明します。
1.調停申立て前の準備
離婚請求に必要な証拠は、早めに確保しておきましょう。離婚調停の申立てに証拠の提出は必須ではありませんが、調停中に証拠の収集が困難になることは少なくありません。そのため、調停申立ての前には確保しておきましょう。
確保すべき証拠はケースによって異なりますが、主に以下のようなものが挙げられます。
【離婚原因を証明するための証拠】
・不貞行為の証拠画像や動画、音声、メールやLINEでのやりとりなど
・DVやモラハラの証拠画像、動画、音声、日記に記載した記録など
・DVやモラハラで心身に不調をきたした際の診断書、画像など
【財産分与を請求するための証拠】
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・車検証
・保険証券
・通帳の写し など
【養育費を請求するための証拠】
・給与明細
・源泉徴収票
・確定申告書の控え
・納税証明書 など
こちらの記事では、離婚前にやっておくべき準備事項や検討事項について詳しく解説しています。
また、こちらの記事では、離婚調停に望む際の服装や持ち物などをご紹介しています。確認し、必要なものがあれば早めに準備しておきましょう。
また、こちらの記事では、離婚調停に望む際の服装や持ち物などをご紹介しています。ご確認の上、必要なものがあれば早めに準備しておきましょう。
2.家庭裁判所への調停申立て
必要な証拠を確保できたら、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。
離婚調停の申立ては、申立人の住所地ではなく相手方の住所地の家庭裁判所で行います。例えば、申立人が大阪市に居住、相手方が東京都に居住している場合、大阪家庭裁判所ではなく東京家庭裁判所への申立てが必要です。
申立ては、申立書およびその他の必要書類を家庭裁判所に持参するか、または郵送して提出することに行います。
申立てが受理されると、1回目の調停期日が指定されます。1回目の調停期日は、申立てから約1ヶ月半先の日程になることが少なくありません。
3.1回目の調停期日
1回目の調停期日として指定された日時に、当事者双方が家庭裁判所へ出頭します。
申立人と相手方の待合室は、それぞれ離れたところに設けられています。出頭指定時刻もずらされるなどして、お互いが裁判所内で鉢合わせしないように配慮されているので安心です。
通常、申立人が先に調停室に呼び出され、調停委員から、別居に至る経緯や離婚原因等について聴き取りを受けます。ひと通りの話をしたら退室し、その後に相手方が調停室に入って調停委員と話をします。以降、申立人と相手方が交代で調停委員と話す形で、話し合いが進められます。
調停室で話をする時間は1回当たり、おおよそ30分~45分で、1回の調停期日に要する時間は2時間程度です。
1回目の調停期日で離婚が成立しなかった場合は、次回期日の日程調整を行います。おおむね1ヵ月~1ヵ月半に1度のペースで複数回の調停期日が設けられ、話し合いを煮詰めていくのが一般的です。
ただし、話し合いによる解決の見込みが薄い場合には、1回目の調停期日で調停不成立となる場合もあります。調停不成立となった場合は状況に応じて、離婚審判を求める、離婚訴訟を提起する、しばらく別居を続けて再度の離婚調停を申し立てるなどの対処法を検討しなければなりません。
こちらの記事では、離婚調停が不成立となってしまった場合の対処法について詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
4.2回目以降の調停期日
2回目以降の調停期日でも、初回期日と同様に、双方が交代で調停委員と話す形で話し合いを進めていきます。
期日間に、それまでの話し合いの内容を踏まえて主張や事実を整理した準備書面や、浮き彫りとなった焦点に関する事実を詳細に記載した陳述書などを提出しておきましょう。そうすれば、次回以降の調停期日における話し合いを有利に進めやすくなります。
話し合いを重ねて当事者双方が合意できれば、その時点で調停が成立します。合意できなければ、さらに3回目、4回目と続けて調停期日が設けられることもあります。
5.調停成立
最終的に当事者双方が合意に至れば、その内容で調停が成立します。調停が成立すると、裁判官が合意内容に基づき調停条項を作成し、当事者双方の面前で読み上げます。
このときには、原則として当事者双方が同席しなければなりません。弁護士に依頼している場合は弁護士が間に着席するなどして、当事者が隣り合わないように配慮されます。
離婚成立後に行う手続き
調停成立後は、裁判所が調停調書を作成します。離婚届を提出する際には調停調書の謄本が必要なので、裁判所に申請して謄本の交付を受けましょう。
調停が成立した時点で離婚は成立していますが、戸籍に離婚の事実を反映させるためには、離婚届が別途必要です。離婚届は、調停成立から10日以内に市区町村の役所へ提出する必要があります。
離婚届は単独で提出することが可能です。どちらが提出しても構いませんが、相手に委ねると期限内に提出されないおそれがあるため、ご自身で確実に提出した方がよいでしょう。
役所では必要に応じて、新戸籍の編製や氏の変更許可などの申請も行います。年金分割の合意をした場合は、年金事務所での手続きが別途必要です。
離婚成立後に行うべき手続きについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
離婚調停で聞かれることとは?
離婚調停で聞かれることはケースによって異なる場合もありますが、一般的に以下のような内容がひと通り聞かれます。
調停委員に分かりやすく、かつ、正確に伝えることができるように、あらかじめ内容をまとめておきましょう。陳述書を作成する際にも、以下のポイントを中心に具体的な事実や心情を記載するとよいでしょう。
・結婚の経緯
・離婚を望む理由
・現在の夫婦関係の状況
・夫婦関係が修復できる可能性
・親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件に関する意見
・離婚後の生活 など
「離婚を望む理由」と「現在の夫婦関係の状況」は、離婚できるかどうかに直結します。離婚条件にも関わる要素ですので、特に説得的に説明できるようにしておきましょう。
また、今までに夫婦関係の修復に努めたものの、できなかったという事情を説明できれば、離婚できる可能性が高まります。
離婚後の生活については、未成年の子の親権を求める場合に特に重要です。離婚後に仕事をして収入を得られるのか、子育てについて親族などの協力を得られるのか、などを説明できるようにしたいところです。
離婚調停を有利に進めるためのポイントと注意点
離婚調停を有利に進めるために押さえておくべきポイントは、次の6点です。
・証拠を集めておく
・調停委員に伝えたい内容をまとめておく
・調停委員の心証を良くする
・争点に関する適切な条件を把握しておく
・調停条項をしっかり確認する
・弁護士に相談する
それぞれの内容について、注意点と併せてご説明します。
証拠を集めておく
まずは、離婚に関する証拠を集めておくことが大切です。例えば、相手の浮気や不倫が原因で離婚したい場合は、写真・動画・音声のほか、メールやLINE、SNSでのやりとりなどで、不貞行為を証明できる証拠を集めておきましょう。
離婚調停では、証拠がなくても申立てが可能です。しかし、相手が浮気や不倫などの事実を否認した場合は証拠がなければ、基本的にその事実はなかったものとして話し合いが進められてしまいます。
そうすると、たとえ離婚できたとしても、慰謝料を獲得することが難しくなります。財産分与や養育費を請求する場合も、夫婦の財産状況や収入に関する証拠を確保しておかなければ、適正な金額を獲得することは難しいでしょう。
離婚調停を有利に進めるためには、有力な証拠を確保しておくことが最も重要です。
調停委員に伝えたい内容をまとめておく
離婚調停の進行役は調停委員となるため、あなたの言い分を調停委員に理解してもらうことは極めて重要です。離婚を望む理由や離婚の希望条件をはじめとして、質問される可能性が高い事項を中心に、調停委員に伝えたい内容を事前にまとめておきましょう。
事前に陳述書を提出した場合でも、補充的な質問を受けることはよくあります。そのため、調停委員に伝えたいことは口頭でも説明できるように、準備しておいた方がよいでしょう。
調停委員の心証をよくする
調停委員は中立・公平な立場ですが、事実上、正当な言い分を述べていると考えられる側に有利な解決に導こうとすることはよくあります。そのため、調停委員の心証を良くすることも大切です。
調停当日は清潔感のある身だしなみや理性的な言葉遣いを心がけ、社会人として常識的な態度で話し合いに臨みましょう。調停中は感情的な態度をとることを極力避けて、相手の言い分にも一定の理解を示しつつ、事実に基づいてご自身の言い分を述べてください。
それでいて、首尾一貫した矛盾のない主張ができれば、調停委員からの信頼が得られる可能性は高くなります。
争点に関する適切な条件を把握しておく
離婚調停で損をしないためには、争点に関する適切な条件を把握しておくことも大切です。例えば、相手の浮気や不倫が原因で離婚する場合の慰謝料について、適切な条件は一般的に数十万円~300万円程度といわれています。
そのため、慰謝料として1,000万円を要求すると、認められる可能性はほとんどありません。調停委員からも「この人は感情的で、常識がない」と判断されるおそれがあります。
逆に、養育費の適正額が月10万円のケースで、相場を知らずに「月3万円は欲しい」などと低い額を条件として提示すると、損することになるでしょう。
調停条項をしっかり確認する
離婚成立後に作成される調停調書には確定判決と同一の法的拘束力が生じますので、裁判官が調停条項を読み上げる際には、文言の1つ1つに注意して確認しましょう。
例えば、慰謝料を分割で支払ってもらう場合、「滞納を○回すると残額を一括で支払う」という清算条項を求めなければ、調停条項に盛り込まれないことがあります。
この場合、相手が滞納を続けたとしても、強制執行手続きでまとまった金額を回収することは難しくなるので、注意が必要です。
弁護士に相談する
離婚調停は、あくまでも法律に基づき裁判所で行われる法的手続きです。
離婚調停を有利に進めるには専門的な知識と経験が要求されますので、弁護士に依頼して行うのがおすすめです。離婚調停の申立てをお考えの際には、離婚問題に強い弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。
離婚調停について弁護士に相談・依頼して得られるメリットは、以下の通りです。
・必要な証拠や、証拠の集め方についてアドバイスしてもらえる
・適切な離婚条件についてアドバイスしてもらえる
・離婚調停の申立て手続きを一任できる
・裁判所や相手方との連絡窓口となってもらえる
・調停期日に同席し、調停委員とのやりとりをサポートしてもらえる
・調停条項が適正か確認してもらえる
こちらの記事では、離婚調停を弁護士に依頼するメリットについて、より詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
当事務所では、離婚問題の解決に力を入れており、数多くの実績がございます。親身な対応を心がけていますので、離婚調停の申立てをお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
離婚調停に関するよくある質問
ここでは、離婚調停に関するよくある質問について、まとめてお答えいたします。
Q.離婚調停中にしてはいけないことがあれば教えてください
離婚調停中には、以下の行為をしてはいけません。
・調停期日に無断で欠席すること
・虚偽の主張を故意にすること
・ねつ造した証拠を提出すること
・相手方と強引に接触したり、嫌がらせをしたりすること
・子どもを連れ去ること
・配偶者以外の人との性的行為(離婚が成立するまでは不貞行為に該当する可能性があるので、避けた方が無難)
Q.離婚調停中に別居をしても問題ないでしょうか?
別居することは可能ですが、できる限り相手方と協議をした上で別居を開始させるのが望ましいでしょう。
相手方の了解を得なければ夫婦の同居義務違反による「悪意の遺棄」に該当すると判断され、慰謝料を請求されるおそれがあります。
ただし、相手方がDVやモラハラ、不貞行為などで夫婦関係を破綻させた場合には、無断で家を出ても問題にはなりません。
また、別居した場合には婚姻費用の分担や子どもの引き渡し、面会交流などの問題をめぐって交渉したり、調停や審判で別途争ったりすることになる可能性もあります。
Q.離婚調停で不成立となってしまった場合、どうしたらいいですか?
離婚を求める場合は、離婚裁判を提起することになるでしょう。その他にも、離婚審判を求めたり、しばらく別居を継続した後に再度の離婚調停を申し立てたりすることも考えられます。
離婚したくない場合は、夫婦関係調整調停(円満)を申し立てることも可能です。
Q.離婚調停で不利になる発言はありますか?
以下のような発言は、調停委員の印象を悪くすることがあります。離婚調停で不利になる可能性があるため、このような発言は極力控えましょう。
・相手の悪口や批判
・具体性がなく曖昧な主張
・過去の発言と矛盾する発言
・自分の希望条件のみに固執する発言
・安易に譲歩しようとする発言
・相手方への直接要求をほのめかす発言
・他の相手との交際をほのめかす発言
Q.離婚調停はどれくらいの期間行なうのでしょうか?
裁判所が公表しているデータによると、離婚調停の申立てから3ヶ月~6ヶ月程度で終了するケースが多く、調停期日の回数は2~4回程度が平均的です。
一方で、期間として1年以上、調停期日の回数として10回以上を要しているケースもあります。離婚に関する有力な証拠がある場合は、早めに離婚裁判に進んだ方が結果として早期に離婚できることも少なくありません。
Q.離婚調停は女性の方が有利だと聞いたが本当か?
離婚調停では、性別による有利・不利はありません。ただし、親権問題については「母性優先の原則」が重視されることから、事実上、女性の方が圧倒的に有利な結果となっています。
また、一般的には男性の方が高収入を得ている世帯が多いことから、婚姻費用や養育費については男性側の負担が重いケースが多いという実情もあります。女性側が浮気などで離婚原因を作ったケースでも、男性側はあえて慰謝料を請求しないケースも珍しくありません。
このような実態から、離婚調停は女性の方が有利だと言われることもありますが、調停委員はあくまでも中立・公平に話し合いを仲介します。
離婚調停は弁護士に相談を

離婚調停は、家庭裁判所で離婚問題について話し合うことですが、有利に進めるには専門的な知識と経験が必要です。相手の主張に押し切られて泣き寝入りしないためにも、離婚調停を申し立てる際は、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士へのご相談をおすすめします。
当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、お電話、Zoom等による方法でお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。