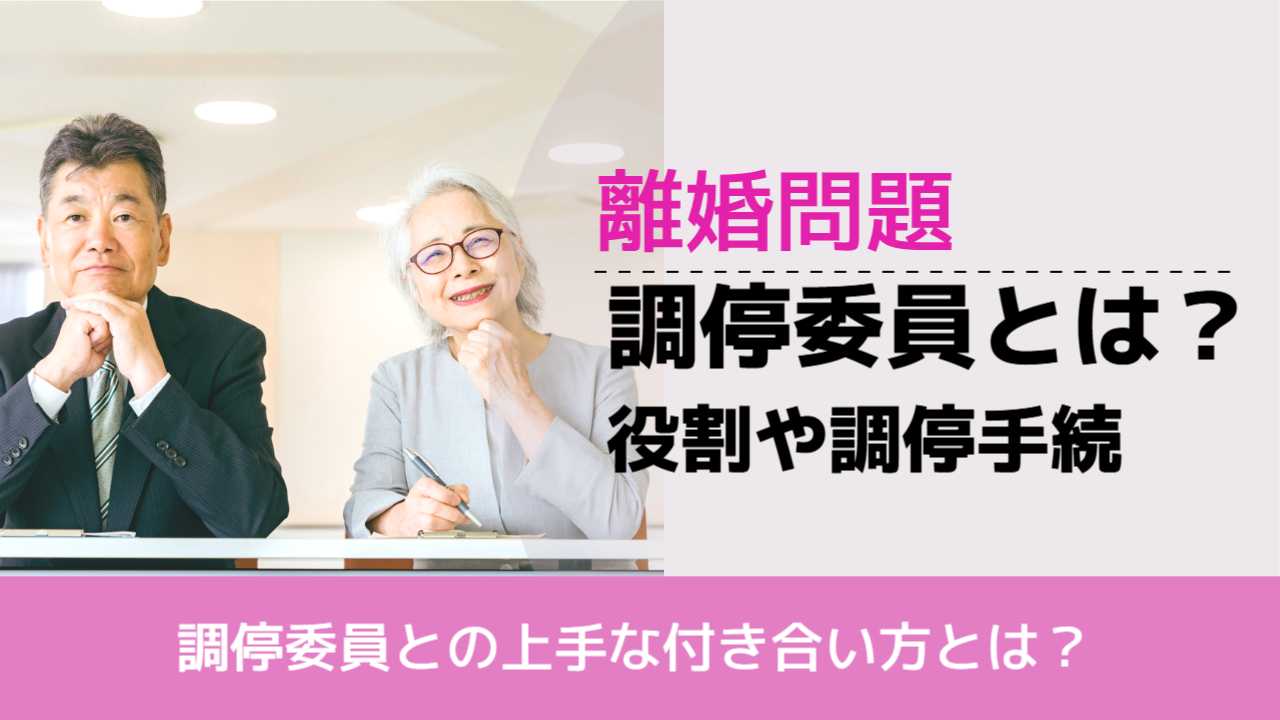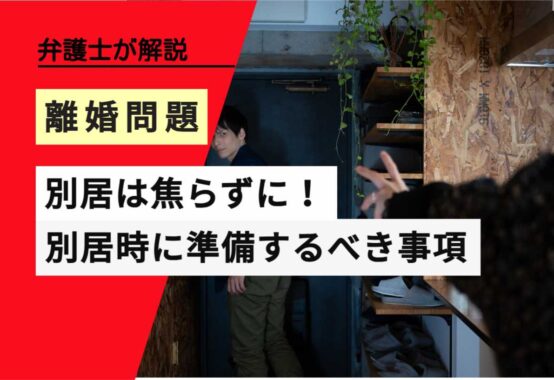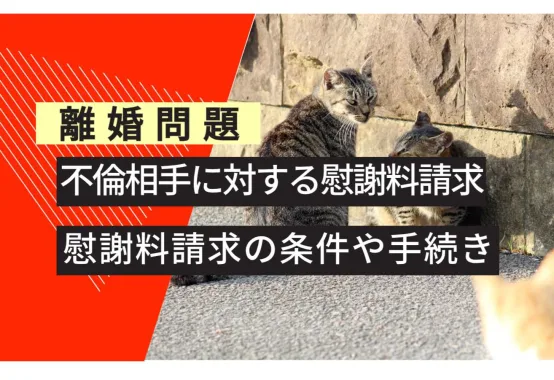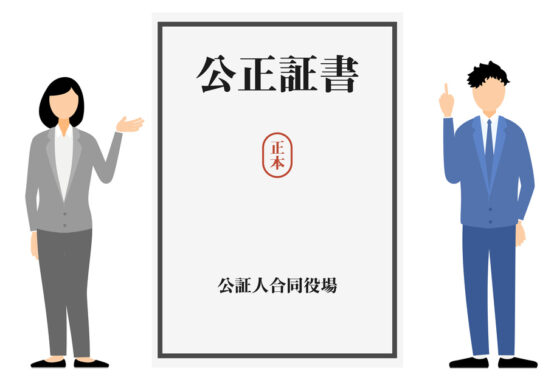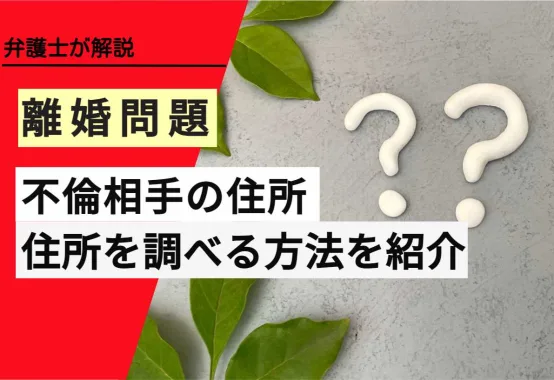調停という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような人が、どんな役割を担っているのかご存じない方もいるのではないでしょうか。「調停委員」は、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれません。
この記事では、紛争解決のサポートを行う調停委員とは一体どんな人なのか、その役割や選ばれ方についてわかりやすく解説します。また、調停の流れや、調停をスムーズに進めるためのポイントなどもご紹介。ぜひ、参考にしてください。
まず知っておきたい「調停委員」の基本的な役割
調停手続において登場する調停委員ですが、その具体的な役割を知っている人はそう多くはありません。以下の項目では、調停委員の具体的な職務内容について詳しくご紹介します。
調停委員は当事者の話を中立な立場で聞く人
調停委員は、申立人と相手方のどちらか一方に偏ることなく、常に中立・公平な第三者として、双方の言い分に平等に耳を傾ける役割を担っています。特に離婚調停などの家事調停では「非対面形式」が採用されており、当事者同士が直接顔を合わせる機会はほとんどありません。調停委員は、申立人と相手方の双方から、互いの主張や感情、紛争に至った経緯や背景にある具体的な事情などを丁寧に聞き出します。こうした聞き取りを通じて、対立する当事者双方の認識のずれを分析し、共通の理解を深めることが、調停委員の基本的な役割の一つです。
裁判官とは違う?話し合いによる円満解決をサポート
裁判官は、法律に基づいて事実を認定し、判決を下す「判断者」としての役割を担います。その判決には法的な強制力があるため、当事者は確定した判決に従う必要があります。一方、調停委員は裁判官とは異なり、当事者間の紛争を話し合いによって解決へと導く「調整役」です。調停では、どちらか一方の言い分だけを正しいと判断するのではなく、双方の意見や感情に耳を傾け、現実的かつ実情に合った解決策を共に探します。
調停の目的は、法的に白黒をつける裁判とは異なり、当事者双方が納得できる解決にあります。調停委員は、そのための双方の対話を促し、当事者の合意形成をサポートします。最終的な判断を下す権限は持たないものの、適切な助言や提案を通じて、当事者の合意を成立させる手助けをします。


調停委員はどんな人が選ばれる?選任の仕組みを解説
調停委員は、社会生活における豊富な知識と経験を持つ一般市民の中から選ばれ、「非常勤の裁判所職員」として、紛争解決に市民の良識を反映させる重要な役割を担います。
では、どのような経歴を持つ人々が、どのようなプロセスを経て調停委員に任命されるのでしょうか。
弁護士や大学教授など、豊富な知識と社会経験を持つ民間人
調停委員には、以下のような法律や専門分野の知識を持つ専門家、および社会生活上の豊富な経験を持つ地域の有識者が任命されます。
| 対象年齢 | 原則として40歳以上70歳未満 |
| 専門職の例 | 弁護士、大学教授、公認会計士、医師、不動産鑑定士、建築士など |
| その他の例 | 地域社会で幅広く活動してきた方 |
これは、紛争の範囲が多岐にわたることから、法律の知識だけでなく、医療、教育、建築、金融、心理学など、それぞれの分野における深い専門知識や多くの社会経験が、具体的な問題解決に求められるためです。
また、専門性だけでなく、人生経験の豊富な調停委員は、当事者の感情や背景にある複雑な事情にも寄り添い、円満な解決への道を共に探ることができます。裁判官とは異なり、民間の視点を持つため、当事者にとってより身近で話しやすい存在として、本音を引き出しやすいという側面も持ち合わせています。
| 職業別/区分 | 民事調停委員 | 家事調停委員 | ||
| 員数 | % | 員数 | % | |
| 弁護士 | 1,442 | 18.7 | 1,664 | 14.5 |
| 医師 | 165 | 2.1 | 37 | 0.3 |
| 大学教授など | 82 | 1.1 | 188 | 1.6 |
| 公務員 | 166 | 2.1 | 328 | 2.9 |
| 会社・団体の役員・理事 | 583 | 7.5 | 914 | 8.0 |
| 会社員・団体の職員 | 447 | 5.8 | 745 | 6.5 |
| 農林水産業 | 57 | 0.7 | 85 | 0.7 |
| 商業・製造業 | 54 | 0.7 | 86 | 0.8 |
| 宗教家 | 82 | 1.1 | 174 | 1.5 |
| 公認会計士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士 等 | 3,002 | 38.8 | 2,601 | 22.7 |
| その他 | 396 | 5.1 | 1,156 | 10.1 |
| 無職 | 1,253 | 16.2 | 3,505 | 30.5 |
| 計 | 7,729人 | 100.0 | 11,483人 | 100.0 |
人格や見識に優れた人が「非常勤の裁判所職員」として任命される
調停委員は、最高裁判所によって任命される「非常勤の裁判所職員(国家公務員)」の身分を有しています。公平性と中立性が重視されるため、選任にあたっては、社会的な信頼が厚く、人格および見識に優れた人物が厳選されます。
また、非常勤の国家公務員である調停委員には、職務上知り得た秘密を厳守する「守秘義務」が課されています。これにより、調停の場ではプライバシーが保護され、当事者は安心して自身の状況や心情を話すことができます。
調停委員は当事者が指名できる?
調停委員は、当事者が特定の人物を指名したり、自ら選んだりすることはできません。これは、調停の公平性と中立性を確保するために重要な仕組みです。
裁判所は、事件の内容や当事者の状況を総合的に考慮し、最も適任と判断する人物を調停委員として選任します。家事事件であれば、書記官が調停委員の名簿の中から男女1人ずつに対して日程を打診し、調停期日に出席できる場合に、当該調停委員を選任しているようです。
【完全ガイド】調停当日の流れと調停委員との関わり方

調停は簡易裁判所や家庭裁判所で行われる話し合いの場で、第三者である調停委員が双方の意見を聞き、円滑な解決を目指す手続きです。しかし、実際に調停がどのように進むのか、当日どのような流れになるのか、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
以下では、家事事件の調停期日における具体的な流れをステップごとにわかりやすく解説します。
ステップ1:申立人と相手方は別々の待合室へ
調停当日、家庭裁判所の受付で手続きを済ませた後、申立人と相手方はそれぞれ別の待合室へ案内されます。これは、当事者同士が顔を合わせることで感情的な衝突が起こるリスクを最小限に抑えるための配慮です。多くの家庭裁判所では、申立人待合室と相手方待合室が明確に分けられ、当事者が安心して調停に臨めるよう、環境が整えられています。
調停委員に呼ばれるまでの間、当事者はそれぞれの待合室で待機します。待機中に、自身の主張を整理したり、話したい内容を最終確認するなどして準備をしましょう。
調停室への入室は、通常、申立人と相手方が交互に行われ、それぞれ30分程度の話し合いが2回程度繰り返されます。
ステップ2:調停委員が双方の部屋を交互に訪問し聞き取り
調停室に入った後、身分確認をした上で、以下の内容について詳しく聞き取りが行われます。
- 申立ての内容
- これまでの経緯
- どのような解決を望んでいるか
- 現在の状況や抱えている問題点
その後、20分から30分経過すると、申立人側が調停室を退室し待合室に戻ります。待合室への入室が確認できれば、これに続いて相手方に調停室に入室してもらいます。調停委員は申立人から聞いた主張の中から、相手方に伝えるべき内容を整理して伝達し、それに対する相手方の言い分や意見を聴取します。調停ではこのように、当事者同士が直接顔を合わせることを避け、調停委員が双方から交互に聴き取りを行う形式で進められます。
1回あたりの聞き取り時間は30分から40分程度が目安とされており、これを繰り返すことで、双方の主張の整理と争点の明確化が進められます。調停委員は、両者の話から対立点を把握し、解決の糸口を探るという重要な役割を担います。
ステップ3:問題点を整理し、解決策を探る
ステップ2で双方から聞き取った内容をもとに、調停委員は両者の主張のどこが一致し、どこが対立しているのかを明確にします。「争点整理」をすることで、問題の本質を掘り下げ、解決の方向性を見出していきます。
その上で、調停委員は法的な知識や社会経験に基づき、客観的な視点から問題解決のための選択肢や、落としどころとなる解決案を提示する場合があります。この解決案は、当事者間の合意形成を促すための提案の一つであり、決して強制されるものではありません。あくまで当事者双方が主体的に話し合い、納得できる合意を目指すためのものです。
調停委員が間に入り、冷静な対話を促すことで、当事者だけでは見つけられなかった妥協点や新たな解決策が見つかる可能性も十分にあります。相手方の真意や提案を落ち着いて聞くことができるため、円満な解決への道が開かれやすくなるでしょう。
ステップ4:合意できれば「調停調書」を作成して終了
調停委員を介した話し合いの結果、当事者間で合意ができる状況に至れば、調停は最終段階へ移行します。この際、調停委員会(調停委員と裁判官)が合意内容を最終確認した上で、当事者双方が異存なければ調停は成立します。合意内容は、裁判所書記官により「調停調書」として正式に作成されます。
この調停調書は、裁判の確定判決と同一の非常に強い法的効力を持つ重要な書類です。調停長所は強制執行することのできる「債務名義」の一つであり、例えば養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、これに基づき強制執行の手続きを行うことが可能となります。
調停調書が作成された時点で調停は成立し、一連の手続きは終了します。一度成立した調停調書の内容は後から変更できません。
調停をスムーズに進めるために押さえておきたい3つのポイント

調停を有意義な話し合いの場とし、円滑な問題解決を目指すためには、適切な心構えと事前の準備が不可欠です。
以下の項目では、調停をスムーズに進めるために特に重要となる以下の3つのポイントについて詳しく解説します。
感情的にならず事実を時系列で分かりやすく話す
調停の場で最も避けたいのは、感情的になることです。相手への不満や怒りが募り、感情的な言葉を発してしまいたくなる気持ちは理解できます。しかし、怒鳴ったり、ヒステリックに泣いたりといった態度は、調停の円滑な進行を妨げる原因となります。感情に任せた人格非難や誹謗中傷は、調停委員に悪い印象を与えかねません。感情的な発言ばかりでは話の要点が伝わりにくくなり、問題解決に向けた建設的な話し合いを進めることが困難になります。
そのため、トラブルの経緯を感情に流されず、客観的な事実に基づき、時系列に沿って分かりやすく説明することが非常に重要です。
自分の主張を裏付ける資料を準備しておく
調停において、口頭での説明だけでは、自身の主張や事実関係が調停委員に十分に伝わらないことがあります。特に複雑な経緯や金銭に関わる問題では、客観的な資料を提出することで、調停委員に正確に理解してもらいやすくなります。
離婚調停は話し合いの手続きであるため、証拠提出は必須ではありませんが、不貞行為やDVなどの証拠があれば、調停委員が事実を判断する上で重要な参考となり、話し合いを円滑かつ有利に進められる可能性が高まります。
相手の意見にも耳を傾け、譲歩できる点を探す姿勢を持つ
調停は、法律に基づいて勝ち負けを決める裁判とは異なり、当事者双方が話し合いを通じて合意形成を目指す手続きです。そのため、自分の主張ばかりを一方的に押し通すのではなく、相手の意見にも耳を傾け、理解しようと努める姿勢も大切です。
調停をスムーズに進めるためには、事前に自分の要望や条件を整理し、優先順位をつけておくことが不可欠です。
また、自分が譲歩する姿勢を見せることは、調停委員に協力的な印象を与え、相手の態度を軟化させる可能性も十分にあります。結果として、自分にとっても有利な条件での合意につながることも期待できるため、柔軟な姿勢で臨むことが大切です。全く譲歩のない姿勢では、調停委員からの協力を得られにくくなる点に留意しましょう。
知っておきたい調停制度のメリットとデメリット
調停制度は、紛争解決における有効な手段の一つです。しかし、裁判と比較した場合の利点と欠点を理解することが重要となります。ここでは、調停制度のメリットとデメリットを具体的に解説します。
メリット:手続きが簡単で費用が安い・非公開でプライバシーが守られる
調停制度には、主に以下の3つの大きなメリットがあります。
- 手続きが簡便
- 費用が安い
- プライバシー保護
まず、手続きに関しては、訴訟のように厳格な形式を必要としないため、当事者にとって利用しやすい点が挙げられます。
次に、費用面では、調停は訴訟に比べて低額で利用できる傾向にあります。また、弁護士を依頼せず、ご自身で手続きを進めることも可能なため、大幅に費用を抑えることができるでしょう。
最後に、調停は非公開で行われるため、プライベートな内容が外部に漏れる心配が少なく、当事者のプライバシーが保護されるという点も大きなメリットです。
デメリット:相手が出席しないと進まない・必ずしも合意できるとは限らない
調停制度には利点がある一方で、いくつか注意すべきデメリットも存在します。特に、話し合いを前提とする性質上、以下の2点が挙げられます。
- 相手方が出席しないと手続きが進まない
- 当事者間の合意に至らない可能性がある
調停はあくまで話し合いを原則とする手続きであるため、当事者双方の出席が不可欠です。
相手方に出席を強制することができず、欠席が続く場合、調停は事実上進まなくなり、最終的に不成立となります。
また、調停委員は、当事者間の合意形成をサポートする中立な立場であり、裁判官のように判決を出す権限はありません。そのため、双方の主張が大きく食い違い全く譲歩が見られない場合は、合意に至らず調停が不成立に終わる可能性もあります。調停が不成立となった場合、問題を解決するためには、改めて訴訟(裁判)を提起するなど、別の法的手続きを進める必要があります。
「調停委員と合わない…」と感じたときの対処法
調停委員は公平中立な立場で話し合いをサポートしますが、「相性が合わない」と感じるかもしれません。もし調停委員の言動が不公平である場合の対処法を解説します。
調停委員の変更は原則としてできない
調停委員は、紛争解決を支援する中立かつ公平な第三者です。そのため、ご自身の主観的な理由で、調停委員の変更を求めることは、原則として認められていません。
ただし、調停委員自身の体調不良や任期満了といった、やむを得ない客観的な事情がある場合には調停委員が変更されることはあります。
不公平な言動が続く場合は裁判所書記官に相談する
調停委員の言動に偏りや高圧的な態度が見られ、不公平さを感じた場合は、裁判所書記官に相談することを検討しましょう。裁判所書記官は、調停手続きが適正に進行するよう、裁判官や調停委員と協力して手続きを進める重要な役割を担っています。
これにより、書記官を通じて調停委員に対して指導や注意喚起が行われる可能性があります。ただし、この相談によって必ずしも状況が改善されるとは限りません。
どうしても不安な場合は弁護士に相談する選択肢も
調停委員とのやり取りに強い不安を感じたり、提示される解決案が法的に妥当か判断できなかったりする場合、弁護士への相談は有効な手段です。弁護士に委任することで、法的な観点から自身の主張を整理し、調停委員へ論理的に伝えられます。また、弁護士が代理人として調停に同席・出席することで、調停委員や相手方との直接的なやり取りによる精神的負担が軽減されます。さらには、もし調停が不成立に終わった場合でも、弁護士は代理人としてその後の訴訟手続きまで見据えたサポートをスムーズに行うため、安心して次のステップに進むことができます。
調停手続は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、調停委員の基本的な役割、どのような経歴を持つ人物が選任されるのか、そして調停が実際にどのように進行するのかについて詳しく解説しました。
調停をスムーズに進め、納得のいく解決を目指すためには、調停委員の役割を正しく理解し、適切な姿勢で臨むことが重要です。調停委員の助けを借りながら、冷静かつ建設的な話し合いを進めることで、複雑な紛争も円満な解決へと導くことができるでしょう。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。